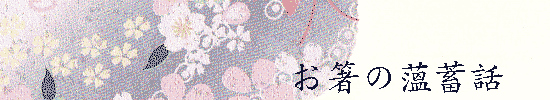 |
| 【 お祝いの箸(箸初め) 】 箸は「生命の杖」と言われ、日本人は誕生から墓場までを、「箸に始まり 箸に終わる」といわれるくらい、生活とは切り離すことの出来ない結びつきが あります。 その中でも特に、人生にとって「おめでたい」行事の祝い膳には、新春真っ 先に芽を出す、清浄で縁起の良い「柳(家内喜)」で作った白木のお箸を使い ます。この白木のお箸は、原則として一度使用したものは捨てることになって おり、これは精神的な不浄感を払うためとされています。 このように、人生の節目を祝うためには、それにふさわしい箸を選択してい るのです。 近年、食事の近代化や、欧米化が進む中で、お祝いの膳も華やかになっています。 こういったお祝いの時、箸を通じて伝承されてきた、日本人のための食文化を 新しい観点から見直し、さらに継承するべき意義を知り、新しい生活の知恵と して再生するべきだと思います。 日本人の一生は「箸に始まり箸に終わる」と言われるように、人生の始まりは 「箸初め」から始まると言ってもいいでしょう。 箸初めは、地方によって「箸そろえ」「箸立ち」とも言われます。どれも、 生後100日目(7日目・120日目)に行うことになっています。 この儀式は、早く食べられるようになって、一人前になってほしい。そして この子が一生食べるものに不自由しないように、という願いを込めてかわいい 茶碗にお椀、そして柳箸(杉箸も)など、すべて新しいものを揃え、赤飯に 尾頭付きの鯛という献立の祝い膳です。 この儀式は、宮中においても「お箸初め式」として行われています。 |
