



道徳起源論から進化倫理学へ
(『哲学研究』566号掲載)
内井惣七
総目次
第一部 道徳起源論と還元主義 第二部 規範倫理学における還元主義 21 合理性──最大化か満足化か? 1 ダーウィンの「危険な考え」 13 規範倫理学と還元主義 22 進化における「最適化」 2 シュルマンのダーウィン批判 14 なぜ還元主義か 23 最大化モデルは不要か 3 科学としての倫理学 15 道徳的とは 24 デネットの「倫理的応急処置」 4 ダーウィニズムの理解 16 行為原則の必要性 25 普遍化可能性と合理性 5 生物学的利益と人間的利益 17 道徳性と普遍化可能性 26 コミットメント関係と信頼 6 道徳感覚あるいは良心の起源 18 すべての人の善の考慮 27 信頼と社会的知性 7 ダーウィンは何を目指したのか 19 善の普遍化可能性と善の平等な扱い 28 普遍化可能性に対する示唆 8 ダーウィンの仮想心理学 20 還元主義倫理学の問題点 29 善の普遍化と重みづけ 9 ダニ取り鳥の行動戦略 文献 30 善の重みづけと社会的知性 10 社会性と知性を仮定すれば 31 善の重みづけについての規約主義 11 行動生態学からの支持 32 進化倫理学と還元主義のプログラム 12 進化心理学 文献 文献
第一部 // 第二部 // 第二部(続)// 還元ノ−ト // FINE lecture
第一部 道徳起源論と還元主義
1 ダーウィンの「危険な考え」
日本では進化論に関心をもつ人は多いようだが、哲学の研究者で自分の研究に進化論の視点を取り入れて本格的な議論を展開する人はまだ少ないようである。日本の哲学論壇の「常道」として、欧米の有名な研究者が華々しい成果を発表すると、その尻馬にのって訳者や紹介者が一時的に騒ぐ、という傾向があるが、哲学と進化論との結合についても、いまその傾向が時流に「なりかけて」いるようである。わたしが念頭においているのは、認知科学の哲学ですぐれた仕事をしてきたアメリカのダニエル・デネットの最近の一連の著作である。昨年から今年にかけて、『心はどこにあるのか』(原著1996)と『解明される意識』(原著1991)という翻訳が相次いで出版され、もう一つの『ダーウィンの危険な考え』(原著1995)もいま翻訳の最中だと聞いている。この最後の題名はたしかに興味をそそる。ダーウィンの進化論のどこが「危険な考え」だろうか。「危険」とはどういう意味だろうか。
はじめにお断りしておくが、わたしは小論でこの「時流」に便乗した議論をしようとしているのではない。わたしは、二十年ほど前から進化論に関心をもちはじめ、断続的に文献を読んだり講義でふれたりしてきたのだが、数年前にダーウィンやウォレスの進化学説の形成史を調べたことがきっかけとなって、いくつかの成果を得ることができた(内井1992、1993)。最もまとまったものは『進化論と倫理』(世界思想社、1996)である。デネットの進化論的視点からの仕事を知ったのはこの本の出版の後であり、いくつかの重要な論点について彼とほぼ同じ見解に達していることを知って心強く感じたので、話のマクラに使わせてもらったにすぎない。しかし、デネットのいう「ダーウィンの危険な考え」がわたしの前著および小論のテーマとよく重なっていることは間違いがない。
ここである程度の種明しはしておく必要があろう。「危険な考え」とは、デネットの理解では、「進化のすべての成果はアルゴリズム的過程の結果として説明されうる」(Dennett 1995, 60)という考えであり、「アルゴリズム的過程」とは、もっとわかりやすく言えば、「心を前提しない、機械的手続きによる過程」のことである。認知科学に最大の関心をもつデネットは、自然淘汰の意義をこのように理解し、生物種の生成だけでなく、心を含むすべての創造物の「設計」の説明に応用できるという、ある種の還元主義を擁護しているのである。しかし、小論では、道徳的心性の起源の説明と、その説明が規範倫理学に対してもつ意義のみにテーマを限定することにしたい。言うまでもなく、人間が道徳をもつことも、人間の「設計」の重要な一部である。そして、わたしは、(前著ではまだ知らずにいた)デネット流の還元主義(少なくとも倫理学における)の支持者である。それがどういうことであるかは、以下でもっと詳しく論じる(「人格」概念についてのパーフィットの還元主義も関係が深いが、これについては奥野1997-98 を参照)。
2 シュルマンのダーウィン批判
さて、ダーウィンが『人間の由来』(1871、第2版1874)第一部で展開した道徳起源論については、前述のわたしの著書をはじめとして、これまでに何度も紹介した(内井1997、1998a、Uchii 1997b)ので、同じことをくり返すのも芸がない。そこで、ここでは、わたしが京大哲学科の書庫で見つけた19世紀末期のダーウィン批判を素材として、ダーウィン説の紹介、批判、およびその意義の解説を行なってみよう。
ジェイコブ・グールド・シュルマン(Jacob Gould Shurman)といってもだれも知らないであろう。わたしにも、何者かよくわからない。わかっているのは、(1)おそらく19世紀後半にイギリスで教育を受け、(2)当時はひとかどの学者だったジェームズ・マーチノー(James Martineau, 1805-1900)という倫理学者、宗教家の弟子であり、(3)後に米国コーネル大学の学長になり、そして(4)1920年5月に京大を訪れて何か講演を行ない、自分の著書を寄贈した、というだけである。その著書は、『ダーウィニズムの倫理的意味』(1887)というタイトルで、寄贈されたのはその第3版(1903)である。注も文献表も索引もない本であるが、読んでみるとけっこう面白い。著者の意見には同意できないが、当時の哲学者によるダーウィンの道徳起源論の受けとめかたとして十分理解できるし、批判の議論にも(やはり同意できないが)見所はある。現代の哲学者(とくに倫理学者)でも、この手の議論に説得力を感じる人はかなり多いのではないか、という感触をわたしは持っている。そして、肝心な点は、彼の議論の基本線が、事実問題についても倫理問題についても「反還元主義」であるということである(ただし、彼が「還元主義」という言葉を使うわけではない)。
3 科学としての倫理学
では、シュルマンの議論をみていくことにしよう。彼の本は6章よりなる。第1章は「倫理学の方法、進化論的およびその他」と題されており、倫理学がどのようなタイプの「科学」でありうるかという問いから始めて、科学としての倫理学は歴史科学でしかありえない、とシュルマンは論じる。原初的な段階の人類における倫理から、今日に至るまでのいろいろな段階の倫理を歴史的に調べて記録するのがその務めである。もっとも、これとは別に、思弁的な道徳哲学はありうる。しかし、科学的に確かめられた事実に基づかない道徳哲学は不毛である。
では、ダーウィンが、進化論の観点から動物と人間の諸能力の間の連続性を強調し、古来人間独自の能力として強調されてきた道徳的能力さえ例外ではないと主張した道徳起源論は、このような科学としての倫理学になり得ているだろうか。ダーウィンの進化論的考察によって科学としての倫理学の基盤が築かれたという見解もあるが、ダーウィンの考察には二つの不備がある、とシュルマンは批判する(Shurman 1903, 37)。
(1)ダーウィンにおいては、歴史的方法が科学的倫理学の方法として使われているというよりは、彼の生物学的仮説を確証する手段としてしか使われていないこと。
(2)また、彼の考察は、思弁的な功利主義の影響のもとにあり、歴史的方法があらかじめ決まっている結論を導くための手段としてしか使われていないこと。
これら二点は、第1章で論証されるわけではなく、これから論証されるべきことの予告である。しかし、この時点でまず気づくことは、シュルマンの言う「科学としての倫理学」と「道徳哲学」の区別と関係はあまり明瞭でないということである。科学としての倫理学ということで彼が意味しているのは、おそらく、人間の道徳的能力がどうあるか、そしてそれが歴史的にどう発達あるいは変化してきたかということの事実に関する探求であろう。この時代、こういう探求の必要性を感じ、実際にある程度実行した人も何人か目につく。例えば、進化倫理学という言葉で真っ先に連想がいくハーバート・スペンサーは、彼の「総合的哲学」の一部として、少なくとも意図においては、このたぐいの経験的探求が不可欠であると考えていたであろう(スペンサー説に対する最も周到な検討と批判は Sidgwick 1902 を参照)。彼も、「科学的な基礎」の上に、世俗化された規範倫理を確立することを時代の急務と認めていたのである。あるいは、もっと本格的に社会学的、人類学的研究を実行したものとしては、ウェスターマークの大著『道徳的観念の起源と発展』(1906、1908)がある。しかし、ウェスターマークの研究にも、いたるところに概念的あるいは思弁的分析が織り込まれており、純粋に経験的な探求とは言いがたい。
シュルマンに戻れば、彼の最も物足りない点は、「科学的倫理学」と「道徳哲学」との関係についてまったくヴィジョンが示されていないことである。「道徳哲学」の目指すべき課題さえウヤムヤのままである。また、(2)の点についてあらかじめ注意しておけば、生物学的な文脈で言われる「有用性」と倫理的あるいは社会的な文脈で問題になる「有用性」とを混同しないように気をつけなければならない。このたぐいの混同は、一般の人々や二流の哲学者ばかりでなく、スペンサーやダーウィン自身においてさえしばしば見られる(後述)。
4 ダーウィニズムの理解
シュルマンの第2章は「進化論とダーウィニズム」と題された、進化論とダーウィンの自然淘汰説の一般的な解説である。彼の意図は、自然淘汰説の批判にあるのではなく、この説が正しいものと仮定した場合、それが倫理学にどのような意義をもつのかを探ることにある。そこで、われわれが注意しなければならないのは、自然淘汰説(しばしば「ダーウィニズム」という語を同義で使う)に関するシュルマンの理解に問題がないかどうかである。そのような問題点が明らかになってくるのは、実は次の第3章「ダーウィン説の哲学的解釈」においてである。
しかし、問題点の指摘に入る前に、現代の観点から歴史的文献を批判する際に心すべき二、三の注意を述べておくことが必要であろう。現代のわれわれは、ダーウィン自身やシュルマンの知らなかったことを数多く知っており、彼らがそれを知らなかったことを指摘して批判してもあまり意味がない。また、まともな遺伝学が成立する以前に自説を展開したダーウィンが、自然淘汰説の持つ意義を十分に把握しきれていなかったり、多くの点でアイマイであったりしたこともしかたがない。こういった点については、シュルマンに対してもわれわれは公平でなければならない。
しかし、ダーウィンの自然淘汰説が現在なお高く評価され「ダーウィニズム」がまだ命脈を保っているのは、理由のないことではない。その最も重要な理由は、おそらく、小論の最初でふれたデネットあるいはわたしの支持する(健全な)還元主義の説明力、成功、そして簡明さにある(健全でない還元主義については後にふれる)。とくに、あらかじめ目的や設計や方向性を前提せずに、「あたかも特別に設計されたかのように」うまくできているという適応を説明できることを、ダーウィンは自説の強みだとして一貫して主張した。ところが、ライエル、エーサ・グレイをはじめとするダーウィンの19世紀の支持者たちは、それに加えて何らかの目的論を読み込んだ「非ダーウィニズム」の形で自然淘汰説を理解しようとしたのが実情である(例えば、ボウラー1992 を参照)。ダーウィン自身の観点からみても、現代の観点からみても、「ダーウィニズム」というとき、還元主義、非目的論は譲れない本質的な特徴である。
以上の点を押さえた上でシュルマンに戻ろう。彼の理解では、自然淘汰の役割は、進化の素材として与えられた多数の変異のうちから、生物がその環境に適応していくのに有用な変異を累積し、生物の形質を変えていくことにある。科学はそのような累積がいかに行なわれるかを説明するが、哲学は変化のもとがどこにあるかに着目する、とシュルマンは言う(Shurman 1903, 76-77)。自然淘汰は、素材がなければ何も生み出しえない消去の過程にすぎず、創造の過程ではない。
ところが、この素材を生み出す種の可変性を説明せずに前提し、可変性や変異の原因を示さない自然淘汰説は、超自然的な起源を前提した目的論とあまり変わらない、とシュルマンは断じる。結果は変容した原因にすぎないのだから、その結果は潜在的に何らかの形で最初から存在していたはずである(Shurmann 1903, 98)。この点を看過して、物理的原因と偶然によって新しい形質や種が生み出されると見なすダーウィン説は、機械論のように見えて実はそうではない。以上が、シュルマンによる自然淘汰説の「哲学的解釈」である。
この「哲学的解釈」が、つい先ほどわたしが押さえたばかりのダーウィニズムの本質からどれほどかけ離れているかは、すでに明らかであろう。これは、シュルマンをこきおろすためだけに言っているのではない。彼が自信をもって展開したこの解釈は、この時代には、哲学者にとってだけでなく、一流の生物学者や博物学者にとってさえ、ダーウィニズムの正当な理解がいかにむずかしかったか、ということの理解の文脈では、一つの意義ある証拠となりうる。「結果が原因のうちに潜在している」という古くさい形而上学的原理についても、おそらくシュルマンだけを責めるわけにはいかない。スペンサーも似たりよったりの原理をしばしば持ち出している。
このたぐいの議論が見落としているのは、形質や変異の複雑な組み合わせ(およびその組み合わせを持った生物がおかれた環境)によって、十分新しい「結果」が生じうるという事実である。ここにはいかなる論理のまやかしもない。例えば、現代のわれわれが知っているチューリング・マシンという簡明なモデルを使えば、この機械を動かすプログラムはたった数個の単純な動作を指示する命令の連鎖で書くことができる。しかし、与えられた連鎖にいくつか「変異」を加えるだけで、もとのプログラムとはまったく異なる計算を行なう新しいプログラムが生じる。また、比較的単純な計算しか行なわないサブルーチン(部分的プログラム)を組み合わせていくことにより、可能な計算をすべて行なえる万能プログラムをつくることさえできる(内井1989、9章参照)。
ついでに、「変異 variations」というキーワードについても注意を加えておきたい。現代の読者は、ダーウィンが「変異」というとき、「遺伝子レベルでの突然変異」という連想をしがちである。この連想、あるいはこの連想に基づくとしか思えない発言は、わたしもいろいろな学会で何度も見聞きした。しかし、ダーウィンが変異と言うときは、この突然変異以外に、現代の言葉でいえば遺伝子の組み合わせの違いによって生じる表現型レベルでの多数の(そして大小の)違いが含まれていることを忘れてはならない。ダーウィンの「変異」は突然変異よりはるかに豊かな内容を持っている。自然淘汰によってある種のなかで定着する形質(や行動)は、突然変異という稀で偶然に依存する原因だけでなく、大多数は組み合わせから生まれる豊かな可能性のなかからの淘汰によって生じうる。近年明らかにされてきた免疫系の驚くほど多様な対応(抗体の多様性)も、文脈は違うが、基本的にはこの組み合わせの妙に基づくのである(立花・利根川1990、119-134)。
また、複雑適応系の研究でサンタフェ研究所で名をあげたジョン・ホランドの「遺伝的アルゴリズム」(ある問題解決のためのコンピュータプログラムを直接書く代わりに、プログラムを「進化」させて適切なプログラムを生み出すための手続き)においても、プログラムの「進化」のための有力な素材になるのは、「突然変異」よりはむしろ種々の組み合わせを作り出す「交差」とか「逆位」という遺伝学とのアナロジーそのままの、組み替えの手続きである(Holland 1975, ch.6. もっとわかりやすい解説は、ワ−ルドロップ1996、221-255 を見よ)。
シュルマンがこういうことに考えが及ばずにダーウィンを批判するのはもちろん仕方がない。しかし、現代において、いやしくも「進化・・学」という名を標榜する学会で「突然変異と自然淘汰だけでは何も説明できない」という声が多くあがるのは唖然とさせられる。もっとも、わたしが属する「科学哲学会」も似たようなもので、「今日は進化についてお話をうかがったが、退化についてはどうですか?」という質問が出る。「進退」という日常言語の対で進化を理解しようとすることは、ダーウィニズムのみならず進化自体の無理解の素朴な一例である。これも、シュルマン流の「解釈」と縁の深い誤解である。
すでにふれたように、19世紀の大多数の人々は、ダーウィンの支持者も含めて進化に進歩を読み込もうとし、ダーウィンの「危険な考え」を結果的に骨抜きにしようとした。スペンサーはその典型である。しかし、超自然的な目的論とダーウィニズムが大差なくなるような理解でダーウィニズムを捉えるのでは、「ダーウィニズムの倫理的意味」などとても論じられない。ここでは、幸運な突然変異の連続によらずとも、すでにあるものの組み合わせによって真に新しいものが生じうることを理解しよう。これを押さえないと、非道徳的なものからいかにして道徳的なものが生じうるのかは絶対にわからない。
5 生物学的利益と人間的利益
さて、シュルマンは、第4章「ダーウィニズムと倫理の基礎」において、いよいよ本題に入る。進化に関するダーウィン説、とくに自然淘汰説を仮定した場合、何らかの倫理学説が導かれるのだろうか。ダーウィン自身が認めるように、自然淘汰説はマルサスの『人口論』にアイデアを負い、個体の形質が生存闘争において有用かどうかという概念を前提する。自然淘汰は、生物学的効用に依存するのである。人間に適用された場合はどうだろうか。直立歩行、知性の発達、道徳感情の出現等、いずれも人類の生存と繁栄にとって有用であったことは容易にわかる。かくして、人間に適用された自然淘汰説は、人間の行動原則を有用性あるいは功利性におく功利主義倫理へと導く。ただし、倫理学説の功利主義が快楽説価値論をとったのに対し、進化論に基づく功利主義は生存闘争における力を有用な価値とみる違いはある。以上がシュルマンの分析であり、小論3節の(2)で予告された主張の論拠とされる。
この議論も、「有用」とか「有利」という言葉の日常的な意味と、それが自然淘汰説での専門用語に転用されて使われた場合の意味とを混同した、説得力のない議論である。もちろん、この判断も、20世紀の生物学を知っているわれわれには比較的容易でも、19世紀の人々にはむずかしかったかもしれない。簡単に説明すれば、ある形質がそれを持つ個体にとって「生存闘争において有利である」ということは、現代の自然淘汰説においては、その個体が与えられた環境においてもつ「繁殖率が(他の個体に比べて)大きい」というほどの意味である。これは、ある人が社会生活において選ぶこの行為があの行為に比べてその人にとって有利である(幸福に貢献する、経済的な利益をもたらす、それゆえ選ばれるべきである)、というたぐいの価値判断ではない。自然淘汰の文脈でいわれる有用性――生物学的利益――は、子孫を次代に残せる見込みの大きさを言っているにすぎない。
他方、功利主義でいう有用性あるいは功利性は、ベンサムやミルなどの古典的功利主義においては、快楽説価値論を前提した上で、「より多くの快(あるいは少ない苦)をもたらすのに貢献する、そしてそれゆえ(倫理的に)望ましい」という純然たる価値概念である。ダーウィンは、「有用性」とか「有利さ」という言葉は使っても、この功利主義の価値概念まで借用しているわけではない。かくして、自然淘汰説がわれわれを功利主義倫理へと導き、そのしかけは自然淘汰説に密輸入されていた功利性の概念である、というシュルマンの嫌疑に対しては、ダーウィンは明らかに「シロ」であるように見える。
しかし、話がこれで簡単に終わってしまうわけでもないことを注意しなければならない。実は、「進化」に「進歩」を読み込んで進化倫理学を確立しようとしたスペンサーだけでなく、ダーウィン自身にも進化倫理学のある種の試みが見られるのである。例えば、自然淘汰説の着想を得たのとほぼ同じ頃(1838年)に書かれたノートには、自分の自然淘汰説によって倫理学の道徳感覚説と功利主義とを統合できるという趣旨のことが書き残されている(内井1996、63-65)。また、円熟期の『人間の由来』においても、生物学的条件に即した「一般的善」の規定が提案され、道徳とつなげようという趣旨が読み取れる箇所がある(内井1996、65-66)。しかし、生物学的利益と倫理学でいう功利性にはある種のアナロジーがあるにしても、どう考えても直結はしない。たかだか、功利性あるいは人間的利益のためには(人間という種にとっての)生物学的利益も無視できない、という弱いつながりが認められるにすぎない。したがって、ダーウィンが部分的な示唆と着想のみにとどまって、規範的な進化倫理学にほとんど踏み込まなかったのは賢明なことであった。
そこで、シュルマンの嫌疑に対する回答は次のようにまとめられよう。「有用性」という言葉のダーウィンの用法には少々アイマイなところがあるとはいえ、前述の生物学的利益(繁殖率の大きさ)以上の意味を要求する用法は、自然淘汰説のうちにはない。したがって、自然淘汰説が功利性の概念を使っているという分析も、自然淘汰説から功利主義倫理が導かれるという主張も、いずれもナンセンスである。しかし、自然淘汰説が規範倫理学に関わりを持つかどうか、持つとすればどのような形でかという問いは、それとは独立に有意義な問いでありうる。問題は、基本的に事実問題に関する仮説である自然淘汰説から、規範や価値の問題に答えるための「功利性」その他の概念までをどのようにつなぐかである。ちなみに、わたしのいう還元主義の倫理学は、論理的誤謬や単なるアナロジーでこのつながりをつけようとする試みではない。
6 道徳感覚あるいは良心の起源
シュルマンの第5章「ダ−ウィンの倫理的考察」は、彼の本の中で最も価値の高い部分である。彼は、ダーウィニズムの倫理的含意とダーウィン自身の倫理学的見解とを区別して論じるが、この章では後者、つまり『人間の由来』第一部の道徳起源論が検討される。
そこで、まずダーウィンの道徳起源論の概略を紹介しておく。ダーウィンは、まず人間の能力と他の動物の能力との連続性を押さえる。人間は多くの高度な能力をもつが、それらの能力は少なくとも萌芽的な形でほかの動物にもある。違いは程度の差にすぎず、断絶した質の違いではない。人間をほかの動物から決定的に分かつ能力として強調される道徳的能力も例外ではない、というのがダーウィンの重要な主張である。彼は、社会性を備え、かつ高度な知性を備えた動物なら、善悪を見分け、良心に従って行為を規制する道徳能力を獲得するはずだと論じ、その獲得の過程を心理的に描いてみせる。カギとなるのは、自他の感情を現在の自分のうちで再現する共感能力を含む社会的本能の永続性と、知性に助けられた記憶の保持、および自他に関する知識が結合した作用である。ダーウィンは、社会的本能が他の一時的に強い欲求を満たしたために充足されなかった場合には、その不快感が記憶に残り、また他者の不快感も共感によって自分のうちに再現され、これらが社会的本能の永続性ゆえに思考のうちで強化されて優勢となって、特有の後悔や自責の念を生み出し、以後の行為決定を規制する作用をもつという。これが良心の起源にほかならない(より詳しくは、内井1996、23-41、内井1997を参照)。
これに対するシュルマンの批判は次のとおりである。ダーウィンの道徳起源論は、生物一般に関する議論や知性の起源に関する議論とは異なる性格をもつ。下等な生物も人間も、生命と知性に関しては共通性をもつ。そして、その共通性の枠内での変異が自然淘汰により集積されて人間の複雑な体制となり、高度な知性となりうる。ところが、道徳の場合、ダーウィン自身も、道徳的でない動物から道徳的な動物が生じること、良心を持たない動物から良心をもつ動物が生じることを問題にしていると認めており、先祖の非道徳的動物と末裔の道徳的人間の間にはギャップがある。ダーウィンは、このギャップを知性と社会的本能の結合による心理的プロセスによって埋めようとしているのだが、このプロセスは純粋に想像上のものでしかなく、彼の進化論の他の場面での推論とは異質である。これは科学とはいえない。彼は、道徳性が非道徳的な材料からいかにしてつくられるかを示そうという不可能な企てを試みている。以上が、シュルマンの批判の本線である。
シュルマンはさらに、この結論が、良心の形成過程に関するダーウィン説の細部を検討しても具体的に確認されるという。「良心」という言葉でダーウィンが何を意味するのかはっきりしないので、ダーウィンが提示する形成過程でいったい何が生まれるのか見るほかはない。ダーウィンの中心的な主張は、社会的本能の永続性が記憶のなかで大勢を制することにより、一時的に強い欲求に負けたことに対して後悔の念が生じるということであり、これをもって良心の起源の説明としている。社会的本能の永続性と一時的欲求に対する優位性についての前提にも疑問があるが、これを認めてさえ、ダーウィンの議論は失敗している。ダーウィンが前提している知的かつ社会的動物は、非道徳的であることを銘記しなければならない、とシュルマンは注意を喚起する。各時点で強い方の衝動に従ったこの動物は、衝動の強さに比例した快楽を得てそれが記憶に残り、後悔の念が生じる余地はないかもしれない。彼の議論で後悔の念が生まれるとされるとき、この想定は道徳的存在の経験を借りているにすぎないのである。すぐれた知性をもつこの動物は、過去の経験と現在の経験とを混同するはずはなく、いま社会的本能が優勢であるからといって、過去に優勢だった利己的衝動の満足をいまの社会的本能の強さと比べて後悔するのは、不十分であるか誤った反省のしかたのせいでしかなかろう。それぞれの衝動の持続時間を考慮したとしても、持続時間の長さがなぜ後悔を生み出すのか説明にならない。このあたり、シュルマンの舌鋒は鋭い。
そこで、結局、ダーウィンの説明はそれぞれの衝動の相対的な価値の序列を前提しないと説得力がない、とシュルマンは論じる(これは、マーティノー説の援用である。Sidgwick 1902 参照)。社会的本能は利己的な本能より高い価値を与えられているので、この動物は低い衝動に従ったときに後悔をするのである。しかし、これはすでに道徳的存在の経験にほかならない。かくして、良心の起源に関するダーウィン説が説得力を持つように見えたのは、読者がダーウィンとともに、この道徳的存在の経験を仮定し、非道徳的動物の意識のうちに道徳的意識を読み込んだからにすぎない。以上がシュルマンの見解である。
7 ダーウィンは何を目指したのか
そこで、シュルマンの批判に対してダーウィン弁護を行なってみたい。まず、シュルマンの批判の論点を次の四つに整理しておく。
(1)知性の発達の説明と道徳性の発達の説明とは論理が異なる。
(2)仮想的な心理的プロセスを持ち出す説明は思弁であって科学ではない。
(3)非道徳的なものから道徳性はうまれない。
(4)ダーウィンは仮想的な心理プロセスのうちに道徳的存在の経験を読み込んでいる。
まず、最も一般的な(1)の論点は、哲学のある種の公式の誤った適用にあると考えられる。その公式とは、「有(すでにあるもの)からの程度の増大は可能だが、無から有が発生するのは不可能だ」というたぐいの一般化である。この公式を一般的に維持することは不可能である。例えば、非生命からどこかで生命が発生したことは現在では常識である。
次に、この公式を適用するにしても、シュルマンは知性や道徳性を実体化しすぎている疑いが強い。ダーウィンは、知性や道徳性をまとまりのあるある種の実体と見なすわけではない。経験主義者のダーウィンは、いずれについても、わずかずつの差でつながる一群の現象の連続的なスペクトラムがあり、ある現象が一定の条件を満たしたなら知性と呼べる、別の線を超えたら道徳性と呼べるというたぐいの議論をしているはずである。「知性」も「道徳性」も、人間の関心に従って名づけられたある程度恣意的な区別である。もちろん、いずれの区別もシャープな線引きができるわけではない。しかし、スペクトラムの下の方では知性も道徳性も明らかに認められず、上の方ではどちらも明瞭に認められるというたぐいの区別である。道徳性だけでなく、知性もどこかで無から有に転じる。
もっと重要な点は、道徳性とは、ある一つの単純な本質で規定できるものではなく、一群の(それ自体では非道徳的な)特性の集まりあるいは組み合わせに付けられる名前だという立場をダーウィンが擁護していることである。これがダーウィンの「還元主義」にほかならない(彼が自分でそう呼ぶわけではない)。これに対し、シュルマンは道徳性は非道徳的なもので定義もできないし、それに還元もできないという非還元主義をとっている。ではいずれの立場が妥当であろうか。
この問題は、いかに為すべきかという規範倫理学の問題ではなく、われわれが道徳的、非道徳的と呼ぶ区別はどのような区別かという、なかば概念的、なかば経験的な問題であることに注意したい。そして、とくにダーウィンは、その区別を用いて判断し行動する能力はいかに進化しえたかという経験的な問題を解こうとしている。これは、シュルマンも認めるとおり、経験に訴え科学的に答えるほかはない。そこで、妥当性の判断は、大部分事実の法廷に持ち込まれるはずである。最近の霊長類学のいくつかの成果を参照しても、ダーウィンの見解は支持こそされ、くつがえされる気配はまったくないとしかわたしには思えない(de Waal 1996)。非還元主義の形で問題を立てると、ダーウィンの問題は経験的に解きがたくなるというのがわたしの感触である。もちろん、これは「感触」であり「論駁」ではない。非還元主義で問題が解けるという方には、その立証責任はお任せしたい。
ちなみに、ダーウィン以前の伝統的な倫理学でも(いま論じている、概念的、事実的問題に関する)還元主義の見解はそこここで表明されている。例えば、「良心」に関するミルの見解は、ダーウィンのそれと非常に近い(内井1996、26)。古いタイプの道徳感覚説は、善悪、正邪を見分ける独特の感覚(道徳感覚)を要請したが、道徳感覚のはたらきは、より基本的な多くの能力の複合的な作用に還元されるというのがダーウィンのポイントであり、それらの能力は知性と社会的本能という二つのグループに分類されたのである。かくして、シュルマンのように、哲学的公式のあやふやな適用によってダーウィンの還元主義を退けることはできない、とわたしは考える。
8 ダーウィンの仮想心理学
次に、ダーウィンは科学的推理ではなく思弁的な仮想心理学で道徳の起源を論じたという、シュルマンの(2)の批判を検討しよう。もちろん、ダーウィンの書き方にも問題はあるのだが、ダーウィンの記述を文字どおりある一個体のうちでの心理的プロセスと理解すべきではなかろう。多くの世代にわたる淘汰を経て、ダーウィンがいうような心性が形成されるという進化的な視点をとらなければ話が合わない。簡単に言えば、社会的本能に反する行為を数多くおこない、後悔、自責の念、あるいはそのたぐいの感情を感じず、自分の行為パターンを他者の反応や利害の考察によってある程度規制できないような個体は、次世代に自分の子孫を残せる見込みを減少させ(生物学的に不利)、だんだん数を減らす。逆に、適切なしかたで「利他的」行動をとれる個体は生物学的に有利で数を増やせる。
しかし、いかに社会的とはいえ、強力な利己的傾向をもつ動物がこのたぐいの行動パターンをとれるためには、その行動を決定する心理的要因のうちに、利己的傾向に十分対抗できるだけの強力な要素が不可欠である。この点は、われわれ自身の内省によって示唆されるだけでなく、イヌやチンパンジーなどのほかの社会的動物に関する観察からも経験的に支持される。ダーウィンの心理的考察は、この要素(道徳感覚、良心、あるいは何と呼んでもよいが)がある種の複合体であり、その構成要素(素材)のどれをとっても、人間以外の動物の能力のうちに見られることを指摘し(すなわち、ここでも還元主義の路線をとり)、条件次第では自然淘汰で発達しうるではないかと言っているのである。ちなみに、社会的本能の永続性がカギになるのは、個体の心理のうちで持続する時間というよりは、むしろ進化の過程のうちでの時間だからであろう(社会的本能が永続しなければ、この動物は社会的でない別の動物になる)。そこで、進化論の観点から論証すべきことは、その種のはたらきを行なう複合的心性を持つことが生物学的に有利である、つまり生存闘争のなかでそれを持つ個体数を増やせる見込みが高いということである。ダーウィンは、多くのヒントを示唆しつつも、この論証は行なわなかった。しかし、20世紀の進化生物学の成果は、この論証が可能であることを示している。
動物の「利他行動」の説明については、今世紀の後半にいくつかの顕著な成果が得られた。一つは、(不妊の)はたらきバチがコロニーを維持し、次世代の個体(はたらきバチと濃い血縁関係がある)を育てる「献身的」な行動が、はたらきバチが自分の子孫を残さないにもかかわらずなぜ進化しえたかを「血縁淘汰」によって説明したことである(W.D.Hamilton 1964)。もう一つは、血縁関係のない個体の間でなぜ協力関係や利他行動が(進化的に)定着しうるかを説明した「相互的利他性」の考え方である(R.Trivers 1971)。いずれもゲーム理論の数学が進化論で威力を発揮する一例であり、この方面で多くの重要な貢献をしたのは、メイナード-スミスというイギリスの数理生物学者である。以下では、形質と同じく行動パターンも遺伝子に乗ると仮定すれば、条件つきの「利他行動」およびそれを促すような心性が自然淘汰で進化しうることを、ごく簡単なモデルによって示してみたい。このポイントが理解できれば、あとの(3)と(4)の批判は比較的簡単に克服することができる。
9 ダニ取り鳥の行動戦略
わたしの本でも使った、ドーキンスから借用した「ダニ取り鳥」の例をもう少し改変して、本質的なポイントをできるだけ簡単な数学の枠内で示してみよう。なお、以下で「利己的」あるいは「利他的」という言葉をカッコつきで使うのは、ドーキンスと同様、通常の倫理的含みをもつ人間的な意味でなく、また意図的になされる行動に適用されるのでもない比喩的な意味に限定するためである。鳥の個体(あるいはそれがもつ遺伝子)が、あたかも自分の子孫(遺伝子の複製)をできるだけ増やそうとするかのように、生物学者から見て記述できる傾向を「利己的」、ほかの個体の子孫や遺伝子の生き残りや増殖に貢献するような傾向を「利他的」と記述する。
ある種の鳥にダニが寄生し、危険な病原体を伝染させて鳥の生存の可能性さえ脅かすので、このダニがついたら早く取り除く必要があるとしよう。ところが、身体の場所によっては鳥が自分で取りにくい所がある。そこで、仲間の鳥につついてもらい、相手にダニがついたときには自分がつついて取ってやれば、両者ともにわずかの奉仕で大きな見返りが得られるとしよう(鳥がそのことを認識する必要はない)。つまり、相互に「利他的」な行為をすれば、そうでない場合に比べて両者の生存率は大幅に改善される。しかし、そのような行為の傾向をもたらす遺伝子にも、鳥の個体にも、人間のような予見能力はないし、自然淘汰は繁殖率の差を通じて盲目的に働くにすぎない。では、このような「利他的」な行動は進化(自然淘汰によって種に定着)しうるのだろうか。
話を簡単にするために、この鳥のダニ取り行動には次の二つのパターン(ゲーム理論では「行動戦略」という)があるとしよう。
戦略A 「相手かまわずいつもダニを取ってやる」――これは「利他的 altruistic」戦略である。
戦略E 「自分は相手にダニを取ってもらうが、相手のダニは取ってやらない」――これは「利己的 egoistic」戦略である。
二つの戦略が生存闘争の場で競争したときにはどうなるだろうか。これを見るためには、ゲームの利得表を決めておかなければならない。この場合「利得」とは、繁殖率を増やすのにどれだけ貢献するかということ(生物学的利益)であり、次の表のように適当な数値(要するに、有利さあるいは不利さの目安だが、後でグラフ化するときに便利でかつ説明の要点を損なわないように、数値を選んである)を割り当てて示すことができる。
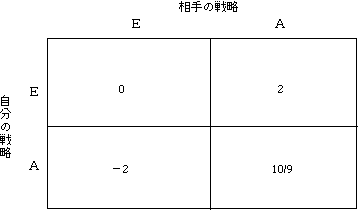
表1 「利己主義」対「利他主義」の利得表
この利得表によれば、Eの戦略はEと対戦したときは得失0、Aと対戦したときは得点2であるから、いずれの場合もAの得点より高く、Aの戦略に対して一方的に有利である。これを自然淘汰の文脈の中で解釈すると、この鳥の集団中で当初のEとAの割合はどうであれ(Eの割合は0ではないとして)、早晩Aの戦略をとる鳥は絶滅して、Eばかりになるということである。また、Eの戦略が大勢を占める集団のなかにAの戦略は決して侵入できない(入ってもすぐ絶滅する)。このとき、専門用語では、Eは「進化的に安定な戦略(Evolutionarily Stable Strategy, ESS)」と呼ばれる。
10 社会性と知性を仮定すれば
しかし、この鳥が社会的であり、仲間の鳥と生涯に何度も出会って相互交渉があるという前提と、ある程度知性があって、個体を識別し、相手の反応を記憶できるという前提をおけば、もっと「賢い」次のようなCの戦略も可能になる。
戦略C 「(a) 初対面の相手にはダニ取りをしてやり、Aと同じにふるまう。しかし、 (b) かつてダニ取りをしてやった相手が自分にお返しをしなかった場合には、以後ダニ取りはしてやらない」――これは「条件つき利他主義 conditional altruism」の戦略である。
もちろん、この戦略に対しても利得表を与えなければならないが、(a) (b) 二つのケースがあるので少し複雑になり、EとCの戦略をそれぞれとる個体が初対面でどれほどの頻度で出会うかの確率を与えておかなければならない。ここでは、単純化のため、この確率は1/2 であるとし、次の利得表を示しておく。
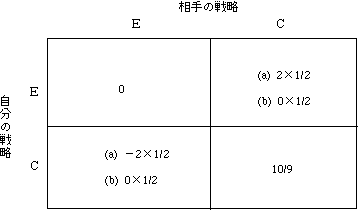
表2 「利己主義」対「条件つき利他主義」の利得表
このように、ダーウィンの道徳起源論をヒントにして少し条件を加えただけで、ゲームの様相はガラリと変わる。(a) (b) 二つのケースが五分五分で生じうる場合、得点は表の二つの数値の和になることに注意されたい。そこで、EはCに対しては一方的に有利とはならない(ついでに、この鳥に感情がありうるとすれば、Eに「裏切られた」Cはどういう感情をもつだろうか。また、次に同じ相手に出会ったときにはどう感じるだろうか。鳥では想像はむずかしい。しかしチンパンジーなら?)。EはEに出会った場合には(平均して)Cより大きく有利である(0対−1)が、Cに出会った場合には(平均して)わずかだがCより不利(1対 10/9)となる。このわずかの差が長期にはどうなるだろうか。
実は、ドーキンスはもう少し複雑な条件の利得表をもとに、三つの戦略が入り交じった大きな集団を想定してコンピュータ・シミュレーションを行なって長期にわたる自然淘汰の結果を出している(図1参照)。それによると、圧倒的多数のA、あまり少なすぎてすぐ絶滅しない程度のCとそれとほぼ同数のEという初期条件でシミュレーションを行なえば、まずAが激減してEが急増する。ところが、最初のうちは減少傾向を示したCは、やがてAが絶滅した後、Eとの競争を制して大多数となる。ただし、Eは少数となっても生き残り、Cと一定の比率をもって共存する(以上、Dawkins 1989, 邦訳296-298)。なぜこのようなことが起きるのだろうか。それは、わたしが改変した前述の簡略なモデルではっきりと理解することができる。
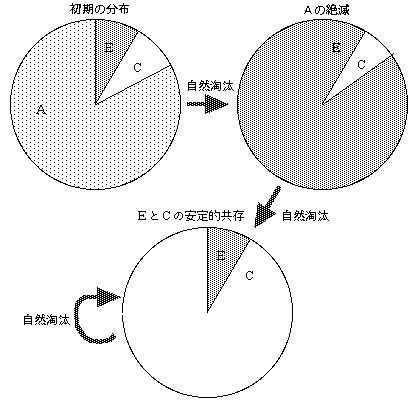
図1 ドーキンスのシミュレーション
比較のため、前述二つの利得表とドーキンスと同じ初期条件から出発したとしよう。Aの絶滅は簡単に理解できる。A対Cの利得表は表1と表2から簡単に得られる――実は、A対Aとまったく同じである。したがって、AとCが対戦する限りはどちらかが有利ということはない。しかし、AはEに対して一方的に不利であるから、世代を重ねるごとに自然淘汰によって数を減らし、やがて絶滅する。ところが、CはEに対して一方的に不利ではない(別の言葉でいえば、どちらも ESS ではない。内井1996についてESS の概念を理解しないまま書かれた書評に対し、わたしは内井1998b で注意しておいた)。このとき、長期にはどういうことになるかといえば、二つの戦略の平均利得が等しくなるところで平衡状態に達するのである。
少し説明を補おう。どちらの戦略も、もちろん当初の(シミュレーションをはじめる時点での)繁殖率を与えられている。しかし、長い間には、それぞれの戦略によって得点を積み重ねていくので、長期にわたる繁殖率を決定するのは、結局平均利得である。両者の相対的な有利さ・不利さはこの長期の平均利得で決まるので、それが等しくなったところが、両者が共存できる平衡点にほかならない。ところが、この平衡点は、集団のなかでのCとEとの比率(個体数の割合)にも依存する。この点は、中学校程度の数学で簡単にわかる。
いま、利得表はそのままにして、集団中でEが占める割合をp、Cが占める割合を(1−p)としてみよう。この割合pは、二つの個体がランダムに出会うものとすれば、戦略Eをとる個体が長期にわたってCと出会う確率となる。そこで、Eの長期にわたる平均利得はこの確率pと、表2によって決まり
p・0 + (1−p)・(1/2)・2 = (1−p)
であるのに対し、Cのそれは
p・(1/2)・(−2) + (1−p)・(10/9) = (10−19p)/9
である。二つの値を一致させるようなpの値が安定した比率である。計算によってこの値を求めると、
p = 1/10
となる。すなわち、EとCの割合が1対9のとき、両者は安定して共存する(図2のグラフを参照)。
もっとも、ここまでの説明にはまだ伏せられた前提がある。CがEと初対面で出会う (a) の確率をわれわれは 1/2 としたが、これは、本当はEの割合pに依存するはずである。そして、この依存関係は、二次式あるいは三次式のような複雑な関数になるかもしれない(ドーキンスがコンピュータ・シミュレーションに訴えたのはおそらくそのためである)。しかし、この点も簡略な一次式を使って考慮に入れ直すことができる。いま、CがEと初対面で出会う確率をqとし、新しいパラメーターとして導入してみよう。qをpの複雑な関数にして動かしてみるより、むしろqを独立に動かしてみて、その結果pがどのように変わるかを見たほうがわかりやすい(本当は依存関係は逆だが、数学的にはたいして変わりはない)。この操作なら、一次関数だけで行なうことができる。そうすると、ゲームの利得表は次のように変わる。
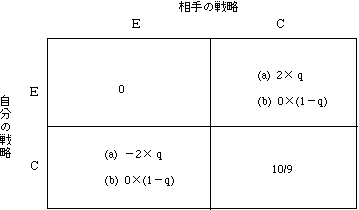
表3 「利己主義」対「条件つき利他主義」、一般化
この利得表でqを0から1の間で動かせたとき、安定的な共存に達するpの値は、次の図のグラフからわかる。要するにE、Cそれぞれの長期の平均利得はqを変数とする一次式で表されるので、qの値を一つ固定したとき、二つの一次式が交わる点の横座標が安定的なEの割合、すなわちpの値となる。グラフでは、qが 0.10、0.25、0.50 と三つのケースを示しているが、最後が表2の利得表に一致し、このときpの値は 0.10 である。
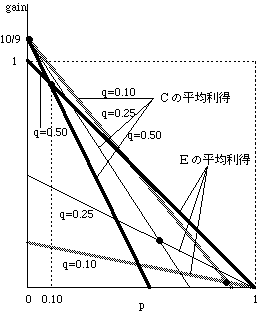
図2 qと安定的なpの相関
以上のように、社会性と知性とを仮定すれば、少なくとも行動戦略としては「利他行動」(つまり、相手の生物学的利益を促進するが、意図や感情を必ずしも伴わない行動)が自然淘汰によって生き残り、大勢を占めることが可能である。ダーウィンが仮想の心理的プロセスのように描いた過程は、自然淘汰の数学によって裏づけられるのである。そして、人間の道徳を「利他行動」の延長線上で考えようとするのは妥当な試みであるように思われる。人間の利他行動(これはカッコなし)の目的が生物学的利益のみに関わるのでないことは確かだが、広範な一致または重複が見られることもまた確かである。例えば、「殺すな」「盗むな」「姦淫するな」「約束を守れ」等の代表的な道徳的義務の遵守や、協力行動から人々がどれほどの利益を得ているか考えてみれば、これは明らかであろう。
もちろん、ここでのモデルと違って、社会的動物とくに人間の(遺伝的な基盤をもつ)行動戦略については「利得表」(生物学的利益で表されることに注意)が不明である。しかし、この点は、モデルや仮説演繹法のたぐいの推論が不可欠な自然科学の常套手段に訴えて切り抜けることができる。すなわち、現実の現象を最もうまく説明できそうなモデルや仮説が最も有望なものとして選び出され、少なくとも暫定的に受け入れられるのだと考えればよい。経験的知識には、これ以上の正当化は望めない。
11 行動生態学からの支持
最後に残る問題は、行動戦略に伴う、あるいはそれを心理的に裏づける感情や動機づけの問題である。ダーウィンは行動戦略ではなくむしろこちらの言葉づかいで問題を扱っていたことを想起しよう。この問題についても、前節の議論に照らして考えれば、ダーウィンの路線は強化されこそすれ、くつがえされることはない。感情や心理の問題は、いまだに思弁と縁をきることはできない。しかし、人間のような高度な知性をもつ存在において、行為決定に際しては感情が大きな役割を果たすことは、古今の哲学者が強調してきた。とくに、利己的な(これはカッコなし)行為を押さえるのに有効なのは道徳感情である(もう一つは、ホッブズが指摘するように、恐怖であろう)。人類に、内容のヴァリエーションはあっても道徳があまねく行き渡っていることを考えると、道徳感情と利他行動とのつながりは否定すべくもない。
しかも、すでに触れたように、動物行動学あるいは生態学の最近の研究も、ダーウィンの路線をさらに具体的に支持しているように思われる。オランダ出身のすぐれた霊長類学者ドゥ・ヴァールの最新の著書(de Waal 1996、邦訳1998)は、道徳の素材となるような能力や心性がほかの動物にも見られること、あるいは霊長類には萌芽的な道徳さえ見られることを豊富な実例で裏づけている。これは、まさにダーウィンの路線の継承と発展にほかならない(その手短な紹介は、内井1997を参照)。わたしに言わせれば、道徳能力の記述における還元主義はこのように強化されているのである。
念のために、ドゥ・ヴァールが道徳性の基盤となる性質として枚挙するものを紹介してみよう。彼によれば、「人間の道徳性は、他の種にも見られる次のような傾向性や能力を抜きにしては考えることがむずかしい」(de Waal 1996, 211)。
共感と関連した特徴
愛着、援助、感情の伝染
学習によって、能力に障害がある者あるいは傷ついた者に対して順応し特別な取り扱いをすること
心の中で他者と立場を入れ替える能力、認知的感情移入
規範と関連した特徴
指令的な社会的規則
規則の内面化と罰の予見
相互性
与えること、取り引きすること、復讐すること
相互的な規則を破った者に対する「道徳的」な攻撃
協調
仲直り、および衝突の回避
共同体への配慮、よい関係の維持
利害の対立を交渉によって調整する
念のために付け加えておくが、ドゥ・ヴァールは以上のリストを人間の観察から引き出したのではない。彼が観察の対象としたのは主として霊長類、チンパンジー、ボノボ(ピグミー・チンパンジー)、ヒヒ、アカゲザル、ベニガオザル、オマキザル(俗に南米のチンパンジーといわれることもある)などである。もちろん、ドゥ・ヴァールによるこういった記述は「擬人化」がすぎるという批判は可能かもしれない。しかし、チンパンジーなどの観察にある程度通じた人に尋ねてみれば、返ってくる答えは一貫して、「彼らはほとんど人間と同じですよ!」というものである。しかも、「擬人化」した記述を使おうが、もっと無味乾燥な「行動主義的」記述を使おうが、見えてくるのは、(ときにはミッシング・リンクを挟んで)わずかずつの違いでつながる類似性の連続的なスペクトラムがあり、どこかで鋭く切り離すことはむずかしいという事実である(内井1998a、10節も参照 )。
12 進化心理学
さて、8節の終わりで予告したように、シュルマンの(3)「非道徳的なものから道徳性はうまれない」、(4)「ダーウィンは仮想的な心理プロセスのうちに道徳的存在の経験を読み込んでいる」、という論点にはもうほとんど関わり合う必要はないと思う。一定の非道徳的な能力や傾向性がないと道徳は不可能であるだけでなく、道徳とはそれらの能力や傾向性が束になって作用する一群の現象に対する呼び名である。これがダーウィンが伝えたかったメッセージであり、わたしはそれを「還元主義」と名づけて支持したい。また、前節までで、現代のいくつかの成果を借用して再構成したかぎりでは、ダーウィンの議論に(4)の批判はまったく当たらないと思う。しかし、わたしが行なって見せたような分析の必要性を指摘しているという点では、シュルマンの批判には確かに価値があったのである。
本節の残りでは、ダーウィンの路線の延長線上に明瞭に位置づけられる現代のもう一つの新しい流れを紹介し、「道徳起源論」が単に19世紀の古くさい研究分野ではないことを示しておきたい。本節タイトルの「進化心理学」という言葉は、たいていの哲学者には耳慣れないはずである。わたしも1996年の秋までは知らなかった。この分野の研究と啓蒙活動を精力的に行なっている長谷川寿一氏は、進化心理学とは「人間の心的活動の遺伝的基盤が進化の産物であるという事実に立脚する心理学」であるというコスミデスとトゥービーの定義を紹介している(長谷川1997)。この観点からどういう展望が開けるかというと、現代人の心にも過去の適応の跡(適応バイアス)が残っているはずであり、適切な調査によって人類に普遍的に備わるとみられる心的特性が見つかれば、それは適応バイアスの有力な候補と見なせるということである。ただし、もちろん、有力な候補が見つかってもそれが実際に適応バイアスであることの立証にはまだ長い道のりがある。「普遍的に備わる」ことが、人類の遺伝的な基盤からくるのか、それとも文化あるいは学習などの後天的要因に基づくのかは、直ちには決められないからである。
そのような候補として現在最も有力視されているのは、コスミデスとトゥービーが「四枚カード問題」の新解釈から明らかにした、「社会的なルール破り」、「タダ乗り」や「抜け駆け」のたぐいの「倫理的不正」に対してとくに鋭敏に反応するという、人間の心性である。「四枚カード問題」とは、わたしも長谷川氏と知り合いになるまで知らなかったのだが、要するにわたしの専門分野の一つでもある論理的推論に関わる問題であり、「PならばQである」という条件文の真偽を確認するにはどうすればよいかを被験者に答えさせる心理学実験の課題である。例えば、表にアルファベット、裏に数字が書かれた次のようなカードが4枚あるとしよう。被験者に求められるのは、「表がAなら裏は3である」という条件文の真偽を確認するには、どのカードをめくって反対側を見なければならないか、という課題に答えることである。
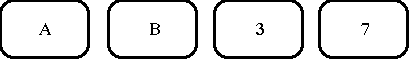
図3 抽象的課題のカード
わたしは論理学教師として20年以上の経験があるが、この課題が(一般の人々にとって)むずかしいことは一見してわかる。わたしも一般読者向けの新書(内井1987、32以下)で解説したとおり、論理学の第一の関門は「ならば」のマスターである。「PならばQ」を反証(偽に)する条件は「PであってQでない」だから、まず(1)表に「P」があればめくってみなければならず、(2)裏に「Qでない」があれば(「PならばQ」は対偶の「QでないならPでない」と等値である)やはりめくってみなければならない。図の例は比較的ストレートでやさしいほうであるが、このような抽象的な課題の場合、正解率は大学生で平均十数パーセントだそうである。図の例では、正解は「一枚目と四枚目をめくる」となる。
しかし、論理的構造は同じままにして、カードに書かれた内容(つまり条件文の内容)を変えてやると、正解率が急上昇することが知られている。これがこのテストの興味深い点である。例えば、「酒を飲んでいるならば二十歳以上である」という、われわれになじみの深い具体的内容の条件文をもとにして、次のようなカードでテストをしたとしよう。
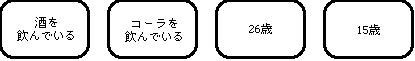
図4 具体的課題のカード
そうすると、正解率は70パーセント近くにまで上がるのである。しかし、この図4と先の図3とは、論理的構造はまったく同じで、正解はやはり「一枚目と四枚目をめくる」となる。
そこで、抽象志向、普遍志向のわたしのような論理学者なら、「人間は理性的動物だという定義はあてにならず、論理的な人間は少ない。とくになじみが少ない課題については人はよく間違う」(内井1987、39参照)という常識的な一般化で満足して、ひそかに優越感をもつかもしれない。ところが、進化論の視点からユニークな発想をおこなったコスミデスとトゥービー (1992) は、論理的に構造は同じでも、話題によって(過去の適応の結果である)適応バイアスが違うからこのような差が生まれるのだという新しい解釈を打ち出した。なじみが少ない内容でも、社会的な契約や規範の文脈に乗せると正解率が上がるというのが決め手である。この発想は、まさにダーウィンの道徳起源論の延長線上に乗る。社会的でかつ高い知性をもつ動物である人間(の祖先)にとって、相互的利他行動は高い適応的価値(生物学的利益)をもっていたはずであり、行動だけでなく、行動を支える諸種の知覚能力や感情も発達させたはずである。そして、相互的利他行動の存立基盤を危うくするような「ルール破り」「抜け駆け」「タダ乗り」の兆候に対してはきわめて鋭敏な心性を獲得したはずである。「ならば」の抽象的な論理には鈍感でも、社会的規範、契約、(条件つき)利他行動に関わる文脈や話題については「違反」や「不正」に対して敏感であるという心性は、自然淘汰説の観点からは当然と言える。一般性には欠けても、差し迫った必要性にはその都度対応して生き延びてきたのが「適者」の実情だからである(Cosmides&Tooby 1992, 長谷川1996、15-18。Dennett 1995, 489)。
もちろん、このような発想だけでなく、それを検証する手続きを遂行し、進化心理学の手法がもたらす理論的な利点の擁護をもコスミデスらは積極的に試みている。彼らの検証結果は、日本でも長谷川寿一・真理子夫妻のグループによって追試され、確認されているようである(詳しくは、長谷川1996、1997参照)。すでに指摘したように、コスミデスらの成果は有望であるとはいえ、人間の心性の遺伝的基盤を明らかにしたと確かに結論できるわけではない。しかし、ダーウィニアンならではの、新しい展望を開いたことは高く評価できると思う。そして、この方向の研究が、人間の倫理を考える上できわめて重要な事実にかかわることは否定できないのである。このように、ダーウィンの道徳起源論の射程は、現在でもまだ探求し尽くされてはいない。(第一部了)
文献
Barkow, J.H., Cosmides, L., and Tooby, J., eds. (1992) The Adapted Mind, Oxford University Press, 1992.
Cosmides, L. and Tooby, J. (1992) "Cognitive Adaptations for Social Exchange", in Barkow et al. (1992).
Darwin, Charles. (1871) The Descent of Man, Murray, 1871. 2nd ed, 1874.
Dawkins, R. (1989) The Selfish Gene, Oxford University Press, 1989.
Dennett, D. (1991) Consciousness Explained, Little, Brown and Co., 1991.
------. (1995) Darwin's Dangerous Idea, Simon and Shuster, 1995.
------. (1996) Kinds of Minds, Basic Books, 1996.
De Waal, F. (1996) Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, 1996.
Hamilton, W.D. (1964) "The Genetical Theory of Social Behavior I, II", Journal of Theoretical Biology 7, 1964.
Holland, John. (1975) Adaptation in Natural and Artificial Systems, The University of Michigan Press, 1975.
Ruse, Michael. (1986) Taking Darwin Seriously, Cambridge university Press, 1986.
------. (1993) "The New Evolutionary Ethics", in Evolutionary Ethics, ed. by M.H.Nitecki & D.V.Nitecki, State University of New York Press, 1993.
------. (1995) "Evolution and Ethics: The Sociobiological Approach", in Ethical Theory: Classical and Contemporary Readings, ed. by L.Pojam, Wadsworth Press, 2nd.ed., 1995.
Schurman, Jacob Gould. (1887) The Ethical Import of Darwinism, Charles Scribner's Sons, 1887. 3rd ed, 1903.
Sidgwick, Henry. (1902) Lectures on the Ethics of T.H.Green, Mr. Herbert Spencer, and J. Martineau, Macmillan, 1902 (edited by E.E.Constance Jones).
Spencer, Herbert. (1879) The Data of Ethics, Crowell and Co., 1879.
Trivers, R. (1971) "The Evolution of Reciprocal Altruism", Quarterly Review of Biology 4, 1971.
Uchii, Soshichi. (1997a) "Comments on Professor Ruse's View", http://www.bun.kyoto- u.ac.jp/~phisci/Newsletters/newslet_19.html, 1997.
Uchii, Soshichi. (1997b) "Darwin on the Evolution of Morality", http://www.bun.kyoto- u.ac.jp/~suchii/D.onM.html, 1997.
Westermarck, Edward. (1906-08) The Origin and Development of the Moral Ideas, 2 vols. Macmillan, 1st ed., 1906, 1908; 2nd ed., 1912, 1917.
ボウラー、P. J. (1992)『ダーウィン革命の神話』(松永俊男訳)、朝日新聞社、1992。
デネット、D. (1997)『心はどこにあるのか』(土屋俊訳)、草思社、1997。
デネット、D. (1998)『解明される意識』(山口泰司訳)、青土社、1998。
ドーキンス、R.(1991)『利己的な遺伝子』(日高敏隆他訳)、紀伊國屋書店、1991。
ドゥ・ヴァ−ル、F. (1998)『利己的なサル、他人を思いやるサル』(西田利貞・藤井 留美訳)、草思社、1998。[De Waal 1996 の訳。注と文献表その他が省かれて原著 のイメージを大いに損なったのが残念。]
トリヴァース、R.(1991)『生物の社会進化』(中嶋康裕他訳)、産業図書、1991。
長谷川寿一(1996)『児童心理学の進歩』1996年版、第1章、金子書房。
長谷川寿一(1997)「心の進化――人間性のダーウィン的理解」『科学』67-4、1997。
奥野満里子(1997-98)「パーフィットの功利主義擁護論」、『哲学研究』564号、565号、 1997、1998。
奥野満里子(1998)『シジウィックと現代功利主義』、京都大学大学院文学研究科、博士 論文、1998。
立花隆、利根川進(1990)『精神と物質』、文芸春秋社、1990。
内井惣七(1987)『うそとパラドックス』、講談社現代新書、1987。
内井惣七(1988)『自由の法則・利害の論理』、ミネルヴァ書房、1988。
内井惣七(1989)『真理・証明・計算』、ミネルヴァ書房、1989。
内井惣七(1992)「ダーウィンの自然選択説に関する二つの疑惑」、『実践哲学研究』15、 1992。
内井惣七(1993)「形質分岐の原理――ダーウィンとウォレス」、『京都大学文学部研究 紀要』32、1993。
内井惣七(1996)『進化論と倫理』、世界思想社、1996。
内井惣七(1997)「道徳起源論」、『科学』67-4、1997。
内井惣七(1998a)「ダーウィニズムと倫理」、『生物科学』50-2、1998。
内井惣七(1998b)「道徳は進化的に安定な戦略か?――大庭健氏の誤読」、『科学哲学』 31-1、1998。
ワールドロップ、M. M.(1996)『複雑系』(田中三彦・遠山峻征訳)、新潮社、1996。
To Part 2///BACK TO UCHII INDEX
November 12, 1998; last modified Nov. 13, 2002. (c) Soshichi Uchii