|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ●室生村の歴史・地勢 <室生村の源流・その歴史的風土>  村のどこにいてもふと立ちどまって佇んでいるだけで、ゆったりとした時の流れに裏打ちされた落ち着いた風情が、色濃く感じられる室生村の風土。
村のどこにいてもふと立ちどまって佇んでいるだけで、ゆったりとした時の流れに裏打ちされた落ち着いた風情が、色濃く感じられる室生村の風土。ここでは、時代の移り変わりを超えてきた歴史の証人と、それぞれの集落で代々受け伝えられてきた文化が、今もここかしこに息づいています。 室生村は山間部にありながら、人々が暮らし始めたのは大変に古く、北中部の各地で縄文後期の土器や石器などが出土していることなどから、すでに三千年から四千年前には人が住み着き、狩猟採集生活をしていたようです。 また、これらの遺跡のほとんどが室生川流域を含む多くの地区でも中期以降の弥生式土器が見つかっており、二世紀ごろには農耕生活も始まったと思われますが、立地条件などからどの集落も小規模で、大集落には発達しませんでした。さらに、古墳時代にも有力な氏族は生まれなかったようで、大野・向淵・無山などに見られる古墳は、六世紀から七世紀にかけての横穴式円墳が多く、いずれも直径10メートル前後の小規模なものです。 しかし、大和政権が国の基礎を固めつつあった飛鳥時代に入ると、壬申の乱(672)の折に大海人皇子(後の天武天皇)の軍が大野を通過したと記されていることなどから、早くも村の北部・中部・南部を東西に横切る三本の街道が通り、大和平野と伊勢・東海地方を結ぶ交通の要所となっていたと思われます。  奈良時代末から平安時代にかけては、祈雨信仰の地として室生の竜穴が朝廷より厚い信仰を受け続け、そして八世紀後半には、竜穴との関係も深い室生寺が興福寺大僧都の賢憬によって創建されるなど、この頃にはすでに、今日まで育まれてきた室生文化の源流が形作られたと考えることもできます。
奈良時代末から平安時代にかけては、祈雨信仰の地として室生の竜穴が朝廷より厚い信仰を受け続け、そして八世紀後半には、竜穴との関係も深い室生寺が興福寺大僧都の賢憬によって創建されるなど、この頃にはすでに、今日まで育まれてきた室生文化の源流が形作られたと考えることもできます。一方、荘園経営が盛んであった平安時代には、伊賀に近い笠間荘が東大寺領であったのを除き、村内のほとんどは興福寺の荘園となり、大野荘・牟山荘・向淵荘などが成立していました。  鎌倉時代に入っても、大和では興福寺の勢力があまりにも強大なために、地頭が置かれることもほとんどなく、宇陀地方の村々は引き続き興福寺の支配下にありましたが、南北朝の争乱が始まると、このころ勢力を伸ばしてきた土豪の多くが南朝方につくなど、興福寺の勢力にも衰えが見えはじめました。
鎌倉時代に入っても、大和では興福寺の勢力があまりにも強大なために、地頭が置かれることもほとんどなく、宇陀地方の村々は引き続き興福寺の支配下にありましたが、南北朝の争乱が始まると、このころ勢力を伸ばしてきた土豪の多くが南朝方につくなど、興福寺の勢力にも衰えが見えはじめました。 室町幕府が成立し争乱が始まると、すでに往時の支配力はなく、土豪たちはいくるかの党に分かれ同盟が結ばれました。その一つ山内党には、村内北部の牟山・多田・上笠間・下笠間などの諸氏が加わり、その団結心を深めていたのが、応永16年(1409)から150年余りの間の連歌会の記録などが現在も残る染田天神講でした。
室町幕府が成立し争乱が始まると、すでに往時の支配力はなく、土豪たちはいくるかの党に分かれ同盟が結ばれました。その一つ山内党には、村内北部の牟山・多田・上笠間・下笠間などの諸氏が加わり、その団結心を深めていたのが、応永16年(1409)から150年余りの間の連歌会の記録などが現在も残る染田天神講でした。大和永享の乱(1429)が起こると、大和の豪族たちは越智・筒井の両派に分かれて抗争を始め、応仁の乱(1467)が大和に波及すると、戦乱はますます激化し、山内でも戦いが絶えることなく、織田信長の支援を受けた筒井順慶が大和を統一するまで争乱が繰り返されました。  江戸時代の初期には、室生村は幕領・旗本領・大名領などに複雑に分割統治されましたが、一方では、わずかな平地や緩斜面を利用した田地の造成が行われ、多くの技村が生まれました。
江戸時代の初期には、室生村は幕領・旗本領・大名領などに複雑に分割統治されましたが、一方では、わずかな平地や緩斜面を利用した田地の造成が行われ、多くの技村が生まれました。また、古代から重要な交通路であった三本の街道は、伊勢参りが盛んになるにつれてますます賑わい、江戸時代には、三本松をはじめ街道筋の集落は宿場町として大いに栄えはじめました。 複雑な支配関係に分かれていた村々も、元禄以後には旧山辺郡のほとんどが藤堂和泉守領となり、明治に入ると幾度か統合され、明治22年の町村制施行によって山辺郡東里村と宇陀郡の三本松村・室生村の三村にまとまり、さらに昭和30年には三村が合併して新しい室生村が生まれ、新たな室生文化が育まれつつあります。 |
|
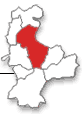 |
|||||