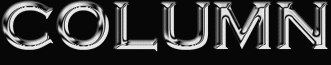
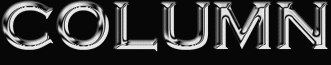
第六夜 盆中駒揃いました。
以前に競馬は丁半と同じカテゴリーの博打であると書いたが、それだけではあまりに乱暴なので、少し掘り下げて考えてみたい。便宜上分けて書くと
Aグループ 丁半、本引き、ルーレットなど
Bグループ カブ、ポーカー、麻雀など
大きな違いは、Aはあらかじめあるものの中から賭けの対象を選ぶのに対し、Bは賭けの対象を作らなければならない。というか競技者となって賞金をとるのと同じだ。ただ普通の競技者は負けてもゼロだが、賭け事はマイナスになるだけである。
わかりやすくいえば、もちろん競馬は前者だが、後者は競馬で言うと騎手になっているようなものである。
Bの典型はポーカーだ。極端に言えば手なんかどうでもいいのである。たとえブタであっても相手に大物手と思わせておろせば勝つことのできるゲームなのである。つまり、自分が作る駆け引きやツキで勝つ、要は自分が走っているのと同じである。
競馬にはいろんな要素が絡みついていて、博打としての本質が見えにくくなっていると思う。
そこで、丁半、本引きと比較してバラバラにしてみようと思う。
さて、丁半博打であるが、基本的なルールはこうである。
2つのサイコロの合計の目が奇数か偶数かに賭けるというだけなのだが、ご存知のように丁目が若干有利になっている。ということは、数学的には丁目にかければ必ず勝つのだが、実際にはそうはいかない。JRAとおなじで控除があるのだ。
しくみとしてはJRAとまったく一緒で、親対子という勝負ではなく、賭けている者同士でとりあうのである。おおむね丁半張方が同数にならなければ壷はあかないので、オッズはいつも2倍ということである。
勝金からは5分の寺銭が引かれる。つまり5%の控除率である。むかしはこの寺銭を1割取った賭場は悪質だということでピンハネといわれたそうだ。25%がいかに悪質かというところである。ちなみに寺銭とは江戸時代は寺社は町方の管轄外だったので、お寺で博打が行われていて、その場所代のなごりだそうだ。
以上のことからたとえ丁目が確率的に少し有利でも、控除が5%あるということは勝てないということである。
仮に丁半それぞれ1/2の確率だとしたら、延々とやればひきわけである。しかし寺銭の分があるので統計的には長くやればやるほど負けるのだ。控除の分だけ胴元が勝つ仕組みだ。というか、正確には胴元は勝負していないので勝つという表現はおかしい。いわば手数料収入である。
張り方は常に5%の負を背負うので、1/2の確率で2倍の固定オッズではどちらに回ってもまけることが最初からきまっているということだ。ではどうしたら勝てるのか。
つまり、資金均等買いでは負けるということなのである。勝てると思った勝負に賭け金をアップさせなければ永遠に勝てない博打なのである。
これが丁半博打の基本のシステムなのだ。博打全般にいえることは、普通にやっていたら数学的に必ず負けるようになっているということである。でないとこんなに長く続かないし、逆にビジネスとして成り立っているギャンブル以外は技術を上げれば勝てるということになる。
つまり、個人レベルの技術が結果にあまり作用しないギャンブルは、しくみの隙間のどこかを突いてひねらなければ勝てないというわけだ。
では競馬のしくみはどうなっているのだろうか。
| 状 態 | A | B | C |
| レース | 情報の流れ | 取捨選択 | 決 定 |
| 壷の中サイコロ | 出目の流れ | 1/2 | 決 定 |
上の分け方で一番異論のあるのは、まだ始まらないレースと壷に入ったサイコロを同列にあつかえるかどうかということだと思う。
競馬の場合、もし今終わったばかりのレースを、同条件でもう一度走らせることができたら、はたして同じ結果になるだろうか?結論からいうと、わたしの考えは、ならない。である。これが前提条件になる。
もちろん、歴然とした力差のあるレースで10回やって8回同じ結果になっても、必ず同じ結果になるというのとでは全然違うと思う。なぜなら、数学のように正解が必ず1つというような問題なら、それに向かっていく道は1本である。
競馬の場合、レース結果を見てだした正解への道はなるほどと思うが、それはその結果に用意された道なのである。
競馬を推理ゲームだと表現する人がいるが、それは間違いである。用意された1つの解答に向かっていくような錯覚を覚えるだけなのである。
じつは、ここのところをわかりやすくするために、サイコロと比較しているのである。
壷に入ったサイコロの目が奇数か偶数か?中は見えないがどちらかの目が出ているのは確かである。つまり、壷の中には正解が存在しているのである。しかし、それを正確に当てる理論もなければ、計算式もないのだ。
シュレーディンガーがもし丁半博打を知っていたら、波動関数はここから生まれたかもしれないくらい難解な問題になる。
サイコロの目を当てるのに、指数もなければ、調教もない。では一体どうやって当てるのだ?
勘である。目のながれ、場を読んで賭けていくしかないのである。体中がセンサーとなって、過去の経験や記憶を組み合わせて決断していくしかないのである。
競馬には、予想するための諸々があるために、あたかも決められた正解があるように錯覚しているのではないだろうか。
基本的にあるものを選ぶことで賭ける博打に正解はないし、王道もないと思う。正確にいうと、用意されたもののうちのどれかということまでしか突き詰められない。
手作り、役作りをする博打はまたちょっと違うのでここでは含めないが、ゲートが開くのと壷があくのとは本質的になんら変わりないということなのだ。
木下師匠がよくいうように、「自分の予想結果はあっているが、たまたま他の馬が今回は飛び込んできたと思う」そういう事だと思うのである。次もし同じレースをやれば、自分の買い目がきているかもしれないのだ。
これは負け惜しみのタラレバとは違う。出た結果から、抜けた目を買っていたらなぁと思うのとは天地の開きがあるだ。
また、ここではずれたことで弱気になるというのは、自分が間違ったために負けた結果だと受け取るからである。その弱気が次の買い目や賭け金に作用していくのである。
サイコロで出た目が違っても自分の積み上げた理論が間違ったとは思わないだろう。
何度も言うようだが、最終的にはデジタルのアナログ補正ではなく、アナログをデジタルで補完していく形なのではないかと思う。木下師匠の凄いところは、もちろん独自の指数等凄いところはいっぱいあるのだが、「勘や」と言い切れるところである。
木下師匠のレース選択の仕方、レースの見方、休み明けの取捨て、馬場の見方等、目からウロコが落ちるように色々おしえてもらうのだが、それをどの場面でどう組み合わせるかということになると、もう説明は不可能だろう。
だから、師匠が「勘なんですわ」と言い切れるところが凄いのである。
当たりなら、もっともらしくこじつけた結果論でもなんでも言えるが、そうじゃないところが本物なのである。
ツメのアカは飲みたくないが、見習いたいところはいっぱいある。
そして、見習いたくないところもそれ以上にある。