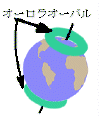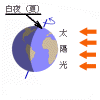オーロラ紀行
in Yellowknife
最終更新日:2003.3.1
この地球上には、絶え間なく不思議な自然現象が繰り広げられている。私は残された人生でそれらの一つでも多くを訪ねて見たいと思っている。その一つが極地にのみ発生するオーロラ。早々この目で見る事とした。その結果の一部を此処にご案内をしましょう。
目 次
A:オーロラ発生原理
B:オーロラ発生要素
C:オーロラ観測の条件
D:オーロラ観測時の服装
E:オーロラ撮影に付いて
F:イエローナイフ・オーロラ紀行
A:オーロラ発生原理 (専門家でもありませんので詳しくは下記のサイトなどを参照下さい)
太陽風に乗ってやって来る荷電粒子が地磁気と作用して極地周辺のオーロラオーバル(地上100km以上)で上層大気
と衝突し、そのエネルギーが光として放出されるのがオーロラ。現在も盛んに研究が進められているがまだまだ謎の部
分が多いらしい。北極圏では、「ノーザン・ライト(正式名称はオーロラ・ボリアリス)」、南極圏では「サザン・
ライト(正式名称はオーロラ・オーストラリス)」と呼ばれている。
多くの学者の観測によって、オーロラの光は線又は帯スペクトルであり太陽光の様な七色になる連続スペクトルては無
い事が確認されている。線スペクトルは原子が放出する光で、帯スペクトルは分子が放出する光である事が判ってい
る。
すなわちオーロラは原子や分子が放出する発光現象で七色にはなりません。更にオーロラは実験室での真空放電で光を
放出して安定な状態に戻るまでの時間の短い現象=蛍光とは全く異なり、励起状態のまま長い時間の現象=燐光がオー
ロラの光なのです。高空の超真空下では何十秒〜何百秒もの間、原子や分子が他の原子や分子と衝突する事なく励起状
態を維持し続ける事が出来、これがオーロラの光として見える。超真空中を磁力線に沿って飛んできた電子が超高速で
酸素原子に衝突し長時間(約150sec)もの間他の原子や分子と衝突する事なく励起状態を維持し続けるとと赤色にな
る。
又電子が窒素分子に衝突して電離した窒素分子は紫外線を放出し二次電子放出する。この二次電子が酸素原子に衝突す
ると酸素原子は緑色を発光するのだそうです。窒素分子に衝突すると青とかピンクの発色とか。難しい光なのですね。
下記のサイトなどは大変判りやすく説明されていますので参考にどうぞ。
アサヒビール自然科学教室:(このサイトは廃止されました)
オーロラが空に浮かぶ世界:http://www.u-zo.com/~alaska/
B:オーロラ発生要素
(1)太陽黒点の活動
太陽の活動が活発な場所に現れる太陽表面の斑点模様を太陽黒点と言い、此処からは強い光を放出しているとさ
れている。太陽表面に出来る黒点の数には約11年の周期があり最近では2000年から2001年が最多で太陽黒点活動
が活発な時期であった。この時期には太陽風に含まれる荷電粒子が多くなりオーロラ発生頻度が高くなると言われ
ている。(但し最近の研究報告の中には「黒点活動はオーロラ発生頻度に直接関係していない」との報告もある)
(2)磁気嵐(地磁気活動)
地球は大きな磁石です。だから地上では方位磁針が南北を指し示します。N,S極間には磁力線が発生している
訳ですが、地球を囲む磁力線は磁極軸に対象では無く、大きなエネルギーを有する太陽風の為に、太陽側は圧縮さ
れ、反対側へと偏った形になっている。荷電粒子は一旦太陽と反対側に貯まり磁力線に沿って地球の北・南極周囲
のリング状地帯へと向かう。強い太陽風が地球に届き地球の磁気層を乱す現象を磁気嵐と言う。磁気嵐が起きてい
る時はオーロラが発生しやすいと言われている。電波の伝播にも影響を与えている。
(3)大気中の微粒子密度
太陽風の荷電粒子が大気中の微粒子と衝突する事によってオーロラが発生している訳だから大気中の微粒子密度
もオーロラ発生と密接な関係があると言える。
これらの観測データからオーロラ発生を予測する事が出来る。アラスカ大学のホームページにオーロラ発生予報などの
情報が公開されているので参考に。
アラスカ大学オーロラ予報:http://www.gi.alaska.edu/predict.php3
このページのTOPへ戻る
C:オーロラ観測の条件
オーロラが発生していても地上の条件が整っていないと見えない。見る為の条件は次の通り。
(1)観測場所 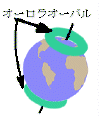
地球の磁極から数千km離れたドーナツ状の「オーロラオーバル」と呼ばれる地域すなわち緯度
60〜70度の帯状地域の上空100km〜を下端として、その上空数100km、時には1000kmまでも延びて
発生する。すなわちあの電離層で発生している事になる。上空100kmの空気分子数は地表の250万
分の1程度で真空に近い状態。すなわち「真空放電現象」が発生する場所なのです。「オーロラ
ベルト」とも言う。「オーロラオーバル」地帯に行けばほぼ360度の視界で観察できる。
この地域から離れるにつれて水平線に近付くので視界を邪魔しない場所が必要。南極の該当地域
は殆ど海の為にオーロラ伝説など殆どなくややもすると北半球だけに発生するものと誤解される。
観測地域として代表例を示す。
| No |
地 域
|
特 徴 |
| 1 |
北欧
|
・発生時間帯は午後8時頃〜午前1時頃。
・ホテルや街の明かりの少ない場所から見るタイプが一般的。 |
| アイスランド |
|
2 |
カナダ |
・発生時間帯は午後10時頃〜午前2時頃。
・街の明かりが届かない観察場所へ移動して見るタイプが一般的。
|
| アラスカ |
(2)晴天率
オーロラは雲より高い所に発生する現象の為に晴れる確立の高い所が良い。降雪や曇天では見えない。
晴天率が高い為には、海流や山脈などの影響を受けにくい場所が良いだろう。私は色々調査の結果カナダの内陸部
のイエローナイフへ2月下旬に行ったが連日の晴天に恵まれ素晴らしいオーロラを見る事ができた。
また週間天気予報のサイトも下記の例の様に色々あるので参考に。都市の指定をすると良い。
週間天気予報:http://weatheroffice.ec.gc.ca/forecast/city_e.html?yzf
(3)月齢
月の明るさもオーロラ観測には影響する。満月の下での弱々しいオーロラの場合は見づらいでしょう。がオーロ
ラベルト地帯で上空に発生するオーロラは可なり明るいので、写真撮影などでは月の明かりで周囲の山などの背景
とオーロラが写し込めるので好ましいとも言えます。新月では背景の写し込み困難。オーロラ観測のみなら新月。
私は満月の4〜6日後にイエローナイフを訪ねたが月明かりの下の写真撮影にむしろ良くオーロラ観測支障なし。
月齢を調べるフリーのソフトもあるので参考にダウンロードしたら如何。
月相検索ソフト:http://www.ausky.jp/store/index.php?kg=soft
(4)白夜 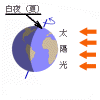
地球の地軸(北極と南極を結ぶ線)と地球の公転している面との間の傾きの為に極地周辺では夜
でも太陽の明かりを受ける神秘的な時期がありこれを「白夜」と言い、オーロラ観測には向いてい
ない。アラスカのフェアバンクスでは5〜8月にかけて太陽の光を一日中受ける。北半球では夏に
生じるから、オーロラ観測は寒い真冬が適当と言う訳です。
このページのTOPへ戻る
D:オーロラ観測時の服装
オーロラ観測や撮影時の服装を私の体験から要約しましょう。
昼間でもイエローナイフの冬はマイナス30℃前後。日本で使っているスキーウェアーと手袋で晴天の太陽の下に飛び
出したら5〜10分もすれば手が痛くなってくる寒さ。「バナナで釘が打てる世界です」
でも心配は無用。到着迄の飛行機の中は普段着で十分。飛行機が凍て付いたイエローナイフの滑走路に降り立つ。窓か
ら見る限り滑走路には積雪こそ無いが凍て付いている。タラップを滑らない様に気を付けながら降りて凍て付いた路面
を徒歩で待合室までの数分間は痛さを感じた。靴はゴム底などの滑りにくいものが良い。直ぐにホテルの迎えのバスに
乗込みホテルへ。ホテル内は空調完備で日本と何ら変わらない。さあ、オーロラ観測へ出発の服装は。個人差はありま
すが私の体験を。 
(1)イエローナイフのオーロラ観測は町の明かりを避け視界が開けた湖岸などの観測場所へ移動する
ので現地のオーロラツアー会社に参加するのが一般的。ここには立派な「防寒服セット」がレンタ
ル出来る様になっている。これが最適。一般的に、フード付きジャケット・防寒ズボン・防寒ブー
ツ・手袋・顔用マスクなどで構成されて居り、長袖シャツ2枚・厚手の靴下位を身に付けてこの
「防寒服セット」を着ると十分。但し、手袋はミトン形なのでカメラ操作等は困難。皮手を下に付
けて置くと便利。足先は痛さを感じたので2日目からは防寒ブーツの中に使い捨てカイロを入れた
ジャケットの両ポケットにも使い捨てカイロを入れて置き皮手でカメラ操作後の痛さ(冷たさ)を
これで暖めた。(右の写真は「防寒服セット」を着込んだ湖上の例です)
(2)マフラーも欲しい。フード付きジャケットで十分ですが首周りなどから外気が入ると寒いので。
(3)帽子。フード付きジャケットで十分ですがうっとうしい時には脱ぎたいもの。その時に重宝なのは耳が隠れるタ
イプの帽子。
(4)自己調達の場合は、上着・ズボン・手袋など外回りはゆったりした空気層のあるもので外気を遮断できる機密性
のあるもの。ジーンズなどは暖かくない。眼鏡使用者はマスクで曇るので要注意。一旦眼鏡を曇らすと取るのに苦
労します。風などあると目以外は隠せる事。うっかりすると直ぐに凍傷に罹りますから我慢は禁物。
このページのTOPへ戻る
E:オーロラ撮影に付いて
オーロラは瞼に焼き付ける事で十分かも知れないが出来る事なら記録として写真に撮りたいもの。幸いにもインター
ネット検索をすれば先輩達が色々とまとめてくれています。大変参考になりました。私が2003.2.20からのカナダ・イエ
ローナイフの3日間での体験を交えて以下にまとめて置きます。
1.出発前の準備
(1)電子式カメラは駄目。マイナス30℃以下の地、電池駆動カメラでは動かない。電池がもたない。勿論インスタ
ントカメラも駄目。マニュアルシャッター(機械式)カメラを準備する。勿論、電子式でも予備電池を暖めて置き
頻繁に交換覚悟なら撮れるかも。バルブ(B)機能のあるもの。それとフラッシュ内臓の場合はOFFに出来る
事。発光したってオーロラ迄届く訳が無いし周囲の人に迷惑。決してフラッシュは焚かないのが基本。苦情が出ま
すよ。例えば、ニコンのFM−3A,FM10,NewFM2,キャノンのNewF−1,EFなど。私はFM−
3A持参。電子式の場合はリチウム電池が低温特性が優れている。予備電池は余裕を持って日本で調達。
モータードライブも電池が問題でしょう。フイルムも寒さで破れ易いので手でゆっくりと巻き上げが良い。
(2)レンズは広角レンズ。オーロラは広範囲に出現するし地上の背景と一緒に写し込める方が良いから。且つ暗い為に
35〜24mmのF1.4〜1.8程度が良い。
(3)レンズフードは霜付着防止や余分な周囲光をカットする為にも必要。
(4)三脚も必需品。撮影は数秒〜数十秒シャッター開放にする必要性から頑丈なものが良い。
(5)自由雲台。すばやくどの方角の空へも向ける為には有った方が良いかも。
(6)レリーズ。カメラブレ防止の必需品。ロック付きが良い。外皮のビニールタイプは寒さで固くな
るので駄目。電子式カメラでバルブ付きを使用ならリモコンも良いだろうが、これも電池の低温
特性から交換が必要になるでしょう。 
(7)フィルムは高感度のISO400〜800程度のカラーフィルムを日本で調達しよう。露出計で
計る事も出来ませんから露出は山勘。その為にネガフィルムが良い。リバーシブルは露出が合え
ば色再現性は良いらしいが。又日本から持参の場合最近の空港でのセキュリティ検査のX線は強
いらしく「X線防護袋」が市販されていますので(右写真は例です)これに入れてハンドキャリ
しましょう。預け荷物のX線は厳しいので。
(8)懐中電灯。暗闇の中でのフィルム交換などに使用。赤いセロファンなどを巻いて周囲の人の迷惑
にならない様にする事。私の場合は寒さでとてもでは無いがグローブから手を出してのフィルム
交換は出来ませんでした。その為には36枚などの枚数の多いフィルムを準備した方がベター。
(9)カイロ灰。カメラ本体の保温やレンズに霜付着を防止するのに使う。又は使い捨てカイロ。
(10)カメラの防寒カバー。カメラ用品店にも有るでしょうが私は調達出来なかったので使い捨てカイロを数枚本体
に貼り付けタオルで包み込みました。同時にカメラ全体をスッポリと包み込める密閉性のある袋も必要。これは
気温の変化の生じる屋内(車内)〜屋外などの移動時の結露を押さえる為にこの袋の中に密閉して温度に慣らし
てからカメラを取り出す為に使う。
(11)粘着テープ。ピントや絞りリングが動かない様に固定するのにあれば便利。
2.現地での事前準備
カメラの準備は観測地へ出発までにホテルで済ませましょう。
(1)ピントは無限大(∞)に固定する。
(2)絞りは開放(F値を一番小さい値)に固定。
(3)シャッタースピードをバルブ(B)に固定。
(4)レリーズを取り付ける。 以上の調節後テープ等で固定。
(5)三脚に取り付け。足は絞まって置く。
(6)防寒カバーでレンズ部、レリーズ取り出し、三脚部を除いてカイロを取り付け覆う。レンズ周りはフードを
含めて開閉出来る様に覆う。密閉性のある袋に入れて外気と遮断する。
(7)電子式なら予備電池を使い捨てカイロに包んで体に付ける。予備のフィルムも準備。
(個人的には観察場でカメラを開けての交換はしない方が良いと思う)
3.観測地に到着後の準備
オーロラは何処に現れるかは不明。気ままに出現するので周囲の見晴らしを考えて場所を決め(オーロラだけを写
すよりも周囲の山や木を入れた画角が良い)三脚をセットする。360度方向が変えられる場所で。密閉性のある袋
のままオーロラの出現を待つ。その間はミトンの手袋で手を保護して待とう。
4.オーロラ出現の兆しを感じたらレンズを向けて密閉性のある袋を外しフィルム巻上げレバーを回してシャッターが
切れる状態にして、レンズの上には覆いをして様子見。オーロラが確認できたら画角を決めてレリーズでシャッター
を開く。シャッター時間はオーロラの明るさや月などの明るさにもよるが大体の目安としてISO800の場合で次の値を
参考に数秒間隔で何枚か連続して写した方が無難。(揺れていてぼんやりしたオーロラの時、F1.4ならば1,3,5,7sec等の段
階露出をする)
|
F |
1.4 |
2.0 |
2.8 |
| 動きが少なくぼんやりしたオーロラ |
3〜6sec |
5〜10sec |
10〜20sec |
| 動きが少なく満月に近い月明かり |
3〜6sec |
5〜10sec |
10〜20sec |
| 揺れていてぼんやりしたオーロラ |
2〜5sec |
3〜6sec |
5〜10sec |
| 揺れていて満月に近い月明かり |
1〜3sec |
2〜5sec |
3〜8sec |
出来上がりは現像して見なければ判らない訳ですから、段階露出をして同一場面を何枚も写す。レリーズはロック付
きのものが良い。静かにカメラが動かない様にレリーズする。フィルム巻上げはゆっくりと巻く事。寒さでフィル
ムのスプロケットが切れたら終わりですから。ファインダーを覗く時には息を止めて。ファインダに霜が付くと堪り
ませんから。フィルム交換等で明かりが必要な時は周囲の人に迷惑を掛けない様に一声かけてから。
5.撮影が終わった後、カメラを暖かい室内などに入れる時には、事前に密閉性のある袋に入れて内部の空気を追い出し
しばらくは廊下等に置いてから入れる。急に入れると結露して故障やカビ発生などの基です。
 このページのTOPへ
このページのTOPへ