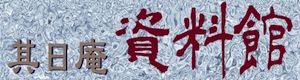其日庵資料館
其日庵著述テキスト
昇之助昇菊の尼ヶ崎を聽く
胴摺帽人(寄)
今日まで昇之助の語り物で、一番上出來の別品であった。人情の分け方、息の繼ぎ離れは、先《まづ》無難であった。元來此段は、寛政十一年未七月大阪道頓堀若太夫座にて、座元豐竹諏訪太夫にて開場し、豐竹麓太夫の語り場となりて以來、大入大人氣を取り爾後百二十一年後の今日まで、流行り流行りて流行り拔いたと云ふは、此段の作者、近松湖南、近松柳や、千葉軒等が、畢生の筆力を揮ふたのも與って力あるに相違ないが、主なる原因は麓太夫の力である。此人は元大阪洗場《ママ》の旦那衆で、鍋屋宗兵衞と云ふ立派な商人で、諸藝に堪能の中に、義太夫節は若太夫の門に入って、名音古今に秀《ひいで》たと云ふ、表三本の調子で上がカスレズ、只の三分で下が樂であったと云ふ、恐ろしい聲の人であった。殊にギンの音《おん》は、日本無双であった。其風《そのふう》を學んで、所謂麓場と云ふ一派が傳はったのである。是程流行った物を後世語り崩し、惡く/\/\なして、皆《みな》簓《ささら》拍子に斗りなって仕舞ったのである。夫《それ》に昇の助がアレ程語ったのは、女義中での大手柄である。
一、殘る蕾の花一つ(よろし)
二、水あげ兼ねし(ギンの譜《つぼ》が違ふた。此場のギンは押へた譜《つぼ》より、ニジッた丈け高いギンの音《おん》で出さねばならぬのである。
三、涙押止め(此フシを〆めたら、其息が拔けぬように、涙押止めた聲で、母樣《ははさま》にも祖母《ばば》樣にもと云ふ事)
四、泣く/\取出す緋縅しの(此邊初菊の文句に、ギンの音を遣はねばならぬ。一番困難な所)
五、操のクドキの假名足惡し。
六、十次郎の物語りの處丈け絃《いと》から離れて語る。
七、此段は光秀で見物が泣くように、夫を主意として作者が書いた物で、跡の人は皆剛氣の光秀がコタヘられぬようにする責め道具に出る物故、大落《おほおとし》までコタヘ/\た光秀が、トウトウ大泣《おほなき》に泣《なく》と云ふが仕組である。昇之助、昇菊はマダ夫を知らぬから、是から段々心掛くれば立派な尼ヶ崎を語ることが出來る。 八、段切の足取のノリも申分なし。兎も角女としては立派に語れて、絃《いと》も無難であった。
夫から其後又紙治《かみぢ》を聽いた處が、此は尼ヶ崎と違ふて役が重いから、如何な賢《かし》こひ此娘《このこ》でも、中々消化しない、夫は其筈じゃ、此段は増補の書下しに、染太夫が語って、古今の大入を取りしより此形《このかた》が殘ったのじゃから、第一枕の音遣《おんづかひ》が丸で出來ぬ。お三のサワリが、眞の西風に手が付いて居るから、アンナに謳ふてはならぬ。息斗りで語る節《ふし》である。古い本に
「染殿の改作の紙治の場を聽きし處、お三が一生に只の一度とも云ふべき悋氣言《りんきごと》を、語り仕舞はれに中に、世話女房の年増の客人達は、一人殘らず顏を上げ得られぬ程泣沈まれ候」
云々と書いてある位である。夫から治兵衞の詞《ことば》。あゝウワ/\してはいかぬ。ウワ/\は前の茶屋場である。此段では「イヤナ女房去っても、錢百貫落した氣がする」と云ふ心で小春に分かれた治兵衞が心重く氣も進まねど、女房の貞節に對して、何とも濟まぬ故に言譯をする積《つもり》で語る。夫が中々六ヶ敷イ、又お三の詞が、アヽ並んでは眞世話にならぬ。地合《ぢあひ》の方の間も、絃《いと》と共に並んで居る。夫が中々只ではコナせぬものじゃ。併し夫は、此可愛らしい二人の娘《こ》の罪ではない。教へる人が知らぬからである。親々は折角小供の時から修業させたのに、本の太夫の稽古でなく、淺墓《あさはか》な三味線引斗りの稽古故尤千萬である。帽人《わたし》は社命によりて義太夫節の評を書く爲めに聽《きゝ》に行け/\/\と云はるれども、今東京では、男女《なんにょ》とも太夫の冬枯で、何所に往く所がないからトウ/\是で昇之助昇菊を三度も聽いたので、此二人娘の藝風が好《すき》になった。其譯は昇之助の方は
第一、女太夫として聲がアレなら十分である。
第二、女太夫で年頃になると腹が薄くなるのに此娘は夫がない。
第三、腹の中に藝が消化《こな》れて居る。
又絃《いと》の昇菊の方は
第一、右手が慥かである。
第二、此前聽いた時より、三味線の拵が違ふて、一二三とも相當に音が泳いで來た。此間までは丸で拵が惡く、音は二間斗り前に落ちて居た夫が直った位故、此方も見込がある。
第三、マダ何と云ふても年が若い上に、藝の向上を計って居るから、修業の心掛けがあると見てよい。
以上の理由は評判に聞いて居た「親僧正、子天狗」とは違ふて居る事が分った、夫は其筈じゃ、何にしても一生を此藝で送る覺悟ならこそ、アレ丈け語り彈《ひ》くのである。即ち土臺が出來て居るから、此から向上の仕儲《しまふ》け、出世の仕勝《しがち》である。今が當人の藝の止りでは、一生小寄席藝人で終るより外仕方がない。今氣を入替へて修業をして本當の間で語ったり彈《ひ》いたりする事になれば、昨今其道の人に計畫の評判ある、女太夫の人形芝居に遣はるゝのは、此二人の娘《こ》が一番早いのである。其人形の間の踏める間になるには、根から葉まで本物になる稽古をせねばならぬ。夫はドウするかと云へば、太夫方の昇之助は先づ
第一、腹に芝居を覺えて、容《かたち》に芝居をしてはならぬ(あれ丈よく語る呂太夫が出世の出來ぬのも夫が一つの疵である。
第二、ドコモかも面白く語ってはイカぬ。
(太夫は人形遣《てすり》から總稽古の時に「オイ、其處を捕《つかま》へて語るな/\と云はれて藝が上るのである)
第三、ドコモかも間と足取《あしどり》が並んでは駄目である。(此處は此足と其の段によりて古《むかし》からチヤンと出來て居るから、夫がチヤンと極《きま》る「夫をアノ太夫は覺えて居ます」と云はるゝのである)
絃《いと》の昇菊が本物になる修業は、先づ
第一、目筋と云ふ物を極める修業をすると、體《からだ》がチヤンと極る(柱でもお客でも目が其處に極る事)體《からだ》が極ると、其の一段の外題と、其太夫を一所に抱へる事が出來る。
第二、右手《みぎ》は良いが、左が惡るい。夫を自分に知って修業をする事(左の指が皆違ふて居る上に、摑み譜《つぼ》である。絃《いと》を押へる指の外は、成丈け指を延ばす事、指を延ばすには、左の肱《ひじ》をモ少し張って上げて、ドコまでも、肱《ひじ》が下《さが》らぬようにすると、指が延ばされる。ソウすると、三味線の天柱《てんぢ》も、モ少し上って來て、體《からだ》の形が極る。ソウすると、今のよふに譜《つぼ》が早動きせぬから、間が大きくなる間が大きくなると、藝も大きくなる。藝が大きくなると太夫も幅が廣くなる。ソウスルと、三人の人形遣ひが廻って動かれてくるのである)
第三、早い一齣《ひとくさ》りを彈《ひ》く時は、早い撥《ばち》が揃はねばならぬ。遲い一齣《ひとくさ》りを彈《ひ》く時は、遲い撥《ばち》が揃はねばならぬ。ソウスルと、マクレぬ事になる。マクレねば間が並ばぬ。間が並ばねば、變なヘタリ撥《ばち》を遣はずして濟むから夫で藝が活《いき》て來る。藝が活《いき》れば、人形も活《いき》てくるのである。要するに二人とも、モツとグツと下手でも良いから、變な前受けを心掛けず、當り前になるよふに/\と心掛けると、二人の息がチヤンと、揃ふ事になる。ソウスルと、五枚八枚と語れば語る程、藝の箍《たが》が〆って往くから、客を引付けて仕舞ふて、手拍子も打たれず、立つにも立たれぬことになるものである。今の處では一齣《ひとくさ》り/\の、藝人となつて仕舞ふ。夫でヌケるから手を拍ったり、倦《あき》が來たりして、立って仕舞ふのである。
古人は「客を面白がらせよふと思ふて語るな。客を苦しがらせよふと思ふて語れ」と教へて居る。義太夫節は、作者が苦《くるし》い樣に斗り書いて居る。夫を苦《くるし》がる樣に語る修業をして夫を聽いた客が苦敷《くるしき》思ひをすると、夫が客の方で面白い。夫が客の滿足する處である。併し、何分子供の時から、段々と付いた癖故夫を直すには、大抵の事ではないが、直されねば、一生今の通り故、アセラズに氣永《きなが》に力強く修業せねば出來ぬものである。兩人《ふたり》は屹度女義太夫中には、前途のある藝人と思ふ故ヒイキに思ふて書いて置く(了)
一、殘る蕾の花一つ(よろし)
二、水あげ兼ねし(ギンの譜《つぼ》が違ふた。此場のギンは押へた譜《つぼ》より、ニジッた丈け高いギンの音《おん》で出さねばならぬのである。
三、涙押止め(此フシを〆めたら、其息が拔けぬように、涙押止めた聲で、母樣《ははさま》にも祖母《ばば》樣にもと云ふ事)
四、泣く/\取出す緋縅しの(此邊初菊の文句に、ギンの音を遣はねばならぬ。一番困難な所)
五、操のクドキの假名足惡し。
六、十次郎の物語りの處丈け絃《いと》から離れて語る。
七、此段は光秀で見物が泣くように、夫を主意として作者が書いた物で、跡の人は皆剛氣の光秀がコタヘられぬようにする責め道具に出る物故、大落《おほおとし》までコタヘ/\た光秀が、トウトウ大泣《おほなき》に泣《なく》と云ふが仕組である。昇之助、昇菊はマダ夫を知らぬから、是から段々心掛くれば立派な尼ヶ崎を語ることが出來る。 八、段切の足取のノリも申分なし。兎も角女としては立派に語れて、絃《いと》も無難であった。
夫から其後又紙治《かみぢ》を聽いた處が、此は尼ヶ崎と違ふて役が重いから、如何な賢《かし》こひ此娘《このこ》でも、中々消化しない、夫は其筈じゃ、此段は増補の書下しに、染太夫が語って、古今の大入を取りしより此形《このかた》が殘ったのじゃから、第一枕の音遣《おんづかひ》が丸で出來ぬ。お三のサワリが、眞の西風に手が付いて居るから、アンナに謳ふてはならぬ。息斗りで語る節《ふし》である。古い本に
「染殿の改作の紙治の場を聽きし處、お三が一生に只の一度とも云ふべき悋氣言《りんきごと》を、語り仕舞はれに中に、世話女房の年増の客人達は、一人殘らず顏を上げ得られぬ程泣沈まれ候」
云々と書いてある位である。夫から治兵衞の詞《ことば》。あゝウワ/\してはいかぬ。ウワ/\は前の茶屋場である。此段では「イヤナ女房去っても、錢百貫落した氣がする」と云ふ心で小春に分かれた治兵衞が心重く氣も進まねど、女房の貞節に對して、何とも濟まぬ故に言譯をする積《つもり》で語る。夫が中々六ヶ敷イ、又お三の詞が、アヽ並んでは眞世話にならぬ。地合《ぢあひ》の方の間も、絃《いと》と共に並んで居る。夫が中々只ではコナせぬものじゃ。併し夫は、此可愛らしい二人の娘《こ》の罪ではない。教へる人が知らぬからである。親々は折角小供の時から修業させたのに、本の太夫の稽古でなく、淺墓《あさはか》な三味線引斗りの稽古故尤千萬である。帽人《わたし》は社命によりて義太夫節の評を書く爲めに聽《きゝ》に行け/\/\と云はるれども、今東京では、男女《なんにょ》とも太夫の冬枯で、何所に往く所がないからトウ/\是で昇之助昇菊を三度も聽いたので、此二人娘の藝風が好《すき》になった。其譯は昇之助の方は
第一、女太夫として聲がアレなら十分である。
第二、女太夫で年頃になると腹が薄くなるのに此娘は夫がない。
第三、腹の中に藝が消化《こな》れて居る。
又絃《いと》の昇菊の方は
第一、右手が慥かである。
第二、此前聽いた時より、三味線の拵が違ふて、一二三とも相當に音が泳いで來た。此間までは丸で拵が惡く、音は二間斗り前に落ちて居た夫が直った位故、此方も見込がある。
第三、マダ何と云ふても年が若い上に、藝の向上を計って居るから、修業の心掛けがあると見てよい。
以上の理由は評判に聞いて居た「親僧正、子天狗」とは違ふて居る事が分った、夫は其筈じゃ、何にしても一生を此藝で送る覺悟ならこそ、アレ丈け語り彈《ひ》くのである。即ち土臺が出來て居るから、此から向上の仕儲《しまふ》け、出世の仕勝《しがち》である。今が當人の藝の止りでは、一生小寄席藝人で終るより外仕方がない。今氣を入替へて修業をして本當の間で語ったり彈《ひ》いたりする事になれば、昨今其道の人に計畫の評判ある、女太夫の人形芝居に遣はるゝのは、此二人の娘《こ》が一番早いのである。其人形の間の踏める間になるには、根から葉まで本物になる稽古をせねばならぬ。夫はドウするかと云へば、太夫方の昇之助は先づ
第一、腹に芝居を覺えて、容《かたち》に芝居をしてはならぬ(あれ丈よく語る呂太夫が出世の出來ぬのも夫が一つの疵である。
第二、ドコモかも面白く語ってはイカぬ。
(太夫は人形遣《てすり》から總稽古の時に「オイ、其處を捕《つかま》へて語るな/\と云はれて藝が上るのである)
第三、ドコモかも間と足取《あしどり》が並んでは駄目である。(此處は此足と其の段によりて古《むかし》からチヤンと出來て居るから、夫がチヤンと極《きま》る「夫をアノ太夫は覺えて居ます」と云はるゝのである)
絃《いと》の昇菊が本物になる修業は、先づ
第一、目筋と云ふ物を極める修業をすると、體《からだ》がチヤンと極る(柱でもお客でも目が其處に極る事)體《からだ》が極ると、其の一段の外題と、其太夫を一所に抱へる事が出來る。
第二、右手《みぎ》は良いが、左が惡るい。夫を自分に知って修業をする事(左の指が皆違ふて居る上に、摑み譜《つぼ》である。絃《いと》を押へる指の外は、成丈け指を延ばす事、指を延ばすには、左の肱《ひじ》をモ少し張って上げて、ドコまでも、肱《ひじ》が下《さが》らぬようにすると、指が延ばされる。ソウすると、三味線の天柱《てんぢ》も、モ少し上って來て、體《からだ》の形が極る。ソウすると、今のよふに譜《つぼ》が早動きせぬから、間が大きくなる間が大きくなると、藝も大きくなる。藝が大きくなると太夫も幅が廣くなる。ソウスルと、三人の人形遣ひが廻って動かれてくるのである)
第三、早い一齣《ひとくさ》りを彈《ひ》く時は、早い撥《ばち》が揃はねばならぬ。遲い一齣《ひとくさ》りを彈《ひ》く時は、遲い撥《ばち》が揃はねばならぬ。ソウスルと、マクレぬ事になる。マクレねば間が並ばぬ。間が並ばねば、變なヘタリ撥《ばち》を遣はずして濟むから夫で藝が活《いき》て來る。藝が活《いき》れば、人形も活《いき》てくるのである。要するに二人とも、モツとグツと下手でも良いから、變な前受けを心掛けず、當り前になるよふに/\と心掛けると、二人の息がチヤンと、揃ふ事になる。ソウスルと、五枚八枚と語れば語る程、藝の箍《たが》が〆って往くから、客を引付けて仕舞ふて、手拍子も打たれず、立つにも立たれぬことになるものである。今の處では一齣《ひとくさ》り/\の、藝人となつて仕舞ふ。夫でヌケるから手を拍ったり、倦《あき》が來たりして、立って仕舞ふのである。
古人は「客を面白がらせよふと思ふて語るな。客を苦しがらせよふと思ふて語れ」と教へて居る。義太夫節は、作者が苦《くるし》い樣に斗り書いて居る。夫を苦《くるし》がる樣に語る修業をして夫を聽いた客が苦敷《くるしき》思ひをすると、夫が客の方で面白い。夫が客の滿足する處である。併し、何分子供の時から、段々と付いた癖故夫を直すには、大抵の事ではないが、直されねば、一生今の通り故、アセラズに氣永《きなが》に力強く修業せねば出來ぬものである。兩人《ふたり》は屹度女義太夫中には、前途のある藝人と思ふ故ヒイキに思ふて書いて置く(了)
【解説】
ここに掲出したのは、杉山茂丸の義太夫評である。杉山茂丸が事実上のオーナーであった雑誌「黒白」の大正八年六月号に掲載されたものであり、記事の署名は胴摺帽人となっている。
杉山茂丸の義太夫に関する著作としては、「浄瑠璃素人講釈」(黒白発行所・1926、岩波文庫上下巻・2004)が夙に知られている。この著書に収録された義太夫論の多くは、雑誌「黒白」に連載されたものであり、確認できる最も早い時期に発表されたのは大正八年十月号であって、この時は「義太夫評」と題され、のち「義太夫虎の巻」と改題されて同誌の終巻まで掲載され続けた。
「浄瑠璃素人講釈」の雑誌掲載時の署名は単行本となった際の杉山其日庵名義ではなく、胴摺帽人名義となっていた。「胴摺」が明治三十年代の娘義太夫ブームの際の、「ドースル連」に由来することは明らかである。「ドースル連」とは娘義太夫の熱狂的なファン集団であり、サワリの部分で「どうする、どうする」と掛け声を発して騒ぎ立てたことから、この名で呼ばれるようになった。外に「追っかけ連」「ステッキ連」などという異称もあるという。
本篇は「浄瑠璃素人講釈」には収録されなかった義太夫評であるが、「素人浄瑠璃講釈」が初めて「黒白」に登場するより四ヶ月も早く掲載されていたこと、杉山には珍しく女流義太夫(女義)を取り上げていること、「浄瑠璃素人講釈」同様に杉山の義太夫技術論が具体的に展開されていることなど、注目に値する文献であろう。
取り上げられている昇之助昇菊とは、竹本昇之助と竹本昇菊という女義であるが、昇之助が義太夫を語り、昇菊が三味線を弾いてコンビを組んでいたもので、昇菊が姉、昇之助が妹の実の姉妹であった。明治三十四年に大阪から東京へ出て来たとき、昇菊はまだ十六歳、昇之助は十二歳の若さであったが、美貌の姉昇菊と、散切り頭の男装の妹昇之助のコンビは、たちまち江湖の評判となった。志賀直哉や夏目漱石、木下杢太郎といった文学者たちが、その作品中に昇菊と昇之助のことを書き記していることは、この姉妹がまだ若き日の彼らの心を惹きつけていたことの証左である。明治四十三年に詠まれた木下杢太郎の詩「街頭初夏」には、次の一節がある。
濃いお納戸の肩衣の
花の「昇菊昇之助」
義太夫節のびら札の
藍の匹田もすずしげに
街は五月に入りにけり。
杉山が本篇を執筆した大正八年の時点で、昇菊は既に三十代半ば、昇之助も三十歳ばかりにはなっていただろう。芸の力よりもアイドルとしての存在意義が大きかった明治三十年代とは異なり、大正期の女義は凋落の淵に立たされていた筈である。確固たる地位を築いていたのは豊竹呂昇や竹本素女であるが、本篇では昇菊昇之助の姉妹の実力に対して、杉山が極めて高い評価をしているのが注目される。しかし大正期に昇菊昇之助が明治期のような輝きを取り戻した様子はなさそうである。杉山の期待は叶えられなかったのであろうか。
なお、本稿執筆に際しては、水野悠子著「江戸東京娘義太夫の歴史」(法政大学出版局・2003)を参照した。
杉山茂丸の義太夫に関する著作としては、「浄瑠璃素人講釈」(黒白発行所・1926、岩波文庫上下巻・2004)が夙に知られている。この著書に収録された義太夫論の多くは、雑誌「黒白」に連載されたものであり、確認できる最も早い時期に発表されたのは大正八年十月号であって、この時は「義太夫評」と題され、のち「義太夫虎の巻」と改題されて同誌の終巻まで掲載され続けた。
「浄瑠璃素人講釈」の雑誌掲載時の署名は単行本となった際の杉山其日庵名義ではなく、胴摺帽人名義となっていた。「胴摺」が明治三十年代の娘義太夫ブームの際の、「ドースル連」に由来することは明らかである。「ドースル連」とは娘義太夫の熱狂的なファン集団であり、サワリの部分で「どうする、どうする」と掛け声を発して騒ぎ立てたことから、この名で呼ばれるようになった。外に「追っかけ連」「ステッキ連」などという異称もあるという。
本篇は「浄瑠璃素人講釈」には収録されなかった義太夫評であるが、「素人浄瑠璃講釈」が初めて「黒白」に登場するより四ヶ月も早く掲載されていたこと、杉山には珍しく女流義太夫(女義)を取り上げていること、「浄瑠璃素人講釈」同様に杉山の義太夫技術論が具体的に展開されていることなど、注目に値する文献であろう。
取り上げられている昇之助昇菊とは、竹本昇之助と竹本昇菊という女義であるが、昇之助が義太夫を語り、昇菊が三味線を弾いてコンビを組んでいたもので、昇菊が姉、昇之助が妹の実の姉妹であった。明治三十四年に大阪から東京へ出て来たとき、昇菊はまだ十六歳、昇之助は十二歳の若さであったが、美貌の姉昇菊と、散切り頭の男装の妹昇之助のコンビは、たちまち江湖の評判となった。志賀直哉や夏目漱石、木下杢太郎といった文学者たちが、その作品中に昇菊と昇之助のことを書き記していることは、この姉妹がまだ若き日の彼らの心を惹きつけていたことの証左である。明治四十三年に詠まれた木下杢太郎の詩「街頭初夏」には、次の一節がある。
濃いお納戸の肩衣の
花の「昇菊昇之助」
義太夫節のびら札の
藍の匹田もすずしげに
街は五月に入りにけり。
杉山が本篇を執筆した大正八年の時点で、昇菊は既に三十代半ば、昇之助も三十歳ばかりにはなっていただろう。芸の力よりもアイドルとしての存在意義が大きかった明治三十年代とは異なり、大正期の女義は凋落の淵に立たされていた筈である。確固たる地位を築いていたのは豊竹呂昇や竹本素女であるが、本篇では昇菊昇之助の姉妹の実力に対して、杉山が極めて高い評価をしているのが注目される。しかし大正期に昇菊昇之助が明治期のような輝きを取り戻した様子はなさそうである。杉山の期待は叶えられなかったのであろうか。
なお、本稿執筆に際しては、水野悠子著「江戸東京娘義太夫の歴史」(法政大学出版局・2003)を参照した。
【底本】
雑誌「黒白」大正八年六月号所載・黒白発行所刊
【註記】
○仮名使い、句読点については、底本に忠実に入力した。ルビは底本を参照しながら適宜取捨して《》内に記述した。
この記事のうち【解説】の著作権はサイト主宰者が保有しています。無断転載を禁じます。