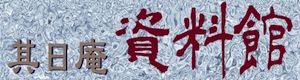其日庵資料館
其日庵著述テキスト
義太夫論
一、淨瑠璃及義太夫節の始め
盛夏嚴冬の差別なく、天狗の鼻を蠢(うご)めかして近所近邊の味噌を腐らし、有(あら)ゆる知人朋友より出入(でいり)の職人下女下男迄に迷惑苦痛を掛ける惨憺の所行を働くものは、凡そ下手義太夫の外決してあらざる可(べ)きを知る。而して近來日本の全國に亘りて尊卑上下(しょうか)の間(あいだ)此の天狗の鼻を蠢(うご)めかし、漫(みだ)りに他の諸藝を凌駕せんとする幾十萬の木葉(こっぱ)天狗が此の恐るべき遊藝に猛烈の勢(いきほひ)を加へ其の餘波澎湃として他の優尚なる藝界をも蕩破(たうは)し、尚ほ餘燼無(なか)らしめんとするの傾向あるは、時勢の推移に伴ふ現象とは云ひながら、其の因りて來(きた)る所の遠由(ゑんゆ)を考究するも亦(また)一の興味ある事たるを信ずるなり抑(そもそ)も聲曲なる者は、遠く源を元暦(げんりゃく)の昔に發し、彼の後鳥羽帝の時、信濃の前司(ぜんじ)行長入道(ゆきながにふだう)源平盛衰記より撰び拔(ぬい)て此の物語りを作り、盲人性佛(しゃうぶつ)に教へて琵琶に合せて唄はしむ。性佛(しゃうぶつ)山王權現に祈り、神勅によりて長短高下遲速緩急の譜節をなし之を唄ひて世に行はれしと聞く。夫(それ)より遙かの後(のち)永祿年間琉球より蛇皮を以て作りたる二絃の樂器を得来(きた)りて、時の樂人石村近江之(こ)れを改作して三絃となし、十二律四十八譜の定(じゃう)を設け、自在に音節に合して情樂を奏し、人をして感動せしめたりと。而して其頃織田信長の侍女小野通女なるもの詞藻(しそう)の道に通じ、命を受けて三州矢矧(やはぎ)の長者の娘淨瑠璃姫が東下りの牛若丸に情逢したる事を作述したるより、之(こ)れを淨瑠璃物語りと名付けたりと。此の文章古今の優美を蒐(あつ)め、婉麗を極めたるを彼(かの)澤住(さはずみ)、瀧野の両■(※けん=手偏に「僉」)校(けんぎゃう)之に譜節して語り出でしより、始めて淨瑠璃の名あり、夫(それ)より段々名人諸流輩出し、薩摩淨雲、杉山丹後の掾(じゃう)は彼(か)の江戸半太夫、双笠(さうりつ)、意教(いけう)等の祖にして山本土佐の掾(じゃう)は彼(か)の都一中の祖にして常磐津文字太夫に傳(つたは)り、又富本豐前太夫に傳(つたは)り、清元延壽太夫に傳(つたは)る。而して此淨瑠璃なるもの即ち杉山丹後、山本土佐、井上播磨より直統して竹本筑後掾(ちくごのじょう)に至る。之を斯道の祖たる竹本義太夫となす。此人大音嬌喉(きゃうこう)、一世を風動したる名人にして、主に人情の微を語り出(いだ)すに悲痛を以てし、之に加ふるに巣林子(そうりんし)近松の名文一世に涌溢(ゆういつ)して藝界俄かに旺盛を加へ、貞享、寛保の間は世人此の長藝の妙魔に魅せられて神心酔へるが如し。終(つひ)に此事時(このこととき)の 天子の叡聞に達し、御縁先きに召されて 天聽を辱(かたじけな)うし、奉侍の百官悉く感動して袖を絞らざる者無きに至る。主上深く其妙技を叡感あらせられ、賜ふに御簾の垂錦を以てせられ、之を以て衣冠とするを許させられ、更に御攝家に命ぜられて竹本筑後掾(ちくごのじょう)と任官せらる。義太夫一派の肩衣(かたぎぬ)に緞子、繻珍(しゅちん)等を用ひるの始まりにして、他藝人の同じ肩衣(かたぎぬ)を着(つ)くるは之を僭偸(せんとう)せるものなりと。義太夫面目身に餘れり、終(つひ)に之を農工商の民間教育の技藝たるべきの允許(いんきょ)を蒙り、大阪道頓堀の西に矢櫓(やぐら)を立て先に賜ふ所の錦布を以て裝束を拵へ、竹本筑後の掾(じょう)の高札を掲げ、西の宮の傀儡師(くわいらいし)百太夫の流れを汲む繰(あやつ)り人形の一流を追うて、芝居を興業するに至れり。即ち元祿三年庚午正月、彼の長州萩の産たる近松門左衛門が蓋世(がいせい)の博識を以て京都に遊べるを聘し之に數百番の著述を乞ひ、益々錦上花を散す的の繁榮を極めたり。而して享保九年の頃、此の筑後掾(ちくごのじょう)の門人たる豐竹越前少掾(とよたけえちぜんしょうじゃう)又た抜群の妙音と優技を以て、矢櫓(やぐら)を道頓堀の東に構へ、驟風砂を捲くの勢(いきほひ)を以て、衡を竹本座と爭ふに至りしは、實に斯界の兩雄として、末世の今日迄狂言外題に、東物西物の別ある始元(はじめ)たるを知るべし。之より名人四方に涌出し、隨(したが)って譜節にも雄大の進歩と改竄を加へたるは、今日現存するの音節に照して最も明瞭なる事實にして恰も一譜節の改良に、一名人を費して一段の外題を完成したりと云ふも敢て誣言(ぶげん)に非ざるべし。即ち一段の中(うち)に文彌と云ふ節あるは岡本文彌の節にして、表具と云ふは表具又四郎の節、又(ま)た説教と云ふは説教與八郎の節にして、道具屋と云ふは道具屋吉右衛門の節なり。彼の林清と云ふは日暮林清の節にして、播磨と云ふは井上播磨の節たるを知るべし。此(かく)の如く其一世に巨技長藝の名人が數百年間數代に亘りて、丹精と錬磨とを重ねて、其深奧を極めたる妙技を無學文盲なる藝人、或(あるひ)は我儘放埒なる素人が所謂テレホーン的口移しに小閑一二ヶ月の間に習得して直(ただち)に渡し守りを呼ぶが如きダミ聲を擧げて怒鳴り散す故、其前後左右にある者犬猫にあらざる限り、苟(いやしく)も人間の形を備へたる者は、忽ち悩苦の深淵に陷(をちい)り、遂に眩暈卒倒の重患に罫(かゝ)りて天壽を縮むるに至る。又た實に當然の事に屬す。然りと雖も物皆一利一害あり、此(かく)の如く精神上不衛生なる遊藝にも、其名人が古來より人心に與へたる感化の強大なる實に驚くに耐へたるものあるを見る。余は之(こ)れより稿を追ひ、義太夫節が社會上に現映したる事實を論じ、進んで古今斯道藝人の鍛錬優劣如何を批評するの興味を擅(ほしい)まゝにせんと欲するなり。
二、芝居の始元
以上の如き系統と歴史とを以て、前代未聞の繁榮を極めたる義太夫節は、當時殆ど人心の全部を支配せんとする勢(いきほひ)となれり。何(いづ)れの頃か知らぬが此義太夫節の興隆に對し沛雨に雷霆(らいてい)を副(そ)ふるが如き援勢を爲したる者は歌舞伎芝居の発生なり。(余之を京都の或る古老に聞く、お國の咄等は別なり。)京都祇園町の興行師仁幸(にんこう)なる者此義太夫節の旺盛を見て、新機軸を案出し、今若(も)し彼(かの)義太夫節の人形芝居を改新して代るに人を扮粧(ふんしょう)して彼の詞(ことば)を云はしめ、太夫をして地合(ぢあひ)のみを謳はしめなば、働作(どうさ)彌々(いよ/\)眞に迫りて、人心の好嗜に適すること更に疑ひある可(べか)らずと頻(しきり)に工夫を凝らせども、當時斯樣の馬鹿氣たる人形の代用をなす者なきより風斗(ふと)した思ひ付より、四條河原の辻藝人を收傭し、當時小説の挿絵師滑川國丸の畫(ゑ)を基(もと)として鬘(かつら)及顔の色彩より裝束の配合に至るまでを案配し、始めて祇園坂下廣小路に於て若竹花太夫、小嵐龍紋の看板を掲げて歌舞伎芝居を興行したるに、其繁榮殊に甚しく、一の外題を三月より六月迄も興行したることありしと云ふ。此故に今尚ほ俳優の姓氏に京丹波の村名を存するは即ち其因證なり。市川、中村、嵐、片岡、尾上等皆大道若(もし)くは河原藝人の出所たりし村名なりと(未だ其是非を知らず)此芝居の興行一たび世に行はるゝや靡然(びぜん)として天下の藝界を席惓し、官民上下(しゃうか)智愚賢凡の別なく、之を見物するに、晨(あした)に出で夜(よは)に歸り、實に寢食を忘れて此の流行の技藝うぃ追隨するの有樣なり。此(こゝ)に於て一時旺盛を極めたる義太夫節、人形芝居は漸次其の勢力を失墜するの止むを得ざるに陷(をちい)りしは、此(こゝ)に不可思議なる印象が社會道徳の上に實現するに至りたる結果なるを知るべし。乃(すなわ)ち君臣、父子、夫婦、兄弟及び男女の交情、朋友等の友誼に對する情愛の發達此れなり。其結果あらゆる勞苦貧難死殺等人生極端の慘事を擧げて、悉(ことごと)く其情愛遂行の上の犠牲に供して更に遺憾なきの傾きあり。啻(ただ)に遺憾なきのみならず、之を極端なる方法を以て遂行したる者に對して却(かへっ)て偉大の同情と賞賛とを以て歡迎して倦(う)まざるに至れり。此れ吾國(わがくに)獨得の名産たる大和魂發達の隆盛時期にして、我國開闢(かいびゃく)以来如何なる学者教育家を喚起し來るも、此(かく)の如き強大なる感化を全社會の精神に印象することは爲し能はざるべし。吾國(わがくに)素より文字(もんじ)なく、典籍なく、人心教育の材料としては寥々(れう/\)一の尊宗を標彰すべきものなく、億兆の民心長く教義に渇して、其の精神の発動を抑壓する茲(こゝ)に二千有餘年、偶々(たま/\)謀反あり戦争あり簒奪あり復讎(ふくしふ)あり、其の觸るる所の境遇によりて一部の發動は、歴史の繼續と共に試演し來りたれども、此(かく)の如く社會全般の人情隱微にまで浸染して一齊の發動を現出せしことはあらざるべし。佛教の渡來は其教化著大なりと雖も權化垂跡(すゐじゃく)の方便によりて徒(いたづ)らに現當二世安樂を説き儒教の普及充滿せりと雖も徒(いたづ)らに内綱常の義に因循して外活發の發揚に資せず、基督(キリスト)の教義東西に馳突(ちとつ)すれども一神空漠の存否すら信念せしむる能はず。彼れと云ひ此れと云ふも皆、悉(ことごと)く一部の偏偶に蹌踉する議論にして未だ人生慘極(さんきょく)の死を顧ずして遂行せんとする強大無比の感化を與ふるの勢力あるものに非ざるなり。獨り此の義太夫節に伴ふ人形及び俳優芝居の如きは其の感化力の猛烈なる吾國(わがくに)に於て前古無比なりと斷言して憚らざるを信ずるなり。此れ蓋(けだ)し其の太夫俳優等の妙技素より其の感化に助けあるべきは論を待たずと雖も、其の狂言作者の筆力亦(ま)た之れが主因たるや疑ひを容れざるなり。當時義太夫節に伴ふ狂言作者は、多くは吾國(わがくに)に於ける有數の學者にして、深く和漢古今の書を渉獵し、東洋的教義の如何を鑒別(かんべつ)し、隨(したが)って其社會上政治上に發現する事柄の是非をも論議するの資格を有する者なるが、時恰も封建武門の專横に制せられ、其の口を箝せられ、其の筆を縛せられて不平鬱勃の間空しく糊鹽(こえん)に■(※けん=手偏に「僉」)■(※ぎょう=口偏に「禺」)して彷徨するの砌り、一たび義太夫節の世に發現するや、呼■(※こう=日偏に「孝」)奔來、各々競うて著作場裏に奮鬪するに至れり。而して其の競技の決勝點とする所は、少しにても著大の感化を世人に與ふるを以て主眼とする譯故其の綴る所其の慮る處相競うて極端より極端に馳するは勢(いきほひ)の止むを得ざる所たり。而して其結局は人生の極慘たる死を以て爭はざるを得ざるに至れり。此の死なるものを最終の判決としてあらゆる趣向を錬磨し、各々其死方(しにかた)殺し方、死ならざるを得ざるに至る順序、殺さざるを得ざる情實に對して種々紛糾したる手段を弄ぶも、終(つひ)に其の主眼たる目的は死と云ふことに歸着せしは爭ふ可(べ)からざるの事實なり。扨(さ)て此の死に導き來るの順序として總ての階級、君臣、父子、夫婦、兄弟(けいてい)、朋友或(あるひ)は男女相愛の状態を捉へ來りて布演輯述(しじゅつ)する筆力文技の非凡なるは、一篇の義太夫を治亂數百年の間に演藝して飽かず、巧拙數千人の藝人が演譚して倦まざるを見ても知るべし。余は此狂言の社會に及ぼしたる感化の關係を論ずるの序(ついで)を以て、當時の狂言作者なるものを紹介するの必要を見るなり。
三、竹本座及豐竹座狂言作者
竹本座の作者として井原西鶴(此は元俳諧師にして「暦」と題するもの、又「凱陣八島」と云ふ淨瑠璃を作りたる人なりと。近松は狂言作者としては此人の門人なりしとか)近松門左衛門、竹田出雲、長谷川千四、三好松洛、錦文流(にしきぶんりう)、文耕堂、吉田冠子、近松半二、並木千柳、二歩堂、淺田可啓、中邑閏助(じゅんすけ)、八民平七、榮善平、北窓後一、竹田因幡、竹田平七、竹本三郎兵衛、竹田外記、竹田和泉、竹田瀧彦、竹田正藏、小川半七、近松景鯉(けいり)、竹田伊豆、並木永輔、竹土丸、福松藤介、竹田文吉、北脇素人、一誠堂、寺田兵藏、近松東南、松田才二、竹田新四郎、苣(ちさ)源七、春江堂(しゅんかうだう)、原爲裳(いしゃう)、近松能輔、松田ばく、守川文藏、中村粂次、春木元輔等は最も著名の人々の由にして、竹本座の繁榮實に推知するに足るべし。而して豐竹座の狂言作者は紀海音(きのかいおん)、西澤一凰、並木千柳、爲永太郎兵衛、安田蛙文(あぶん)、安田蛙桂(あけい)、並木宗輔、同丈助、同良介、同素柳、同五瓶、村上嘉助、豐竹應律、豊岡珍平、淺田一鳥、浪岡橘平、同鯨兒(げいじ)、同蟹藏、中邑阿契(あけい)、中邑阿笑、豐田正藏、梁塵軒(りょうじんけん)、豐正助、難波三藏、黒藏主(こくざうす)、七才子、三津飲子(いんし)、竹本三郎兵衛(竹本座と兩方あり)清水三郎兵衛、若竹笛躬(ふえみ)、近松東南(竹本座と兩方)菅專助、豐竹勘六、但見彌四郎、豐竹上野、並木齋治、福松藤助等が著名なる人々の由なり。當時竹本座の隆盛に對衡して、彼の巨名の義太夫節即ち筑後掾(ちくごのじゃう)が前を遮りて、其門人たる豐竹越前少掾(えちぜんせうじゃう)を擁立し、同じ大阪の道頓堀の東に於て、堂々旗幟を飜したるは、全く是(ここ)に列記する是(これ)等作者の手腕にして、如何に其の出でたちの雄健なりしかを想望せずんばあらざるなり。
余は之れより進んで以上作者等の筆に成る著作の梗概を論じ、併せて狂言の如何に世人に感化を輿へたるかを研究せんと欲するなり。
余は之れより進んで以上作者等の筆に成る著作の梗概を論じ、併せて狂言の如何に世人に感化を輿へたるかを研究せんと欲するなり。
四、大和魂の興隆
斯(かく)の如き多数の作者は、各々特殊の手腕を提(ひっさ)げて東西両座の芝居に割據し、多年錬磨の筆鋒を奮うて其技倆を競ひしは、今日其著作の跡に付て見るも、甚だ瞭然たるものあるなり。而して其脚色の骨子とするものは、即ち「死」の一事を以て人情に迫り、總ての波瀾起伏は之れより發生することゝせり。之れは彼の佛教が生老(しゃうらう)病死の悲哀的を根據として百萬の經典を縱横し、以て人情迷悟の妙機を制したるに傚(なら)ふものにして、即ち人類最強感の「死」を以て基礎としたるを知るべし。其君臣の義は之を以て貫き、父子の親も之を以て遂げ、夫婦の和又之を以て唱ふ。是(ここ)に於てか社會百般の出来事は悉く死に纏綿したる情實にして、之を解決する死の研究をなす事は、此等作者によりて愈々(いよ/\)進歩したりと云ふべし。此故に己れの尊信する道義の爲め、若くは恥辱の爲めには容易(たやす)く死と云ふことを以て解決するは全く此の狂言作者の圓滑なる慫慂に出で、之を受けて譜節演布したる巧妙なる藝人によりて、全脳を感化せられたる者と云はざる可(べ)からず。要するに此の義太夫節の感化に魅せられたる吾(わが)國民は、能(よ)く「死」と云ふことに極端の興味を翫味(ぐわんみ)し盡すに至れり。
彼の近松門左衛門は元祿十六年未五月所謂世話淨瑠璃の始元たる、お初徳兵衛「曽根崎心中」を書下(かきおろ)してより、天下青若(せいじゃく)の男女は競うて心中の興味に酔ひ、死は戀の實なるかの疑ひを起さしめ、盛(さかん)に心中の試行實現を見るより、終(つひ)に時の政府をして曽根崎心中の興行を禁斷せしむるに至れり。作者の筆力茲(こゝ)に至りて極まれりと云ふべし。此(かく)の如く作者は何(いず)れも死を以て基礎として巧妙の筆を舞(まは)し、藝人は死の情を布演するに滿腔の精を傾けたり。此(ここ)に於て天下は死の競爭場裡と成たりと云ふも敢て過言に非(あら)るなり。果して然らば余が前言したる大和魂なるものは、己れの信念及び恥辱の爲めに遺憾なく死を實行するものにして、之れを薫陶成育したるものは義太夫節と云ふ音曲の力最も其多きに居るを斷言し得べし。如何となれば吾國(わがくに)故(も)と文字(もんじ)なく、典籍なく、人心を教育するの材料に乏しく、今日に於てさへ尚ほ外國の文字(もんじ)即ち半ば漢字を借り、半ば中國中古の僧空海の拵へたる「いろは假名」を以て填補(てんぽ)せざれば、文章を成す能はざる程の教育的程度の國たり。彼の神代記、古事記、日本書紀等の書は、一も國民をして決死の猛勇を養成すべき感化を輿ふるの書に非ざるなり。其他宗教的の教育は却て死を恐るゝか、死を敢てせざるかの本旨に外ならざるもの許(ばか)りにて、此(かく)の如く容易(たやす)く死するの教育、即ち大和魂的の教育は此の義太夫節の外、吾國(わがくに)に古來より其材料なきこと明らかなり。而して此等狂言作者の趣向は、終(つひ)に其の死にかた、殺しかたの競爭となり、少しにても悲壯慘烈の死にかたを爲す程、一般の欽祟(きんすう)を引く事に誘ひ來れり。寛保元年五月彼の文耕堂、松洛、小出雲等が「新薄雪物語」を書下して、竹本播磨掾(はりまのじょう)等が之を演じて、當時の藝界を驚倒したり。此の狂言には三人笑ひと云ひて、或る事情の爲め三人同時に腹を切りて痛くないと云ひて笑ひ死する事あり。また寛延元年辰八月松洛、出雲、千柳等が假名手本忠臣藏を書下し政太夫、島太夫、此太夫等の之を演ずるや、吾國(わがくに)忠臣の大義を全國民の腦髓に刻銘したり。而して其の勘平切腹の段に於て、原郷右衛門が氣息奄の勘平に向って勘平血判と云ふや、其聲に應じて心得たりと絶叫し、腹十文字に掻切りて臟腑を抓んでシッカと捺(お)すと云ふ。元來指の頭に附着する血汐にて十分なる血判に臟腑を抓んでとは、誇大の虚言も亦た甚だしけれども、名人島太夫の演藝眞に迫り人をして實に勘平が死(しに)かたの慘烈に同情を極めしむ。其他正徳二年七月近松作の嫗山姥(こもちやまんば)の如き阪田の時行(ときゆき)は腹を切る其魂妻八重桐の胎内に入りて怪童丸を産むなど、又寛政十一年七月近松柳等の作に成った「大功記鷺の森」の鈴木孫一は或る事情の爲め幼弱の實子二人に刀を輿へ少しづゝ己れの首を斬り落させて本懷と云ふ等、漸次極端より極端に至る。死にかたの競爭は一番は一番より悽壯を極めたり。世は泰平なれど、音曲は修羅場なり。人心は平穩なれども芝居は鮮血淋漓たり。此(かく)の如き薫陶を下層民衆が受けて永年の間一日も間斷なく感化せられたれば、其衷心より言語動作に至るまで、悉く芝居的俳優的に變化し去りたるは殆ど事實的に現映し來れり。所謂日本人の名誉なるものゝ表式は彼(か)の日清日露兩度の戰爭に矮躯小弱の國民が、其の慘烈の死樣を競爭して或(あるひ)は軍人の模範と云ひ、或(あるひ)は軍神と云ふもの亦(ま)た爭ふ可(べ)からざる因由の存するなくんば非ざるなり。而して其名誉なるものゝ俳優的なる、彼(か)の出征將軍の凱旋するや、萬歳聲裡に擧手答禮する時、成田屋−−と大呼せば如何に満足するならんを想見し、或(あるひ)は議會壇上に立って、鷹揚四邊を睥睨するの時音羽屋−−と高唱せば、如何に得意なるべきを忖知(そんち)せずんばあらざるなり。其他婦女の男子に戀想する、恰(あたか)も八重垣姫の勝頼に於けるが如く妻の夫に貞操なる、亦正にお三の治兵衛に對するが如し。侠客は幡隨院を氣取り、義勇は荒木又右衛門を擬す。蓋(けだ)し之れ音曲隆盛の一大現象なり。而して義太夫節の流行も其風俗に對するの傷害敢て少なきに非らざるべきも、一方吾(わが)大和國魂の興隆に資するもの尤も著大なるべきを信じて止まざるなり。余は茲(こゝ)に至りて益々本論を進むるの機會あることを喜ぶなり。
彼の近松門左衛門は元祿十六年未五月所謂世話淨瑠璃の始元たる、お初徳兵衛「曽根崎心中」を書下(かきおろ)してより、天下青若(せいじゃく)の男女は競うて心中の興味に酔ひ、死は戀の實なるかの疑ひを起さしめ、盛(さかん)に心中の試行實現を見るより、終(つひ)に時の政府をして曽根崎心中の興行を禁斷せしむるに至れり。作者の筆力茲(こゝ)に至りて極まれりと云ふべし。此(かく)の如く作者は何(いず)れも死を以て基礎として巧妙の筆を舞(まは)し、藝人は死の情を布演するに滿腔の精を傾けたり。此(ここ)に於て天下は死の競爭場裡と成たりと云ふも敢て過言に非(あら)るなり。果して然らば余が前言したる大和魂なるものは、己れの信念及び恥辱の爲めに遺憾なく死を實行するものにして、之れを薫陶成育したるものは義太夫節と云ふ音曲の力最も其多きに居るを斷言し得べし。如何となれば吾國(わがくに)故(も)と文字(もんじ)なく、典籍なく、人心を教育するの材料に乏しく、今日に於てさへ尚ほ外國の文字(もんじ)即ち半ば漢字を借り、半ば中國中古の僧空海の拵へたる「いろは假名」を以て填補(てんぽ)せざれば、文章を成す能はざる程の教育的程度の國たり。彼の神代記、古事記、日本書紀等の書は、一も國民をして決死の猛勇を養成すべき感化を輿ふるの書に非ざるなり。其他宗教的の教育は却て死を恐るゝか、死を敢てせざるかの本旨に外ならざるもの許(ばか)りにて、此(かく)の如く容易(たやす)く死するの教育、即ち大和魂的の教育は此の義太夫節の外、吾國(わがくに)に古來より其材料なきこと明らかなり。而して此等狂言作者の趣向は、終(つひ)に其の死にかた、殺しかたの競爭となり、少しにても悲壯慘烈の死にかたを爲す程、一般の欽祟(きんすう)を引く事に誘ひ來れり。寛保元年五月彼の文耕堂、松洛、小出雲等が「新薄雪物語」を書下して、竹本播磨掾(はりまのじょう)等が之を演じて、當時の藝界を驚倒したり。此の狂言には三人笑ひと云ひて、或る事情の爲め三人同時に腹を切りて痛くないと云ひて笑ひ死する事あり。また寛延元年辰八月松洛、出雲、千柳等が假名手本忠臣藏を書下し政太夫、島太夫、此太夫等の之を演ずるや、吾國(わがくに)忠臣の大義を全國民の腦髓に刻銘したり。而して其の勘平切腹の段に於て、原郷右衛門が氣息奄の勘平に向って勘平血判と云ふや、其聲に應じて心得たりと絶叫し、腹十文字に掻切りて臟腑を抓んでシッカと捺(お)すと云ふ。元來指の頭に附着する血汐にて十分なる血判に臟腑を抓んでとは、誇大の虚言も亦た甚だしけれども、名人島太夫の演藝眞に迫り人をして實に勘平が死(しに)かたの慘烈に同情を極めしむ。其他正徳二年七月近松作の嫗山姥(こもちやまんば)の如き阪田の時行(ときゆき)は腹を切る其魂妻八重桐の胎内に入りて怪童丸を産むなど、又寛政十一年七月近松柳等の作に成った「大功記鷺の森」の鈴木孫一は或る事情の爲め幼弱の實子二人に刀を輿へ少しづゝ己れの首を斬り落させて本懷と云ふ等、漸次極端より極端に至る。死にかたの競爭は一番は一番より悽壯を極めたり。世は泰平なれど、音曲は修羅場なり。人心は平穩なれども芝居は鮮血淋漓たり。此(かく)の如き薫陶を下層民衆が受けて永年の間一日も間斷なく感化せられたれば、其衷心より言語動作に至るまで、悉く芝居的俳優的に變化し去りたるは殆ど事實的に現映し來れり。所謂日本人の名誉なるものゝ表式は彼(か)の日清日露兩度の戰爭に矮躯小弱の國民が、其の慘烈の死樣を競爭して或(あるひ)は軍人の模範と云ひ、或(あるひ)は軍神と云ふもの亦(ま)た爭ふ可(べ)からざる因由の存するなくんば非ざるなり。而して其名誉なるものゝ俳優的なる、彼(か)の出征將軍の凱旋するや、萬歳聲裡に擧手答禮する時、成田屋−−と大呼せば如何に満足するならんを想見し、或(あるひ)は議會壇上に立って、鷹揚四邊を睥睨するの時音羽屋−−と高唱せば、如何に得意なるべきを忖知(そんち)せずんばあらざるなり。其他婦女の男子に戀想する、恰(あたか)も八重垣姫の勝頼に於けるが如く妻の夫に貞操なる、亦正にお三の治兵衛に對するが如し。侠客は幡隨院を氣取り、義勇は荒木又右衛門を擬す。蓋(けだ)し之れ音曲隆盛の一大現象なり。而して義太夫節の流行も其風俗に對するの傷害敢て少なきに非らざるべきも、一方吾(わが)大和國魂の興隆に資するもの尤も著大なるべきを信じて止まざるなり。余は茲(こゝ)に至りて益々本論を進むるの機會あることを喜ぶなり。
五、作者の苦心
義太夫節の起因及其歴史又此音曲の社會人心に及ぼしたる反應等は既に其概略を論了したるを覺ゆ。故に余は更に當時の狂言作者が如何に苦心したるかを探求せんとす。
抑々(そも/\)昔時の著述家即ち作者が、其一篇の趣向と文章に苦心したるの状態は實に筆紙の能く盡す所にあらず、慘澹と云はんより寧ろ決死の覺悟を以て従事したるの形跡瞭々たるを見るなり。蓋(けだ)し現代の小説か若くは著作家が惰慢終(つひ)に湯薪の資に窮し、下宿屋の二階に午睡纔醒(ざんせい)の餘暇を以て淺薄の思想に筆を驅り、原稿一頁の價を爭ふか、又は過譽虚名の學者が賣文一時の榮華に乘じて、夏は署を涼風涼泉の地に避け、冬は寒を硝窓煖爐の間に遯(のが)れ、放辟酒婦に戯むるゝの傍ら、一氣徒らに筆馬に鞭(むちう)って成る所の文章と、日を同じうして論ずべきものに非ざるなり。古(いにしへ)の作者は勞を忘れ、貧を忘れ、病を忘れ、終(つひ)に死生の境界を忘失して精神を其の著作に傾注し、一に其の成就する所の作篇を以て生命として蹇々(けん/\)倦まざるを見るなり。
余曾(かつ)て巣林子(さうりんし)近松の桃山祠畔著作堂を圖を見るに、方二間許りの草廬(さうろ)にして四方壁を塗り、其の一方に三尺許りの入口あり、他の一方に三尺角許りの窓あり、此の前に机を置き、傍らに火鉢及手燭附け木等を置き、他の四壁は悉く書棚にして和漢の參考書を堆積し、殆んど暗室同樣の裡に棲坐(せいざ)し、一たび此中(このうち)に入る時は直ちに虚淡の境界に入り、心中一の衛生なく、生死なく、只だ人情纏綿の空想に耽りて心思微動の煩念なし、門人の食を搬するや窃(ひそか)に入口に挿入して、■(※しば=しかばねに「婁」)々(しばしば)其食了したるや否やを窺ふのみなりと。此(かく)の如くして趣向を練り、句調を敲いて勞苦と老來とを知らず、一身の全部頓(とみ)に著述娯樂の花園に■(※しょう=ぎょうにんべんに「尚」)■(※よう=ぎょうにんべんに「羊」)して心念又た古今に來往し、事蹟作例に窮すれば燭を點じて四壁の參考書を獵り、妙趣堂に充ち、奇興心身を襲ふに至りて一篇の文章を成すと。嗚呼宜(むべ)なる哉、其の著述の後世に亘りて、至大至強の感化を人心に致し、其同文同篇は喩へ千百回之を反讀するも尚(な)ほ厭(あ)く事なきの状を見るや。而して彼れ巣林子(さうりんし)は其の門生に箴して曰く、主旨は卑近を貴び、趣向は紛纏(ふんてん)を要し、句調は平易を可とすと。此の三つのものは彼れが百世の人心を驚倒して高歌低唱、今尚(な)ほ措く能はず、終(つひ)に風俗を搖撼(えうかん)するに至るの秘奧たるや、更に疑を容れざるなり。
又た彼の簑笠漁翁(さりうぎょおう)瀧澤馬琴の如き、一代の著作多くは唐誕に因る。其の博識廣聞は彼れが天資の強記と剛根とによって、描出したる戯作なりと雖ども、其の苦心慘澹より産出したるの興味は、忽焉として紙表に踴躍(ゆうやく)するあり。所謂人心を搖撼(えうかん)し風俗を變易するもの、此(こゝ)に於て存するを知る。而して彼れが著作中の一大篇たる「南総里見八犬傳」は殆んど絶筆にして、其の自白する處、實に惨澹にして又快なるを覺ゆ。彼れは天保四年癸巳の初秋輕微なる眼底炎に罹れり。爾後天保十年己亥までは七年間醫を求め、療を加ふるの暇なく不撓不屈、此の稿の満尾(まんび)せしむるに於て死尚(な)ほ辭せざるの決意あり。其の十八罫の稿本を十四罫となし、十罫となし、終(つい)に七罫となし、五罫となして、恰も兒童の清書大になすも尚(な)ほ其の稿を止めず、終(つい)に翌年十六年庚子の春に至りて失明闇黒となれり。彼れ若し普通常科の人たらば、茲(こゝ)に至りて筆を投じて止むべきに、由来東洋不世出の文豪矣爲(なんす)れぞ箇般(こはん)の災禍を以て其の精神を搖がすべき、益々胸憶の興趣を奮うて終(つい)に其の可憐の孫娘を捕へ來り、一字一句、若くは一事一例をも苟(いやしく)もせず、古籍舊典を代讀せしめ、隨って代寫せしめ、孳々焉(じゝえん)として倦まず、終(つい)に其の起稿より二十八年目、萬延元年庚辰の歳を以て満尾(まんび)脱稿するに至れりと。其勁勇巨膽(けいゆうきょたん)復(ま)た何を以てか之れに比せんや。即ち此れ等著述家の眼中には素より寒暑なく、飢渇なく、疾病なく、衛生なく、死生なきや論を俟たざるなり。彼の並木宗輔が「嫩軍記(ふたはぐんき)」を著すに、須磨の苫屋に寝(い)ねて漁夫に撻(むちう)たれ、三好松洛が「襤褸錦(つゞれのにしき)を著すに辻堂に起臥して乞食(こつじき)と誤られたるも、亦た其一例たるを知るべし。果して然らば余が現代の著述家に向って窃かに淺薄と云ひ惰慢と叫ぶも、敢て無禮の罵言に非ざるを信ずるなり。若し其(それ)著書にして坐(そゞ)ろに再讀に値し、誠實なる感化を社會に與ふるに足るものあらば、余は直に甲(かぶと)を其門下に脱し、謝して九禮を捧ぐることを辭せざるべし。
抑々(そも/\)昔時の著述家即ち作者が、其一篇の趣向と文章に苦心したるの状態は實に筆紙の能く盡す所にあらず、慘澹と云はんより寧ろ決死の覺悟を以て従事したるの形跡瞭々たるを見るなり。蓋(けだ)し現代の小説か若くは著作家が惰慢終(つひ)に湯薪の資に窮し、下宿屋の二階に午睡纔醒(ざんせい)の餘暇を以て淺薄の思想に筆を驅り、原稿一頁の價を爭ふか、又は過譽虚名の學者が賣文一時の榮華に乘じて、夏は署を涼風涼泉の地に避け、冬は寒を硝窓煖爐の間に遯(のが)れ、放辟酒婦に戯むるゝの傍ら、一氣徒らに筆馬に鞭(むちう)って成る所の文章と、日を同じうして論ずべきものに非ざるなり。古(いにしへ)の作者は勞を忘れ、貧を忘れ、病を忘れ、終(つひ)に死生の境界を忘失して精神を其の著作に傾注し、一に其の成就する所の作篇を以て生命として蹇々(けん/\)倦まざるを見るなり。
余曾(かつ)て巣林子(さうりんし)近松の桃山祠畔著作堂を圖を見るに、方二間許りの草廬(さうろ)にして四方壁を塗り、其の一方に三尺許りの入口あり、他の一方に三尺角許りの窓あり、此の前に机を置き、傍らに火鉢及手燭附け木等を置き、他の四壁は悉く書棚にして和漢の參考書を堆積し、殆んど暗室同樣の裡に棲坐(せいざ)し、一たび此中(このうち)に入る時は直ちに虚淡の境界に入り、心中一の衛生なく、生死なく、只だ人情纏綿の空想に耽りて心思微動の煩念なし、門人の食を搬するや窃(ひそか)に入口に挿入して、■(※しば=しかばねに「婁」)々(しばしば)其食了したるや否やを窺ふのみなりと。此(かく)の如くして趣向を練り、句調を敲いて勞苦と老來とを知らず、一身の全部頓(とみ)に著述娯樂の花園に■(※しょう=ぎょうにんべんに「尚」)■(※よう=ぎょうにんべんに「羊」)して心念又た古今に來往し、事蹟作例に窮すれば燭を點じて四壁の參考書を獵り、妙趣堂に充ち、奇興心身を襲ふに至りて一篇の文章を成すと。嗚呼宜(むべ)なる哉、其の著述の後世に亘りて、至大至強の感化を人心に致し、其同文同篇は喩へ千百回之を反讀するも尚(な)ほ厭(あ)く事なきの状を見るや。而して彼れ巣林子(さうりんし)は其の門生に箴して曰く、主旨は卑近を貴び、趣向は紛纏(ふんてん)を要し、句調は平易を可とすと。此の三つのものは彼れが百世の人心を驚倒して高歌低唱、今尚(な)ほ措く能はず、終(つひ)に風俗を搖撼(えうかん)するに至るの秘奧たるや、更に疑を容れざるなり。
又た彼の簑笠漁翁(さりうぎょおう)瀧澤馬琴の如き、一代の著作多くは唐誕に因る。其の博識廣聞は彼れが天資の強記と剛根とによって、描出したる戯作なりと雖ども、其の苦心慘澹より産出したるの興味は、忽焉として紙表に踴躍(ゆうやく)するあり。所謂人心を搖撼(えうかん)し風俗を變易するもの、此(こゝ)に於て存するを知る。而して彼れが著作中の一大篇たる「南総里見八犬傳」は殆んど絶筆にして、其の自白する處、實に惨澹にして又快なるを覺ゆ。彼れは天保四年癸巳の初秋輕微なる眼底炎に罹れり。爾後天保十年己亥までは七年間醫を求め、療を加ふるの暇なく不撓不屈、此の稿の満尾(まんび)せしむるに於て死尚(な)ほ辭せざるの決意あり。其の十八罫の稿本を十四罫となし、十罫となし、終(つい)に七罫となし、五罫となして、恰も兒童の清書大になすも尚(な)ほ其の稿を止めず、終(つい)に翌年十六年庚子の春に至りて失明闇黒となれり。彼れ若し普通常科の人たらば、茲(こゝ)に至りて筆を投じて止むべきに、由来東洋不世出の文豪矣爲(なんす)れぞ箇般(こはん)の災禍を以て其の精神を搖がすべき、益々胸憶の興趣を奮うて終(つい)に其の可憐の孫娘を捕へ來り、一字一句、若くは一事一例をも苟(いやしく)もせず、古籍舊典を代讀せしめ、隨って代寫せしめ、孳々焉(じゝえん)として倦まず、終(つい)に其の起稿より二十八年目、萬延元年庚辰の歳を以て満尾(まんび)脱稿するに至れりと。其勁勇巨膽(けいゆうきょたん)復(ま)た何を以てか之れに比せんや。即ち此れ等著述家の眼中には素より寒暑なく、飢渇なく、疾病なく、衛生なく、死生なきや論を俟たざるなり。彼の並木宗輔が「嫩軍記(ふたはぐんき)」を著すに、須磨の苫屋に寝(い)ねて漁夫に撻(むちう)たれ、三好松洛が「襤褸錦(つゞれのにしき)を著すに辻堂に起臥して乞食(こつじき)と誤られたるも、亦た其一例たるを知るべし。果して然らば余が現代の著述家に向って窃かに淺薄と云ひ惰慢と叫ぶも、敢て無禮の罵言に非ざるを信ずるなり。若し其(それ)著書にして坐(そゞ)ろに再讀に値し、誠實なる感化を社會に與ふるに足るものあらば、余は直に甲(かぶと)を其門下に脱し、謝して九禮を捧ぐることを辭せざるべし。
六、著名の外題二三を記す
余は此の好機に乘じて以下當時の狂言作者が著述したる義太夫節の中にて世間の間に馴れたる外題丈けを二三掲出せんと欲するなり。
○おさん茂兵衛「大經師昔暦」正徳五年乙未の春近松門左衛門作
○「心中天網島」享保五年庚子十二月近松門左衛門作
○「心中宵庚申」同七年寅四月近松門左衛門作
○「壇浦兜軍記」同十七年子九月文耕堂長谷川千四作
○「蘆屋道満大内鑑」同十九年壬寅十月竹田出雲作此時より與勘平の人形の腹のふくるゝ樣に作り、操人形は三人掛りとなる、夫までは一人遣ひなりしと。
○「敵討襤褸錦(かたきうちつゞれのにしき)」元文元年丙辰五月文耕堂、三好松洛作
○「御所櫻堀川夜討」元文二年丁巳正月文耕堂、三好松洛作
○「ひらがな盛衰記」同四年己未四月文耕堂、千前軒(此時吉田文三郎梅ヶ枝の人形に長さし金と云ふ事を始む、後(の)ち菅原傳授の千代などにも遣ふなり)
○「新薄雪物語」寛保元年辛酉五月文耕堂、三好松洛、小川半平、竹田小出雲作
○「夏祭浪花鑑」延享二年乙丑七月並木千柳、竹田小出雲、三好松洛作世話物九段續きは是より始り又三代目吉田文三郎工夫して長町の段にて人形に水を掛ける事を思い付たり
○「楠昔話」同三年丙寅正月竹田小出雲、並木千柳、三好松洛作、人形吉田文三郎、山本伊平次出遣ひ
○「菅原傳授手習鑑」同三年丙寅八月竹田出雲、並木千柳作
○「義經千本櫻」同四年丁卯十一月、竹田出雲、並木千柳、三好松洛作、吉田文三郎の工夫にて忠信に源氏車の廣袖を著(き)せる事を初む
○「假名手本忠臣藏」寛延元年戊辰八月竹田出雲、三好松洛、並木千柳作實に古今の大入なり
○「双蝶々曲輪日記」同二年己巳七月竹田出雲、三好松洛、並木千柳作此の芝居にて鶴澤友二郎死す
○「源平布引瀧」同二年己巳十一月並木千柳、三好松洛作此芝居にて上總太夫死す
○「戀女房染分手綱」寶暦元年辛未二月三好松洛、吉田冠子作
○「奧州安達原」寶暦十二年壬午九月竹田和泉、近松半二、北窓後一、竹本三郎兵衛作、翌癸未正月、竹田座類燒に付竹本座へ加はる
○「本朝廿四孝」明和三年丙戌正月三好松洛、竹本三郎兵衛作
○「太平記忠臣講釋」同年十月近松半二、竹本三郎兵衛作
○「傾城阿波の鳴門」同五年戊子六月近松半二、竹本三郎兵衛作
○お染久松「新版歌祭文」安永九年庚子九月近松半二作
以上竹本座外題中の大略拔書きなり
○「刈萱桑門筑紫■(※車偏に「榮」)(かるかやどうしんつくしのいへづと)」享保二十年乙卯八月並木宗輔、同丈助作、駒太夫始めて出座(播磨屋彌三郎事)
○「玉藻前曦袂(たまものまえあさひのたもと)」寶暦元年辛未正月橘平、一鳥、蛙桂(あけい)作
○「祇園祭禮信仰記」寶暦七年丁丑十二月應律、黒藏主(くろぞうす)、三津飲子、一鳥作
○「岸姫松轡鑑」同十二年壬午四月應律、笛躬(てききう)、一鳥作、八重太夫出席(泉屋平兵衛事)
○茜屋半七みのや三勝「艷容女舞衣(あですがたおんなまひぎぬ)」安永元年壬辰十二月豐竹定吉座三郎兵衛、應律、平七作
右豐竹座外題中の大略拔書なり。
以上列記の外題の外數座に亘り凡(およそ)二百餘年間數百千の書下し外題あり、此等は皆(み)な國家の治亂興廢に關せず、幾百年間間斷なく日夜の間に演唱せられ、又幾千百人の藝人に幾千萬回演奏せられたるやは殆んど想計する能はざるなり。然らば則(すなわち)厭(あ)かれざるは興味あるが爲めなり。興味あるは感化せらるるの本(もと)たり。感化せられて初めて風俗に變易を生ず。又た以て止むを得ざるの順序に屬するを知るべし。
七、藝人の苦心
義太夫節は幸運によりて名人と學者との好遇を得たるがため、世人に絶大の歡迎を受けて偉大なる功力を百世の後に遺したるは他の藝術の永く欽羨(きんせん)に耐へざるところたり。而して往昔此の音曲を演ずる名人は播磨掾、越前掾、政太夫、大和掾、筑前掾、住太夫等雲の如く起り、潮の如く湧き、各々其の技藝を練磨せしが、其の苦心の梗概は彼の淨瑠璃古咄集によるも瞭々たるものあるなり。其の後寛政、享和、文化、文政の頃を中心として一事藝界を驚倒せしめたる一人は大阪船場の商人義太夫節にては素人の所謂旦那衆たりし鍋屋宗左衛門と云ふ人、多年此の音曲の妙味深奧を研鑚し、斯道藝人の段々俗調に流るるを歎き、又た豐竹座の衰微廢滅に歸せんとするを慷慨し、終(つい)に豐竹駒太夫の門人として豐竹麓太夫と名乘り打って出(い)でしより、滿天下の藝界を振蕩(しんとう)し、其の藝人と素人の別なく、老幼婦女より出家、侍、町人、百姓に至るまで此の麓太夫の語り場を聞かんと、四方より堵(と)の如く豐竹座に群集したり。爾後麓太夫が語りたる外題多く、彼の繪本太功記(えほんたいこうき)尼ヶ崎の段、蝶花形八ツ目挾間合戦の七册目八陣の八ツ目の如き皆此麓太夫の語りたる場なりしなり。
此故に此の太夫の語りたる場を麓場と稱(とな)へて藝界一種の風格を殘し、百年の後此の藝風を追うて修行研鑚を加ふるもの、其幾千萬なるを知らざれども、一人も其堂奧(どうおう)を伺ひ得る者なく、比々頻々として團子を杓子で掻き廻す如き調節にて怒鳴り散すことになり居れり。而して此の麓太夫が研鑚の状態は如何、抑々義太夫節の世に歡迎せられたるは、他の藝風と違ひ、大聲、強喉、譜節、整然、之れに加ふるに詞(ことば)と色と、間と足取と、音(おん)遣ひと云ふやうのものありて各種人情の變化状態を語り出(いだ)すもの故、如何なる無智文盲の人にも其語味と情愛とを會得せしめ得るが特徴にて、他の音節諸藝は所謂座敷藝にて數百人若しくは數千萬人の群集の大芝居にて其語味と情愛とを明瞭に聞取る事能はざるの時に當り、元祖義太夫が天性の大聲美音なるを資(もと)として、之を芝居に掛けて興行し以て已(※ママ)が藝風を社會に徹底せしめたるより、麓太夫は深く此本義を尊祟(そんそう)し、第一詞に於ける人情の變化を考へ隨って詞を云はんとする前にある色と云ふ音節の語り方を研究し、而して初めて詞(ことば)と地合(ぢあひ)と云ふ總ての譜節も明白に優美に上品に高尚に攻修(かうしう)し翕々(きふ/\)然として順舒(じゅんじょ)ある語り振りを旨としたるより巍然(ぎぜん)として一藝の風儀を一變したるなり。夫れ茲(ここ)に至る迄の麓太夫の苦心は敢て尋常藝人の窺ひ知り得べき處に非ざるなり。彼の荏土(えど)藝遊記に曰く、寛政元年二月(麓太夫が狹間合戦の七册目を語る頃)根岸伏戸町都一賀師匠は浪華の鍋屋大人に招かれて京都の藤澤■(※けん=手偏に「僉」)校と共に一中節深草の節付けを調べて翌年正月に荏土(えど)に歸り夫(それ)より此節廻し一入(ひとしほ)流行せり云々とあるにても如何に麓太夫が音節の譜調に討究苦心せしかを知るべし。時恰も太平の世にして貴人(きにん)富客(ふかく)の遊藝に心を傾くる者多しと雖も此悲風悽慘を基礎として著述したる義太夫節の改良に精苦を盡したるは、敢て常人の企て及ぶべき處に非ざるなり。宜(むべ)なる哉、其藝百年の後尚(な)ほ上下(しょうか)の人心に偉大の感化を與へて止まざることや。而して麓太夫が此仰鑚(かうさん)を盡して藝風の腐敗を防止したるは一は藝祖の高風を懷(おも)ひ一は當時藝人の頽勢を悲み其阿世(あせい)迎合(げいがふ)操行(さうかう)日に下落して昔時の遺風だもなきを慨嘆したるより出でたることは其藝風の遺傳に見るも明かなる事實たるを知るなり。彼の所謂麓場なるものの音(おん)遣ひは頗る高尚優美にして殊にギン(※原著には「ギン」に傍点あり)の譜に對する音(おん)遣ひは妙味津々として盡くることなく、其のギン(※原著には「ギン」に傍点あり)のツボ((※原著には「ツボ」に傍点あり)をニジリたる處より音(おん)を發して、何處までも下劣なる音調に落ちざるは、恰も丹頂の鶴九霄に舞うて下界の塵に交はらざると一般、如何なる田夫野人も覺えず襟を正して其調節を玩味するに至る。今や世界の政治經濟論を外にして只藝界の一路のみを一瞥する時は昭代長(とこし)へに風清く山静かにして萬樹枝を鳴さず太平の餘慶巷衢(かうく)に滿ちて民間の諸藝實に非常の進歩をなすの時に當り、此義太夫節のみ荐(しき)りに其品位を失墜し此等(これら)麓場等の音調を眞正に玩味して演奏する者將さに絶滅せんとするは藝界の爲め實に惆悵(ちうちゃう)の念に耐へざるなり。唯だ過去僅かに雲間の一星とも云ふべき故竹本攝津大掾(せっつだいじゃう)の如きは毅然として斯道の明暗を司どり烱々(けいけい)の光輝を發したるあるのみ。余はいよ/\本論を進めて斯道將來の消長を卜定(ぼくてい)せんと欲するなり。
此故に此の太夫の語りたる場を麓場と稱(とな)へて藝界一種の風格を殘し、百年の後此の藝風を追うて修行研鑚を加ふるもの、其幾千萬なるを知らざれども、一人も其堂奧(どうおう)を伺ひ得る者なく、比々頻々として團子を杓子で掻き廻す如き調節にて怒鳴り散すことになり居れり。而して此の麓太夫が研鑚の状態は如何、抑々義太夫節の世に歡迎せられたるは、他の藝風と違ひ、大聲、強喉、譜節、整然、之れに加ふるに詞(ことば)と色と、間と足取と、音(おん)遣ひと云ふやうのものありて各種人情の變化状態を語り出(いだ)すもの故、如何なる無智文盲の人にも其語味と情愛とを會得せしめ得るが特徴にて、他の音節諸藝は所謂座敷藝にて數百人若しくは數千萬人の群集の大芝居にて其語味と情愛とを明瞭に聞取る事能はざるの時に當り、元祖義太夫が天性の大聲美音なるを資(もと)として、之を芝居に掛けて興行し以て已(※ママ)が藝風を社會に徹底せしめたるより、麓太夫は深く此本義を尊祟(そんそう)し、第一詞に於ける人情の變化を考へ隨って詞を云はんとする前にある色と云ふ音節の語り方を研究し、而して初めて詞(ことば)と地合(ぢあひ)と云ふ總ての譜節も明白に優美に上品に高尚に攻修(かうしう)し翕々(きふ/\)然として順舒(じゅんじょ)ある語り振りを旨としたるより巍然(ぎぜん)として一藝の風儀を一變したるなり。夫れ茲(ここ)に至る迄の麓太夫の苦心は敢て尋常藝人の窺ひ知り得べき處に非ざるなり。彼の荏土(えど)藝遊記に曰く、寛政元年二月(麓太夫が狹間合戦の七册目を語る頃)根岸伏戸町都一賀師匠は浪華の鍋屋大人に招かれて京都の藤澤■(※けん=手偏に「僉」)校と共に一中節深草の節付けを調べて翌年正月に荏土(えど)に歸り夫(それ)より此節廻し一入(ひとしほ)流行せり云々とあるにても如何に麓太夫が音節の譜調に討究苦心せしかを知るべし。時恰も太平の世にして貴人(きにん)富客(ふかく)の遊藝に心を傾くる者多しと雖も此悲風悽慘を基礎として著述したる義太夫節の改良に精苦を盡したるは、敢て常人の企て及ぶべき處に非ざるなり。宜(むべ)なる哉、其藝百年の後尚(な)ほ上下(しょうか)の人心に偉大の感化を與へて止まざることや。而して麓太夫が此仰鑚(かうさん)を盡して藝風の腐敗を防止したるは一は藝祖の高風を懷(おも)ひ一は當時藝人の頽勢を悲み其阿世(あせい)迎合(げいがふ)操行(さうかう)日に下落して昔時の遺風だもなきを慨嘆したるより出でたることは其藝風の遺傳に見るも明かなる事實たるを知るなり。彼の所謂麓場なるものの音(おん)遣ひは頗る高尚優美にして殊にギン(※原著には「ギン」に傍点あり)の譜に對する音(おん)遣ひは妙味津々として盡くることなく、其のギン(※原著には「ギン」に傍点あり)のツボ((※原著には「ツボ」に傍点あり)をニジリたる處より音(おん)を發して、何處までも下劣なる音調に落ちざるは、恰も丹頂の鶴九霄に舞うて下界の塵に交はらざると一般、如何なる田夫野人も覺えず襟を正して其調節を玩味するに至る。今や世界の政治經濟論を外にして只藝界の一路のみを一瞥する時は昭代長(とこし)へに風清く山静かにして萬樹枝を鳴さず太平の餘慶巷衢(かうく)に滿ちて民間の諸藝實に非常の進歩をなすの時に當り、此義太夫節のみ荐(しき)りに其品位を失墜し此等(これら)麓場等の音調を眞正に玩味して演奏する者將さに絶滅せんとするは藝界の爲め實に惆悵(ちうちゃう)の念に耐へざるなり。唯だ過去僅かに雲間の一星とも云ふべき故竹本攝津大掾(せっつだいじゃう)の如きは毅然として斯道の明暗を司どり烱々(けいけい)の光輝を發したるあるのみ。余はいよ/\本論を進めて斯道將來の消長を卜定(ぼくてい)せんと欲するなり。
八、豐竹座の再興竝(ならびに)麓太夫の藝風
蒸暑の盛んなる三旬ならずして涼味忽ち秋郊に生じ、黄丹坐(そぞ)ろに樹抄を染めて、落葉觀(み)す/\地上に委す、騒人一朝の霜に驚駭して詩思未だ熟せざるに、氷雪遽然として軒に迫る。此れ一年無常盛衰の状態にして、古今實に其揆(き)を一にす。人間界裡百般の榮枯も亦た正さに之れに齊しきものあるを知るなり。貞享、元祿の間一時絶大の旺盛を極めたる義太夫節も藝界進歩の華たる俳優演劇の爲めに其光彩を奪はれ、終(つひ)に明治大正の頃より其技藝の精神に惰慢の脈を通じ、次第に藝科の妙趣に離れて修養甚だ正しからず、情縺れ気殘(こ)ねて卑譜斯界に普(あま)ねく、俗調巷衢(かうく)に滋(しげ)し。是を思ふ時昔日、彼の藝雄麓太夫の如きありて、慨然として斯道の頽敗を嘆き、彼の尚■(※けい=糸偏に「冏」)(しゃうけい)を拂うて錦衣を顯はすが如く、其の研鑚の妙技を提(ひっさ)げて藝界の腐敗を防止し、恰も疾風の砂を捲くが如くに、懸崖に石を轉ずるが如く、積日の衰運を一時に挽回して沒日を中天に回(かへ)すの慨あらしめしは、其快果して如何ぞや。彼の明和七年十一月に於て、「北條時頼記」を座祖豐竹越前少掾(えちぜんせうじゃう)の七回忌に遺子豐竹和歌三を座元となし、麓太夫自ら鉢木(はちのき)の場を出語りにて勤めたるが爲め、茲(ここ)に愈々(いよ/\)豐竹座藝風の礎石を勁硬(けいかう)ならしむることを得たりと。而して此一段に於ける麓太夫の苦膽焦慮は後風下流の藝人等が敢て其一端をも窺ふ能はざるものにして、時恰も徳川泰平の餘澤に狃(な)れ、政綱弛緩、士氣腐爛、士人の華奢婉麗は亡國亡身の讖(しん)をなし、民衆の鼓腹撃壤(こふくげきじょう)は癈倫乖義(はいりんくわいぎ)の聲に均しきの時、彼れ麓太夫が怒氣虹の如く、五百年前の古武士佐野常世を捕へ來りて、末世墮落の淵に沈淪(ちんりん)せんとする士心を警声せんとする、其の企圖の雄健なる、豈(あ)に一の豐竹座再興の籌計(ちうけい)として見る可(べ)けんや。所謂治に居て亂を忘れざる、日本固有の元氣を其汚溺に救はんとするや、更に疑を容れざるなり。之れに加ふるに其技藝の鍛錬に費す處の苦困果して如何ぞや。古老の咄に曰く「麓太夫殿の鉢木(はちのき)の段は高尚にして優美に氣健やかにして情深し、此(こ)は京都の能太夫金剛伊織殿を招いて日夜工夫稽古を勵み、又三味線の某(それがし)殿は七日七夜の斷食稽古を爲し、興行三日目舞臺にて血を吐かれたり」と云ふを以て見るも、其決心の如何に勇壯なりしかを見るべし。余が曾(かつ)て一藝の奧を極めて世に感化を與へんとする者は、敢て死を顧みずと云ふの正に過言にあらざるを知るべし。而して此の興行の當時、社會に及ぼしたるの效果は實に尠少(せんせう)にあらざるなり。又曰く、「麓太夫殿の時頼記の開場せらるゝや、京大阪詰合ひの諸藩侍衆は、多くは二度三度も聞きて皆々感心し、何(いず)れも其重役の許しを受けて、態々(わざ/\)京都邊より宿屋付にて聞きにわせられたり。時の御奉行樣より麓太夫殿に任官の事を勸めらるゝも、私は麓と申(まうす)低き名前が相當でござりますと、只管(ひたすら)に御斷り申上げられたり、云々」にても、其麓太夫が精神の如何に功名に淡く濟世に急なりしかを窺ふを得べし。嗚呼世遠く人亡び、教へ弛まり、修養正しからざるの時に當り、身を封建の制下に委したる干城の武士にあり乍(なが)ら、治者は士心の搖亂を恐れて、制度を忘れ、士風日に月に惰弱にして、痴道に陥るを救はず、苟且偸安(かうしょとうあん)一日を姑息するを以て偉功勳績となし、被治者は人慾の放縱(ほうしょう)に耽溺して、君國の大事を忘れ、偶々閭巷(りょかう)一藝兒の演技に警醒せられて、青天の霹靂かと疑ひ、農工の愚民と感を同じうして、歔欷泣涕(きょききうてい)の醜をなす。宜(うべ)なる哉徳川封建の瓦崩するに當りて、士氣の却て土民に劣れるものあるや。而して其義太夫節の教義は、深く下民の脳官に浸潤して、萬世不滅の大和國魂を凝成し、國難に攫(かゝ)るゝ毎に、鏘鏗(しゃうかう)金石の聲を發するを見る。爾後豐竹座の勢運日に月に隆盛に赴き、麓太夫の名聲天下に磅■(※ばく=石偏に「薄」)(はうばく)するに至れり。而して一方彼の竹本座にて其礎石とも云ふべき、老功無比の一員たる竹本政太夫(まさだいふ)の藝風は更らに一改進を加へ、人氣滿都に横溢して恰も錦上花を散らすの概ありて、藝界炬火翁の偉跡照々として萬世に滅せざるを識るなり。是(ここ)に於て余は尚本論を進めて孤舟(こしう)藝界の波浪に漂漾(へうやう)し、其奇勝妙寶を探りて獨り逸興(いつきゃう)を縱(ほしい)まゝにせんと欲するなり。
九、現下義太夫の墮落(結論)
余は聊か茲に淨瑠璃の始元より、義太夫節の事歴に對して其粗漫を略述し、之れに加ふるに菲薄(ひはく)なる余の査察と私見とを附加して、茲に第九回を以て其の論稿を終らんと欲す。夫れ明和以後安永、天明、寛政、享和、文化、文政、天保より、昭和の今日に至るの間、決して斯道の名人無きに非らざるも、其の存する處の語り本、或(あるひ)は諸書によりて覈閲(かくえつ)を試みるに、盡く古人の書下し古人の語り方を研鑚する事薄く、未だ人情の變化語氣の動靜人格の品位等を腹中に構へて、音聲(おんじゃう)の舒破急(※原典には「舒破急」に傍点あり)を練磨するもの尠(すく)なく、甲は詞(※原典には「詞」に傍点あり)巧みに語れども地合(※原典には「地合」に傍点あり)に生氣なく、乙は地合を優美に語れども詞に氣合なく、丙は詞、地合とも音(おん)遣ひ流暢なれども、間、抜け、息、悪く情合切實ならざるが如き輩簇出(ぞくしゅつ)して、聊(いささ)か以て斯道の全豹(ぜんべう)を盡して、藝命を生動せしむるに足るの藝人多からざるは、寔(まこと)に慨嘆に耐へざるのことに屬す。蓋し天下百般の音曲中にて天資の惡聲を以て、日本一の名人たるの藝妙を究め得らるゝものは、義太夫節と謡曲の外決して非ざるを知る。彼の江戸の立て藝とも云ふべき、長唄、富本、常磐津、清元の如き音曲は、若し美音ならずして惡聲なりせば、始めより其門に臨む能はざるのみならず、其の閾(しきゐ)だも越ゆる能はざるの藝術なり。又何人も之れに造詣するの意を起さゞるなり。義太夫節は其の筋簡易にして常に此の藝奧に入るの道を闡(ひら)いて、後世の藝學を迎ふると雖も、輙(たやす)く其の妙處に到る能はざるは、蓋し其の修行の疎漫と柔弱とに胚胎せずんばあらず。即ち他藝に比して其の修行の困難なる實に顕著なるものありて存するなり。
今余の識見を以て、修行の困難なるの實例を檢擧せんと欲せば、敢て一片論文の能く盡す所にあらず、故に試(こころみ)に一例を以てせんに、總て藝道に下手の多きは其修行の困難を代表するものたらざるはなし。彼の謡曲、圍碁、一中節、義太夫節の如き其下手の多きこと實に此れが計數の道なきに苦しまんとす。而して此の各藝大下手連の大軍は、彼の蚊蠅(ぶんよう)の夫れの如く、世人が少し油斷のあるに乘じて吶喊邁往(とっかんまいわう)、天狗の鼻を振り蠢かして強制の喝采を迫り赤恥の千萬を陳列して贄資(しし)のみを貪らんとす、危險何ぞ是より太(はなは)だしきものあらんや。夫れ道は入り易うして達する事難し。彼の禪家の所謂「雲去りて青山近く、道易うして且つ行く難し」と一般、此の下手は入り易きに發起して、行いて迷悟の界に彷徨し、一悟三迷終(つひ)に修行の道途を紛亂し、一念不覺の界に墮落して荐(しき)りに不可思議の狂音を亂發し、不衛生なる■(※うん=きがまえ(气)+「囚」の下に「皿」)氣(うんき)を釀成し、遂に社會を暗黒の界と成し去らずんば止まざらんと欲するに似たり。此時に當りて彼の老雄故竹本攝津大掾の如き巍々焉(ぎゞえん)として斯道の大綱に踞し、我れ生存中は決して斯道の範制に瑕疵(かひ)を留むるを許さずと、叮嚀琢蹉(たくさ)其討究を怠らざるの結果、八十餘歳の高齡まで燦たる藝彩を把持して失はざりし爲め、今日まで僅かに斯道の壘砦を留むるを得たり。攝津大掾は既に其高齡に加ふるに聾鼻喘胃(ろうびぜんい)の諸疾患を有しながら老いて益々矍鑠(くわくしゃく)、而して尚ほ研鑚修行の酷苦を繼續して止まざりしに至りては、彼(かの)馬琴翁の如く其藝術の深奧なる唯だ驚嘆の他なきを知るなり。
余弱冠より諸藝の科學的研究を好み、彼の故攝津大掾が越路太夫頃よりの演藝を聴くこゝに殆んど三十有餘年、(明治十四年より大正二年頃迄)倩々(つら/\)彼れが研鑚の跡を回顧すれば航程渺茫として煙の如きも、宛(えん)として波瀾澎湃の間明媚の風光を來往したるの跡を見るなり。余は去る明治の昭代に於いて、危く義太夫節の綱紀を把持したるの勳績は、故豐澤團平(此の絃師團平と攝津大掾との論評は他日更に發稿する所あらんとす)と攝津大掾とのみに歸せずんばあらざるなり。嗚呼義太夫節の盛衰も亦晩秋の天の如く、晴曇常なく風雨時によらず、過去の旺盛は一時の夢にして、僅かに攝津大掾一人にして此の頽勢を支へ來りしは、彼(か)の所謂管中微(なか)りせば髪を被(かう)ぶり袵(じん)を左にせんと云ふの責め、一に攝津大掾の雙肩に懸在せしを見るなり。當時に於ける大掾たるものゝ任荳(あ)に輕からずと云ふ可(べ)けん哉。
夫(それ)然り而して義太夫節の策源地たる大阪にして唯だ一の攝津大掾有るのみなりしが、殊に京阪現在の斯界は實に満野草茫として狐兎走るの有樣にして、只だ無茶苦茶の藝人のみが陸梁跋扈(りくりゃうばっこ)して斯界を暗黒にし去らんとするの傾向あるを見るなり。且つ夫れ斯界に於て斯道藝人を蔑如(べつじょ)することの斯く絶甚(ぜつじん)なる所以は、要するに精勵の如何より打算することにして、權威なく鍛錬なきが故に其の修行が未熟となり、止むを得ず徒らに阿諛迎合只だ聽客に媚びるを以て本旨とするに原因せずんばあらざるなり。更らに余を以て之れを觀れば斯(かゝ)る藝人に對して是非の批評を下すは未だ義太夫節の何物たるを知らざる者のことに屬す。如何となれば義太夫節の修行は恰も武士の武術を修行するに酷似せり。其滿身力の應用其氣合の鍛錬、其息、間等の研究實に寸毫の間隙、油斷を許さゞるの藝術たり。故に此修行は彼の惰慢放縱兒の敢て一音節だも窺ひ知り得べきの事にあらざるなり。即ち彼等は古作の名文に節を附けて讀むと一般なり。語を換へて之を云へば、此名文を浪花節に讀むも人は感ずべく、又祭文節にするも人は聞くべし。不幸にして義太夫節にして之を讀むが故に、人は義太夫節かと思うて之を聞くなり。夫れ武道に均しき修行をなし其爲す處の演藝は、即ち人を斬るの演藝なり。所謂絃師と眞劍の勝負を爲すなり。此故に互に一丈三尺の腹帶を締めて、無我の觀念を定めて演臺に上り、始より雙方の息と隙とを相窺ひ、競技上に於て死生を決せんとす。故に其一方に於いて秋毫の隙あるも、直ちに流血淋漓に均しき大怪我を爲すなり。
現代の藝人は之に反し彼の俳優の弄ぶ刀の如く、竹篦に銀箔を塗り、呼吸を捨てゝ其手續を演じ、斯く打たば斯く受けよ、斯く突かば斯く外せよと、恰も兒戲童踊に等しきことを連續する内に、一種の息呼吸の物眞似をなす。其息呼吸の醜陋(しうろう)なる、尚ほ大道藝人の事に均しきを見る。如何となれば太夫と絃師と二人の仕事なればこそ、幼少より息、間の修行を要するなり。其の呼吸の合ふと合はざるは此の修行の大問題なり。然るに現在の演藝を見るに角力士(すまうとり)が土俵の上で何か不都合な相談をして角力を取っているやうな感を免かるゝ能はざるなり。何ぞ其の巧拙を論ずるの價値あらんや。嗚呼悲しい哉。昔日藝祖の此道を剏(はじ)むるや、畏れ多くも之れを宮中に演奏し、延(ひ)いて人心の教義に資し、以て世道に偉大の裨益(ひえき)を遺したるの藝格を、現代は惰慢放恣の修行に委して、終(つひ)に泥土の中に滅盡(めつじん)せしめんとす。
彼の能楽の旺盛なるや、政府之れを武家式樂の班に加へて修養せしめしに、後世に至りて墮落武士が破笠(はりう)裂扇(れっせん)を敲いて市井に食を乞ふの資となす。義太夫節の末路正に之れに宛如(えんじょ)たるものあるを見るなり。古語に曰く禮樂興らずんば道蒼生に至らずと。古(いにしへ)の樂は高尚悠遠なり。今の樂は近易切實なり。吾國(わがくに)は貞享以後此の近易切實の音樂によりて大功を奏し以て此の蒼生の感化を支配せり。今や此の樂の滅盡(めつじん)正さに目睫に迫らんとす。夫れ又た何物の樂か更らに將來の感化を司令せんとするや。落日悠々として秋復(ま)た老い、遠天際(かぎ)り無(の)うして鳥空しく飛ぶ。聊か義太夫論を草して所思を述ぶると云爾(しかいふ)。
今余の識見を以て、修行の困難なるの實例を檢擧せんと欲せば、敢て一片論文の能く盡す所にあらず、故に試(こころみ)に一例を以てせんに、總て藝道に下手の多きは其修行の困難を代表するものたらざるはなし。彼の謡曲、圍碁、一中節、義太夫節の如き其下手の多きこと實に此れが計數の道なきに苦しまんとす。而して此の各藝大下手連の大軍は、彼の蚊蠅(ぶんよう)の夫れの如く、世人が少し油斷のあるに乘じて吶喊邁往(とっかんまいわう)、天狗の鼻を振り蠢かして強制の喝采を迫り赤恥の千萬を陳列して贄資(しし)のみを貪らんとす、危險何ぞ是より太(はなは)だしきものあらんや。夫れ道は入り易うして達する事難し。彼の禪家の所謂「雲去りて青山近く、道易うして且つ行く難し」と一般、此の下手は入り易きに發起して、行いて迷悟の界に彷徨し、一悟三迷終(つひ)に修行の道途を紛亂し、一念不覺の界に墮落して荐(しき)りに不可思議の狂音を亂發し、不衛生なる■(※うん=きがまえ(气)+「囚」の下に「皿」)氣(うんき)を釀成し、遂に社會を暗黒の界と成し去らずんば止まざらんと欲するに似たり。此時に當りて彼の老雄故竹本攝津大掾の如き巍々焉(ぎゞえん)として斯道の大綱に踞し、我れ生存中は決して斯道の範制に瑕疵(かひ)を留むるを許さずと、叮嚀琢蹉(たくさ)其討究を怠らざるの結果、八十餘歳の高齡まで燦たる藝彩を把持して失はざりし爲め、今日まで僅かに斯道の壘砦を留むるを得たり。攝津大掾は既に其高齡に加ふるに聾鼻喘胃(ろうびぜんい)の諸疾患を有しながら老いて益々矍鑠(くわくしゃく)、而して尚ほ研鑚修行の酷苦を繼續して止まざりしに至りては、彼(かの)馬琴翁の如く其藝術の深奧なる唯だ驚嘆の他なきを知るなり。
余弱冠より諸藝の科學的研究を好み、彼の故攝津大掾が越路太夫頃よりの演藝を聴くこゝに殆んど三十有餘年、(明治十四年より大正二年頃迄)倩々(つら/\)彼れが研鑚の跡を回顧すれば航程渺茫として煙の如きも、宛(えん)として波瀾澎湃の間明媚の風光を來往したるの跡を見るなり。余は去る明治の昭代に於いて、危く義太夫節の綱紀を把持したるの勳績は、故豐澤團平(此の絃師團平と攝津大掾との論評は他日更に發稿する所あらんとす)と攝津大掾とのみに歸せずんばあらざるなり。嗚呼義太夫節の盛衰も亦晩秋の天の如く、晴曇常なく風雨時によらず、過去の旺盛は一時の夢にして、僅かに攝津大掾一人にして此の頽勢を支へ來りしは、彼(か)の所謂管中微(なか)りせば髪を被(かう)ぶり袵(じん)を左にせんと云ふの責め、一に攝津大掾の雙肩に懸在せしを見るなり。當時に於ける大掾たるものゝ任荳(あ)に輕からずと云ふ可(べ)けん哉。
夫(それ)然り而して義太夫節の策源地たる大阪にして唯だ一の攝津大掾有るのみなりしが、殊に京阪現在の斯界は實に満野草茫として狐兎走るの有樣にして、只だ無茶苦茶の藝人のみが陸梁跋扈(りくりゃうばっこ)して斯界を暗黒にし去らんとするの傾向あるを見るなり。且つ夫れ斯界に於て斯道藝人を蔑如(べつじょ)することの斯く絶甚(ぜつじん)なる所以は、要するに精勵の如何より打算することにして、權威なく鍛錬なきが故に其の修行が未熟となり、止むを得ず徒らに阿諛迎合只だ聽客に媚びるを以て本旨とするに原因せずんばあらざるなり。更らに余を以て之れを觀れば斯(かゝ)る藝人に對して是非の批評を下すは未だ義太夫節の何物たるを知らざる者のことに屬す。如何となれば義太夫節の修行は恰も武士の武術を修行するに酷似せり。其滿身力の應用其氣合の鍛錬、其息、間等の研究實に寸毫の間隙、油斷を許さゞるの藝術たり。故に此修行は彼の惰慢放縱兒の敢て一音節だも窺ひ知り得べきの事にあらざるなり。即ち彼等は古作の名文に節を附けて讀むと一般なり。語を換へて之を云へば、此名文を浪花節に讀むも人は感ずべく、又祭文節にするも人は聞くべし。不幸にして義太夫節にして之を讀むが故に、人は義太夫節かと思うて之を聞くなり。夫れ武道に均しき修行をなし其爲す處の演藝は、即ち人を斬るの演藝なり。所謂絃師と眞劍の勝負を爲すなり。此故に互に一丈三尺の腹帶を締めて、無我の觀念を定めて演臺に上り、始より雙方の息と隙とを相窺ひ、競技上に於て死生を決せんとす。故に其一方に於いて秋毫の隙あるも、直ちに流血淋漓に均しき大怪我を爲すなり。
現代の藝人は之に反し彼の俳優の弄ぶ刀の如く、竹篦に銀箔を塗り、呼吸を捨てゝ其手續を演じ、斯く打たば斯く受けよ、斯く突かば斯く外せよと、恰も兒戲童踊に等しきことを連續する内に、一種の息呼吸の物眞似をなす。其息呼吸の醜陋(しうろう)なる、尚ほ大道藝人の事に均しきを見る。如何となれば太夫と絃師と二人の仕事なればこそ、幼少より息、間の修行を要するなり。其の呼吸の合ふと合はざるは此の修行の大問題なり。然るに現在の演藝を見るに角力士(すまうとり)が土俵の上で何か不都合な相談をして角力を取っているやうな感を免かるゝ能はざるなり。何ぞ其の巧拙を論ずるの價値あらんや。嗚呼悲しい哉。昔日藝祖の此道を剏(はじ)むるや、畏れ多くも之れを宮中に演奏し、延(ひ)いて人心の教義に資し、以て世道に偉大の裨益(ひえき)を遺したるの藝格を、現代は惰慢放恣の修行に委して、終(つひ)に泥土の中に滅盡(めつじん)せしめんとす。
彼の能楽の旺盛なるや、政府之れを武家式樂の班に加へて修養せしめしに、後世に至りて墮落武士が破笠(はりう)裂扇(れっせん)を敲いて市井に食を乞ふの資となす。義太夫節の末路正に之れに宛如(えんじょ)たるものあるを見るなり。古語に曰く禮樂興らずんば道蒼生に至らずと。古(いにしへ)の樂は高尚悠遠なり。今の樂は近易切實なり。吾國(わがくに)は貞享以後此の近易切實の音樂によりて大功を奏し以て此の蒼生の感化を支配せり。今や此の樂の滅盡(めつじん)正さに目睫に迫らんとす。夫れ又た何物の樂か更らに將來の感化を司令せんとするや。落日悠々として秋復(ま)た老い、遠天際(かぎ)り無(の)うして鳥空しく飛ぶ。聊か義太夫論を草して所思を述ぶると云爾(しかいふ)。
(完)
【底本】
「義太夫論」杉山其日庵著・昭和九年・台華社発行
【註記】
○底本は総ルビであるが、入力にあたりルビは適宜省略した。
○漢字の使用については、JIS第2水準までの範囲において、底本に忠実に入力することとし、正字体を使用した。JIS第2水準に加えられていない正字体については、簡易体を使用した。
○仮名使いについては、底本に忠実に入力した。
○原典において、各行末に句読点が省略されていると判断できる箇所については、適宜句読点を付した。
Edited by Tomoyuki Sakaue.