|
科学哲学ニューズレター |
![]()
Newsletter No. 32, April 18, 2000
|
1. Book Review by Soshichi Uchii: Nagayasu Shimao, Faraday, Iwanami, March 2000 [Japanese] |
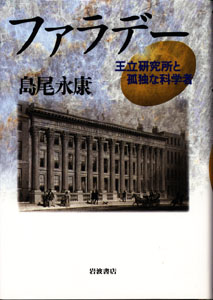 |
| 2. Our activities in 1999 | |
Editor: Soshichi Uchii
日本の科学史学界の長老のひとりと見なされる島尾氏のファラデー伝が出たことを知ったので早速購入して通読した。昨年度、わたしの特殊講義でもファラデーを取り上げ、このニューズレター25号(1999年5月)でファラデーの伝記について(英文の)紹介記事を書いたこともあり、わたしにとっては強い関心のある題材である。
まず、著者が本書で示そうとしたことを、著者自身の「あとがき」から引用しておきたい(211ページ)。
本書はファラデーの科学的業績に限定したファラデー伝ではない。ファラデーを中心に視野を広く取ったファラデー伝である。その設立の十三年目に入所して一生をすごした王立研究所の成立事情や改革の状況、その人を語らずしてファラデーを語れないデーヴィなどに、かなりの紙幅を費やした。またファラデーはこれまで純粋科学者としてのみみられてきたが、実は膨大な技術的業務をおこなっており、科学研究は私事だったことを述べる。またかれは小さな、厳格な宗派に属して、司祭なき宗派の司祭の役割をつとめたが、その信仰生活がかれの私生活と公的活動に、さらにはかれの科学にどのような影響を与えたかをみる。さらに、不明瞭な点は多いが、従来触れらることが少なかったファラデーの病気をも扱った。
こういったテーマが手慣れた筆で語られていき、「普通」のスタンダードによれば読みやすい好著になっていることは疑いがない。そのほか、筆者にとって参考になったのは、第7章「リサーチ・スクール」である。ほとんど独力で研究を進めたファラデーとは対照的に、有機化学のリービッヒを例として、研究室を単位として学生を養成し、グループでの研究の推進と専門家の養成とをおこなうリサーチ・スクールの伝統を作っていくドイツの事情が語られているのはきわめて興味深い。リービッヒはファラデーと親交があった。ファラデーとリービッヒの研究スタイルが対照的だというだけではなく、イギリスの王立研究所でリサーチ・スクールができたのが、ウィリアム・ヘンリー・ブラッグが王立研究所に着任した1923年以後になる(159ページ)、という点が驚きなのである。
ここまでは、好意的な感想を述べたのだが、以下ではこのたぐいの伝記、あるいは科学史の研究書として、本書に欠けているいくつかの条件について、少々苦情を言わせていただく。
まず、本書には巻末に文献表がつけられているものの、本文の中では、文献に言及する注も挿入文もほとんどないのが気にかかる。新書のたぐいでスペースが限られている場合はやむを得ず許容されるかもしれないが、資料による裏づけや、先行研究に対する言及やクレジットの必要な、科学史研究の本でこういう不備があるのは、控えめに言っても、困ったことである。著者は日本の科学史学界の長老なのだから、こういうところはきちんとお手本を見せてしかるべきであろう。
実は、本書を読み始めてすぐに気がかりになり始めたのは、先行研究に対する言及が、具体的には皆無に近いことであった。すでに引用したあとがきの部分をもう一度見ていただきたい。(1)王立研究所の成立や改革、(2)王立研究所におけるファラデーの技術的業務、(3)ファラデーの信仰生活のいずれについても、多くの先行研究があるはずである。わたし自身は科学史の専門家でもないし、ファラデーの研究家でもないが、(1)と(2)については、ファラデーの「学術的」伝記としては最初のものとされるピアース・ウィリアムズの本(Pearce Williams 1965)に対する言及もクレジットもないことにショックを受けた(文献表にあるのみ)。こういった、ファラデー研究では今や古典的と見なされる文献をふまえ、島尾氏の研究がどこまでを先行研究に負い、どれだけの発見を新たに付け加えたか、それをきちんと明らかにすることが、科学史家としての最低限の責務ではないだろうか。
これは、単なる一般論として言っているのではない。例えば、島尾氏が第8章「科学を語る」でファラデーの講演についての考えを分析するところ(164-172)、ファラデーや同時代人からの引用文は、ほとんどすべてピアース・ウィリアムズからの孫引きだと考えられるが、その旨一言も断り書きがないし、ウィリアムズの本に対する言及すらない。ファラデーの講演術語録について、すでにウィリアムズの周到な分析があることは(Pearce Williams 1965, 323-334)、素人のわたしでも知っているのだから、島尾氏もよくご承知のはずである。
同じ苦情は、(3)についてはもっと強力に当てはまる。サンデマン派信徒としてのファラデーに焦点を合わせた労作として、ジョフリ・カントールの研究(Cantor 1991)があり、これについてはつい一年ほど前に当ニューズレター25号でかなり詳しく紹介したばかりである。このカントールの本は文献表にあげられており、わたしが島尾氏の記述を読んだ限りでは、島尾氏の見解は、(3)についてだけでなく(2)についても、この仕事に大きく依存していることは明白である。しかし、本文でも注でも(実は、注は皆無である)カントールの本に対する言及は一カ所もない。これはどうしたことだろうか。
わたしの危惧あるいは疑念の根拠を、以下で(3)のみに限定して具体的に示したい。以下のテーブルで、左側は島尾氏からの抜粋、右側はカントールの本からの抜粋である。いずれも、島尾氏がカントールの先行研究に対してしかるべきクレジットを与え、きちんと借用を断って記述すべき箇所である。カントールの仕事は、何年もかけてサンデマン派の文献、集会所の場所、人脈などを綿密に調べ上げたものである。
島尾 83-84
サンデマン派とはどんな宗派か
この宗派はスコットランド・プレスビテリアン教会から分裂してできたもので、ジョン・グラス(1695-1773年)を教祖とする。・・・この教派はどの時期でも信徒数が1000人を超えたことはない。十八世紀にはイギリス全土で四十カ所、アメリカには五、六カ所の集会所があった。ファラデーのころはイギリス全土で信徒数は600人で、主としてスコットランドにいた。ロンドンには約100人がいた。
Cantor 1991
Awaiting a more careful analysis, it appears that the sect started by Glas and extended by Sandeman at no time numbered more than 1000 who had made their confession of faith. (27)
Throughout the sect's history there were about forty meeting houses in Britain and a handful in America. (25)
In life, even perhaps in death, Faraday inhabited this small, close-knit community numbering about 100 souls in London and perhaps 600 in the whole of Britain. (5)
there were perhaps 600 members in 1821 and some 400 in 1867. (27)
the single most important feature of Faraday's perspective was the isolation of the London meeting house. This small fellowship comprising about 100 souls was not only isolated from other Sandemanians (...) but ... (28)
島尾 88-89
サンデマン派はしばしば教会員を除名しているが、ファラデーには重度の神経衰弱から回復した直後の、1844年3月31日、教派から除名されるという重大なことがおこった。・・・このときの除名は、正当な理由なく日曜の礼拝に欠席したからといわれる。かれはヴィクトリア女王からウィンザー宮での昼食に招かれていたのである。・・・ しかし最近の研究では、ファラデーがヴィクトリア女王に招かれた事実は宮廷記録にはなく、当時の新聞にも記載がない。またこのとき除名されたのはファラデー以外にも、彼の親友や親戚など18人に上り、これはロンドンの教会員の20パーセントに当たることから、除名は教会内部の事情によるものと考えられている。
Cantor 1991
Not only was Faraday excluded on 31 March 1844 but eighteen others suffered similarly at about the same time and among these were several of his close friends and relatives, ... Could Faraday's visit to the Queen have created such controversy, with some 20 per cent of the membership being excluded at that time? ... The standard account is, however, problematic for four further reasons. Firstly, neither Frank James (who is editing Faraday's correspondence) nor I have been able to find any evidence that Faraday visited the Queen at that time. The Queen's diary and the 'Court Circular' in The Times are silent and no contemporary letters mention the incident. ... (62)
島尾 90
科学は、手職や金儲けの職業、ファラデーのいわゆるプロフェッションと違って、天職または召命であると考えていた。したがってこれに従事する人々は、ちょうどサンデマン派の人々が信仰によって結ばれた兄弟団を形成しているように、一種の友愛会を形成しているとみた。たしかにファラデーとド・ラ・リーヴ、デュマ、シェーンバイン、テインダル、ヒューウェルらとの友情はそのようなものだったのであろう。
このような友愛会で結ばれた科学者間には、科学上の論争はあってはならないというファラデーの見解は注目される。論争は「科学そのものに属するのではなく、堕落した人間性に属する」という(1853年3月3日)。
Cantor 1991
'My desire', wrote Faraday, was 'to escape from trade, which I thought vicious and selfish'. ... A further term that became more prominent in Faraday's later correspondence is profession. For Faraday profession were superior to trades, but they too implied a financial, and thus ultimately flawed, relationship with other people. (119-120)
His friendship with such men as de la Rive, Dumas, Shoenbein, Tyndall and Whewell were almost as intimate as those in the Sandemanian brotherhood. At its best the brotherhood among scientists was like the Sandemanian church ... (124)
In the same letter to Matteucci Faraday sought to explain why science was littered with controversies.
These polemics of the scientific world are very unfortunate things; they form the great strain to which the beatiful edifice of scientific truth is subject. Are they inevitable? They surely cannot belong to science itself, but to something in our fallen natures.
(122, quotation from letter to Mateucci, 3 March 1853)
最近の出版界の傾向として、翻訳物を出す際に、定価を抑えるため、原著にあった注を省き、さらに文献表まで省いてしまうということが頻繁に行なわれていることは、わたしも承知している。しかし、ある程度学術的な研究については、こんなことをやると翻訳の価値を大幅に損なってしまう。とくに、翻訳書ではなく、資料による裏づけが命のはずの科学史の研究書でこんなことがまかり通っては、この分野の学問自体の自殺行為になりかねない。これは、もちろん、自分や自分のところの研究室の学生に対する自戒やいましめの意味も込めたコメントである。
文献
Cantor, Geoffrey (1991) Michael Faraday, Sandemanian and Scientist, Macmillan, 1991.
Pearce Williams, L. (1965) Michael Faraday, Chapman and Hall, 1965.
今年より、院生および学生の業績も加えることにした。1999年4月-2000年3月末までのもの。
内井惣七(教授)
4月 論文「道徳起源論から進化倫理学へ(続)」『哲学研究』567号5月6日 Newsletter 25, "Biographies of Michael Faraday"5月 討論「進化的に安定な戦略とは」『科学哲学』32-16月8日 Newsletter 26, Review: Albert E. Moyer, Joseph Henry8月4日 Newsletter 27, Review: Glenn. T. Seaborg, A Chemist in the White House8月20日-26日 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Cracow, Poland. General Program Committee のメンバーとして参加。Assessor に選出される。9月 ハッキング『偶然を飼いならす』の書評、思想 903 号9月14日 Newsletter 28、書評 高木仁三郎『市民の科学をめざして』10月4日 Newsletter 29、書評 ハーウィット『拒絶された原爆展』12月18日 講演 FINE Kyoto Forum 3 「道徳起源論から進化倫理学へ」1月21日-2月14日 Newsletter 30、書評 デズモンド&ムーア『ダーウィン』2月3日 Newsletter 31、本年度の修士論文・卒業論文特集伊藤和行(助教授)
論文 「科学の近代史−『プリンキピア』から「ニュートン力学」へ」、『叢書/転換期の フィロソフィー3 科学技術のゆくえ』、ミネルヴァ書房,pp. 26-42、4月25日発行。「ノストラダムスと医学のルネサンス」、『ノストラダムスとルネサンス』、岩波書 店、pp. 235-254、2月18日発行。発表 11月3日 「古典力学における運動法則の歴史性」、京都哲学会講演会、」京都大学文 学部新館第三講義室。11月27日 「病へのまなざし−ノストラダムス的宇宙観における病因論」、京都大学 大学院文学研究科/文学部第4 回公開シンポジウム「病い−その思想と文化」、京都 大学文学部新館第三講義室。12月11日 「人文主義から科学革命へ−ルネサンスにおける実践的学問観」、ルネサ ンス研究会研究発表会、同志社大学文学部。松王政浩 (研究員)
論文: 「バーチャルリアリティと人格」 (1999.6.16発行。電子情報通信学会『電子情報通信学会技術研究報告 FACE 99-10〜15 (信学技報 Vol.99 No.114)』pp.1-6.)「テンスの事実性に関するプライアの主張をめぐって」 (1999.12.25発行。科学基礎論学会『科学基礎論研究』93号, pp.25-30.)研究発表: 「コナトゥス論の変遷 〜ホッブズからライプニッツへ」 (1999.5.15 日本哲学会、上智大学)「バーチャルリアリティと人格」 (1999.6.16 電子情報通信学会 情報文化と倫理研究会、京都大学)「バーチャルリアリティと身体」 (1999.9.25 FINE京都フォーラム、京都大学)
澤井直 (D1)
論文: 「ウィリアム・ハーヴィの発生論:「すべては卵から」」 『ルネサンス研究』第六号 (2000年3月発行予定)研究発表: 「ハーヴィの方法論」 日本科学史学会京都支部1999年度第1回例会 ( 同志社大学今出川キャンパス)1999年4月17日
瀬戸口明久(M2)
論文: 「保全生物学の成立−生物多様性問題と生態学−」 『生物学史研究』64:13-23(1999年10月発行)
研究発表: 「保全生物学の成立をめぐって−環境問題と分野形成の力学−」 日本科学史学会生物学史分科会総会シンポジウム「自然保護,野生生物保護に かかわる生物学史,制度史を巡って−自然観・社会的体制・政治性−」、東大先端研、1999年12月12日
小野田波里(M1)
発表 「Einsteinの宇宙論―相対論的宇宙論の起源」、名大小沢科研費研究会、北大、1999年9月20日
そのほか、1999年10月13日には、プリンストン大学科学史のマイケル・マホニー教授が来京し、理学部数学教室と共催の講演会が行なわれた。
(c) Soshichi Uchii
Last modified Nov. 30, 2008
