

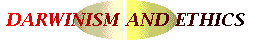 Soshichi Uchii, Kyoto Univ.
Soshichi Uchii, Kyoto Univ.(この論文は『生物科学』50-2、September 1998 に掲載されたものである。掲載論文では字数の制限のため一部の語句を省略したが、以下では省略された箇所もすべて完全に復元した。)
ダーウィニズムと倫理との関係を論じるのがわたしに与えられた課題である.小論では,この問題に関するダーウィンからハクスリーに至る19世紀の論議を概観(1節−8節)したのち,ダーウィニズムから倫理的含意を引き出そうという現代のレイチェルズの試みを検討し(9節−11節),最後にわたし自身の見解をスケッチする(12節−15節).
進化と倫理との関係は,ダーウィン自身をはじめ,19世紀の思想家によってもすでに考察の対象とされている.しかし、現代においてこの話題をアカデミックな論議の土俵に乗せるには,特有の困難がある.現代における進化倫理学――進化論の観点から倫理の問題を論じる試み――の主要な提唱者の一人であるマイケル・ルース(RUSE 1986,1993,1995)がくり返し指摘しているように,進化と倫理との間に何らかのつながりを認めようという進化倫理学は,今世紀の大半を通じて評判が悪かった.その原因はいくつか考えられる.まず,19世紀後半から20世紀前半にかけて流行した「社会的ダーウィニズム」と呼ばれる比較的粗野な思潮があり,「進化倫理学」と言えば必ずこれとの連想が成立するという事情がある.この思潮は,人間社会においても「適者生存」あるいは「自由競争による生き残り」のルールが支配すべきだと主張し,この規範的な主張を科学に基づいて正当化できるかのような印象を与えた.しかし,この思潮に強い影響を与えたのはダーウィンではなくむしろスペンサーであり,しかも社会的ダーウィニズムは,スペンサーの倫理思想自体をも著しく歪曲したものであることを注意しておかなければならない.
次に,社会的ダーウィニズムのある形態は,優生思想(およびある種の政治的イデオロギー)と結合して悪名高いナチスの蛮行を生み出すことに貢献した,という印象がわれわれにほぼ定着している.この印象に抗して進化倫理学のプラス・イメージを回復させようとするのは,なかなかむずかしい企てであろう.
そして,わたしのような哲学あるいは倫理学の専門家にとっては,今世紀初頭に現れた,「自然主義的倫理学」一般に対するG・E・ムア(1873-1958,ケンブリッジの哲学者)の手厳しい批判が重要な試金石として常に控えている.ムアは,善悪という倫理的概念を自然的な事実や性質を記述する概念によって定義し,その定義を通じて倫理的価値判断を導出しようとする試みを倫理学における「自然主義」と名づけ,このたぐいの試みはすべて「自然主義的誤謬」と呼ばれる論理的な誤りを犯すものだと非難したのである(MOORE 1903).とくに,スペンサーはこの誤りを犯した哲学者の代表として取り上げられ,「より進化した」という事実条件から「より善い」という倫理判断を誤って導出し、この誤った導出を彼の倫理学の一つの礎石にした,とムアによって論難されたのである.ムアによれば,(1)ダーウィンでは意味のない「より進化した」と「より進化してない」という比較級をスペンサーが使って「進化」に「進歩」を読み込んでいるうえに,(2)進化による善悪の規定を見逃したとしても,スペンサーはさらに彼の大前提としている快楽説価値論(生命の量が増大することを善だというために,快が善であり,生命の量の増大は快を増大させることを前提しなければならない)のところで別の自然主義的誤謬を犯していることになるのである.わたし自身も,ムアのこの議論を最初に読んだ若い(22歳の)ときの強烈な印象をいまだに忘れていない.
しかし、こういった悪評や難点によって,進化と倫理との関係を考察する試みは無益だということになってしまうのだろうか.そう結論するのは早計であるし,ある種の偏見を鵜呑みにすることになってしまう,とわたしは考える.それを以下で明らかにしていくつもりだが,まず,無用の混乱と誤解を防ぐために,倫理・道徳に関する哲学的考察を行なう倫理学(古めかしい呼び名では,道徳哲学)の基本的な区別と用語とを説明しておかなければならない(すでにご存知の方は,次節は飛ばしていただいてよい).
倫理学の課題を最も広くとるならば,倫理学とは,(1)人間の倫理・道徳に関わる諸々の事実を考察し,(2)倫理・道徳において使われる基本概念――例えば「善悪」,「義務」,「権利」,「責任」など――の意味を明らかにし、(3)われわれが為すべきこと,あるべき社会の条件,あるいは善悪の基準などを考察する学問分野である.もちろん,われわれは倫理学など知らなくとも,日常の倫理を実践し,ほぼ円滑に実生活を営むことができる.しかし,時折,われわれが直観的に使いこなしている倫理的原則(いかに為すべきかを示す規則)だけでは対応できないような事態――古典的な事例では,「忠ならんと欲すれば孝ならず・・・」,現代的な事例では「脳死を人の死と認めるべきか否か」――に遭遇し,そのためにある程度倫理「学」的な分析や考察に立ち入る必要が生じる.倫理学は,これを組織的に行ない,できれば日常的な倫理原則の妥当性の根拠まで明らかにできるような,少数の基本原理にまで遡ろうという営みである.
さて,倫理学の前述の課題のうち,(1)は倫理に関わる事実関係を明らかにすることであるから,記述的な課題であり,それ自体では善悪の価値判断や何を為すべきかという規範的な判断には立ち入らない.そこで,この課題に関わる分野は記述倫理学と名づけることができる.この分野は,当然心理学や社会学とも重なりうる研究領域である.進化論との関係で言えば,倫理判断を下してそれによって自分の行動を律するという「道徳的能力」の成り立ちや起源を明らかにするという課題は,この分野に属する.
次に,一般の人々に比較的なじみの少ない(2)は,錯綜した倫理の問題を明晰に分析し,基本原理にまで遡ろうとする哲学者にとっては死活問題であり,この手の概念分析をおろそかにしては,「倫理判断の妥当性」などというむずかしい問題には迫れるはずもないのである.先に触れたムアの倫理学における貢献は,まさにこの種の問題の重要性について再認識を強力に促した点にある.この問題分野の特徴は,「何が善か」「何を為すべきか」という倫理判断を下すことではなく,これらの判断に含まれる概念――「善」「べし」など――や判断自体を分析の対象にすることにあるので,この分野はメタ倫理学あるいは分析倫理学と呼ばれる.このような分析によって,倫理判断の特質,記述的判断との違いなどが明らかになり,ひいては倫理判断の正当化が可能かどうか,可能だとすればその条件がどういうものかが明らかになるはずだ,と多くの哲学者は考えてきた.
最後に,(3)は古今の倫理学が最終的な目標にしてきたものであり,歴史的な事例としては,理性的な自由意志が下す無条件命令(定言命法)を基本原理と見なすカントや,社会の最大幸福がすべての倫理規範の基準であると主張する功利主義などがある.しかし,(2)の成果や立場いかんによっては,このような目標は達成できないという見方も成り立つかもしれない.妥当な倫理的規範や倫理原則の存在は,倫理学を始めるにあたってあらかじめ前提できるとはかぎらない.このような懐疑的な結論にいたる可能性も含めて,この最後の分野は規範倫理学と呼ばれる.
ダーウィニズムと倫理との関係を考えるとき,われわれの考察はこれら三つの分野にまたがることになるが,科学理論としてのダーウィニズムがそれぞれの分野にどのように関わることになるのか,しっかりと区別して考える必要があろう.
さて,以上の三つの分野のどれかに関わる知見をある程度体系的に展開するという試みを「進化倫理学」と呼ぶことにすれば,進化倫理学の歴史は少なくともダーウィニズムそのものと同じほど古い.ダーウィンが進化と倫理との関係について自分の考えを発表したのは晩年の『人間の由来』(1871)においてであるが,彼が進化について考え始めた初期のころから,進化と倫理の関係について深い関心をもっていたことは,ほぼ間違いがない.なぜなら,この問題に関わる彼の基本的なアイデアは,「古い無用のノートOld & Useless Notes」というタイトルで分類されている書類の30番(1838年10月)ではっきりと述べられている(BARRET et al. 1987, 609)からである.
道徳家の二つのグループ。一方は、われわれの生活の規則は最大幸福を生み出すはずだという。――他方は、われわれが道徳感覚を持つという。――しかし、私の見解は両者を結合し、それらがほとんど等しいことを示す。最大の善を生み出してきたもの、あるいはむしろそもそも善のために必要であったものは、本能的な道徳感覚である(そして、このことのみが、なぜわれわれの道徳感覚が復讐を指示するのかを説明する)。幸福のための規則を判断するには、われわれははるかな将来と一般的な行為を見なければならない――なぜなら、もちろん、その規則ははるかな過去にわれわれの善にとって一般に最善であったものの結果だからである――(われわれが将来を見られるよりも、もっと遠くまで過去に遡る。だからわれわれの規則はときには言うことがむずかしいかもしれない)。ミツバチの巣がミツバチの本能なしでは存続できないのと同様、社会は道徳感覚がなければ存続しえない。(内井訳。太字はダーウィンの強調。)
若いときにノートに書きつけた覚え書きであるから少々わかりにくいところもあるが,とくに最後の文において,20世紀後半の社会生物学と同じ発想が明確に述べられていることに驚く.このように,ダーウィンは,まず(1)進化論が道徳の生物学的起源について重要な事実を明らかにできると考えている.これは前節で述べた記述倫理学に属する主張であり,ダーウィンは「記述倫理学には生物学が不可欠である」という主張をおそらく初めて打ち出したのである.
次に,生物学者にはおそらくあまりなじみのない「道徳感覚」という言葉について少し説明しておかなければならない.わかりやすく言えば,これは「善悪や正・不正を見分ける能力」とでも言い換えられるある種の知覚能力であり,18世紀のかなりの数の哲学者は,この能力を認めることで人間の倫理に見られる多くの事実が説明できると考えたのである.この道徳感覚には,自分の個人的な好みに逆らって義務を果たさなければならないという「義務感」や,なすべきことを為さなかった場合に感じる「悔恨」や「自責の念」といった道徳感情を感じる能力も含められている.
そこで,引用の最初の部分でダーウィンが言っていることは,(2)「倫理学者には,われわれの幸福を基準において得られる行動規則を重視する学派と,道徳感覚がわれわれの行為に指針を与えることを強調する学派とがあるが,進化論の観点から見れば,道徳感覚は社会生活に適応した結果定着した能力であり,社会の幸福にとって不可欠の手段である.他方,道徳感覚が過去の適応の結果われわれに備わった能力であるということは,それによってわれわれの祖先が善を享受してきたということである」という趣旨になろう.この主張は,もちろん(1)の主張をより詳細に展開した部分も含むが,純粋に記述倫理学の枠のなかに収まるとは言いがたい部分も含む.というのは,ダーウィンが言及している倫理学者が考えている「幸福」や「善」は,適応の文脈でいわれる善,すなわち生物学的利益――適応度,あるいは子孫をより多く残せるという意味での利益――とは明らかに異なるからである(そして、このことを明らかにできるのは,前節で触れたメタ倫理学にほかならない).
このように,ダーウィンの短いノートを解釈するに際してさえ,進化倫理学が直面すべき問題点がある程度縮図の形で認められる.すなわち,ダーウィニズムが記述倫理学に貢献できるという主張は問題なく認められるとしても,それから先,メタ倫理学や規範倫理学に立ち入る部分については,ダーウィニズムはいったいいかなる貢献をなしうるのであろうか.
ダーウィンの進化と倫理との関係についての円熟期の思索は,すでに触れたとおり,『人間の由来』で展開された.これについてはすでに何度も紹介したので(内井 1996, 1997, UCHII 1997b),ここでは主要な論点のみをまとめておく.
(1)まず,ダーウィンの考察の基盤となるのは,人間の諸能力と動物の諸能力との連続性の主張である.微少な変化の積み重ねによって大きな変化が生じるという彼の進化理論からすれば,これは当然の主張とも言えるが,理論から要請されることとは別に,多くの具体的事例によってこの主張を裏づける試みがなされているところが,ダーウィンの真骨頂であろう.この主張は,人間を他の動物から分かつ条件と従来見なされてきた人間の高度な心的能力,とくに知性と道徳(を可能にする)能力にまで拡張される.
(2)人間は社会的な動物であることが確認され,社会的本能と高度な知性との結合が倫理を可能にする本質的な条件として特定される.ダーウィンが言う社会的本能とは,仲間との交わりを好み,共感(自分の過去の感情や,他者の感情を自分のうちで再現すること)の能力をもち,仲間に対する奉仕を行なうような性向のことであり,本能と呼ばれるからには当然遺伝的な基盤をもつことが前提されている.ダーウィンがこう前提するための決め手とするのは,共感の行使には明らかな「身内びいき」の傾向が見られることで,このことは自分の進化学説によってしか説明できない,と彼は考えている.
(3)そして,ダーウィンが彼の道徳起源論の中心的な命題として主張したのは,社会的であり,かつ高度な知性を備えた動物であれば(人間であろうがなかろうが),この動物は「倫理判断」を下し,その判断とそれに伴う「道徳感情」に従ってみずからの行為を規制するという「道徳的能力」を獲得するはずだということである.このような能力のことを,哲学者は「道徳感覚」とか「良心」と名づけてきたのである.
ダーウィンのこの主張を少し解説するなら,少なくとも二つの論点が含まれている.一つは,(a)「道徳感覚」は複合的な能力であり,より基本的な能力に分析できるという論点である.もう一つは,(b)そのような複合的な能力が,(2)で述べられた条件が満たされる動物にあっては自然淘汰の結果獲得されるであろうという(彼の進化論,すなわちダーウィニズムによる)推測である.
(a)の論点は,必ずしも進化論を前提するわけではない.したがって,進化論を知らない哲学者でもこの論点は提示できるかもしれない.事実,「道徳感覚」を一つの基本的な能力として仮定する哲学者が多数いた一方で,これをもっと基本的な能力に分析した哲学者も,ダーウィン以前および以後に何人かいたことが指摘できる(内井 1996、25-31、73-76).しかし、(b)の論点はダーウィンに特有である.また,この論点は,人間以外の動物に対してもある種の「予測」を含意しうるので,単なる思弁ではない「科学的」な内容を含むことに注意しなければならない.例えば,チンパンジーなどの霊長類において,ダーウィンが挙げた二条件が近似的に満たされていると見るならば,チンパンジーの行動観察はダーウィンの推測を検証する材料になりうるのである(もちろん,自然淘汰の結果として解釈できるかどうかは,直接検証できるわけではなく,ある種のモデルを介した間接的な突き合わせに依存するであろうが).
(4)道徳感覚をもつとは,「こうすべきだ」という判断にある種の拘束力をもたせることを意味する.ダーウィンは,この拘束力が一群の感情(道徳感情)によって与えられると考え,なぜそのような感情が生じるのかを説明すべきだと考えた.彼の説明は,社会的本能が満たされないときに生じる不快感が蓄積されて道徳感情を生み出すというものである。他の欲求や本能は一時的には社会的本能より強力に働きうるが,社会的本能の永続性ゆえに,記憶の中では社会的本能と関係する感情のほうが(共感によってたびたび再現されるので)優勢となる.また,自分の行為の結果他人が被害を受けた場合には,その他人の不快感や仲間からの非難も共感によって自分のうちにある程度取り込まれる(そして,記憶や他者と自分との関係に関する知識は高度な知性に依存する).こうして生じた感情が「次はこうすべきでない」という判断に拘束力を与え,それが蓄積されて「良心」の拘束力となる,とダーウィンは論じる.このように,社会的本能の永続性と共感の作用を持ち出すのが彼の説明のカギとなっている.
(5)ダーウィンは,人間の倫理が生物学だけで説明できるわけではなく,個人や社会の習慣あるいは文化,時と場所によって変化しうる人為的な規範という側面を考慮に入れる必要性も十分に認識していた.そして、このような側面においては模倣や感化という,自然淘汰とは別の過程が重要な役割を果たすことも認識していた.しかし、倫理のそういった他の側面が機能するためには,前述のような生物学的な基盤が不可欠であることを強調したのである.この認識は,若いときのノート以来一貫している.
(6)前述(3b)の科学的推測を裏づける議論は,よく知られているように,社会的本能や共感能力に含まれる「利他性」がなぜ自然淘汰で進化しうるかという点の論証が不十分であり,ダーウィン自身もそのことに気づいていた.ダーウィンは血縁淘汰や群淘汰のアイデアを示唆しているが,遺伝学の知識を欠いていた当時の状態では,この不備は致し方のないことであろう.
以上に概略を紹介したダーウィンの道徳起源論は,若いときのノートと違ってほぼ厳密に記述倫理学の枠内にとどまっている.しかし、『人間の由来』でも,文明と自然淘汰との関係を論じた部分(第1部第5章)では,規範倫理学にも関わりがある微妙な議論が出てくる.
例えば,ダーウィンは,文明の発達が自然淘汰の働きを抑制し,その限りでは生物学的に望ましくない効果をもたらす,と認めている.この認識は,表現の違いはあっても,この時代のウォレス,ゴールトン,ハクスリーらの多くの人々に共通するものである。「生物学的に望ましくない」というのはわたしの表現であるが,その意味は,肉体的・精神的に虚弱な者の数が増えるということである.念のためにダーウィンの言葉を引用しておこう.
かくして、文明社会での虚弱な成員はその数を増す。家畜の繁殖にたずさわってきた者なら誰でも、これが人類にとって大変有害であるにちがいないということを疑わない。管理を怠ったり、誤った管理の仕方をしたりした場合、家畜の品種の退化がいかに速やかに生じるかは、驚くほどである。しかし、人間自身の場合は除外して、誰にせよ自分の最も劣った家畜が繁殖することを許容するほど無知ではないのである。(DARWIN 1874, 206. 邦訳195. ただし,引用の訳は拙訳.以下同様.)
しかし、ダーウィンは,このことを根拠にして何らかの「優生政策」を考えるべきだと主張するわけではない.人為淘汰と自然淘汰とのアナロジーが彼の自然淘汰説の支えになっているからといって,人間の「人為淘汰」にまでやすやすと踏み込んでよいことにはならない.ダーウィンは,ここでは彼の倫理的見地に踏みとどまって,人間の弱者に対して救いの手を差し伸べるべきであり,そのように促す感情が進化と文化的影響の結果われわれに備わっていると主張する.ここでの彼の倫理判断は,次の引用から明らかなように,予測されうる(倫理的)善と悪とを秤にかけた功利主義的な判断である.
外科医が手術のとき無情に振舞ってよいのは、彼が患者の利益になることを行なっていると知っているからである。しかし、もしわれわれが弱くて無力な人々を意図的に見捨てたとしたならば、これは不確かな利益のために圧倒的に大きな悪を現在に為すことでしかないことになろう。したがって、われわれは、虚弱な者が生き残って数を増やしていくということの間違いなく悪い結果を耐えなければならない。しかし、その悪い結果を抑制する要因が少なくとも一つ、常に働いているように見える。というのは、社会の中の弱い劣った成員は、健康な者ほど自由には結婚しない。そして、この抑制は、心身の虚弱な者が結婚を控えることによって、限界なく強化されるかもしれない。ただし、これは、当然期待すべきことというよりは、希望にとどまる。(DARWIN 1874, 206. 邦訳195-196.)
要するに、ダーウィンは,生物学的に望ましくない(そして不確かな)悪を避けるために,それよりも圧倒的に大きな倫理的悪を人々に為すことは道理にあわない,と言っているのである.この判断は疑いもなく健全だと思われる(だが、なぜ「健全だ」と言えるのだろうか.その理由を明らかにするのがメタ倫理学と規範倫理学の一つの課題である).しかし、この判断を下した倫理的見地は,進化論や生物学の知見とは独立に,あらかじめ前提されているにすぎない.つまり,ダーウィニズムの問題領域において規範倫理に関わる問題が生じたとき,ダーウィンは彼の記述倫理学とは無関係に前提された倫理的見地をとり,その見地から倫理判断を下しているわけで,記述倫理学は規範倫理学には何も貢献していないことが明らかである.
March 10, 1999. Last modified June 14, 2006. (c) Soshichi Uchii
webmaster