保健体育研究室 藤猪省太(ふじいしょうぞう)

天理大学を卒業してはや28年、そして50歳になり、時の流れの速さを感じさせられる年齢に達したと思う今日このごろです。
常に前しか見ない性格ですが、もうそろそろ過去も少しは振り返りながら前向きに人生を送らなくてならない年齢であることも自覚し、良い仕事ができるよう努力しようと思っています。
天理柔道にあこがれ強くなりたい一念で、高校から天理にお世話になり大学卒業までの7年間柔道中心に学び、卒業後、18年問は天理を離れ色々なことを私なりに経験してきましたが、やはり柔道を中心に多くのことを学ぷことができました。
そして、天理大学に奉織して10年になりますが、柔道以外で多くのことも学びますが、柔道に開連することで学ばせられる印象はやはり強く、柔道家であることを常に自覚させられます。
今後も柔道中心に学んだことを例えてながら教員生活に生かし、人生勉強をしていきたいと願っています。
私は教員でありますが、柔道家であり教員であると思っています。
今後も柔道のことを中心に学び、柔道家であり教員である気持ちで天理大学にあったアドパイスを学生にしていきたい。
趣味は、柔道、読書(特に歴史書、歴史小説)です。
趣味も広げたいと思っています。
図書館学研究室 山中秀夫(やまなか ひでお)
 「Tulips」目下最大の目玉・大型連載記事「教養部所属教員・私を語るシリーズ」の最終回を飾る(?)原稿締め切りが遠に過ぎ,西国あたりに逃亡していましたが,編集長様より複数のメール・アドレス宛に同時にでかい赤丸印の「督促メール」を頂戴し,ついに観念,徒然なるままにつたない文章で失礼します。
「Tulips」目下最大の目玉・大型連載記事「教養部所属教員・私を語るシリーズ」の最終回を飾る(?)原稿締め切りが遠に過ぎ,西国あたりに逃亡していましたが,編集長様より複数のメール・アドレス宛に同時にでかい赤丸印の「督促メール」を頂戴し,ついに観念,徒然なるままにつたない文章で失礼します。
担当と部屋:
図書館司書課程および学校図書館司書教諭課程のいくつかと「コンピュータ入門」。いつもは研究棟北棟3階南向き独居室(日当たり良好,会議室直近,廁牀やや遠方)
成立過程:
生まれは河内ですが,小学2年から天理に住み,高校1年から桜井に移住,なぜか入れた大学の4年間は東遷,あっという間に時が過ぎ,Uターンして天理大学に奉職。はじめは大学図書課に在籍,2年で天理図書館に配置換え,木星1周12年が過ぎて再び大学に舞い戻り現在の場所にやっと3年おります。
性格:
自分で申告するのであてにはなりませんが,一応…。血液型A型のキャッチフレーズとして(大学時代の恩師のマネで),「謹言実直質実剛健,日本を支えるA型」。自分でも感心する性格は,「Optimist」であること。よい面で機能すればいいのですが,悪い面で機能すると朽索にすがってずるずると…。でも,結局は忘却の彼方へ。
雑を大切に:
何かを分けようとするとき,(例えば新聞の切り抜きやコピーであったり,図書であったり)項目として作っておけば大変便利なのが「雑」という項目です。多くの図書館で資料をその内容によって分類するときに用いられている「日本十進分類法」にはありませんが,近い項目はあります。この「雑」という項目に入るモノには,なにか楽しげな,ワクワクさせる魅力を感じます。何かに依らない,分けきらない,しかし単独で魅力的な何かを持っている,とてもいいと思いませんか? 「雑」をつかった言葉として,昔からお世話になっている「雑巾」,みんな本当は大好きな「雑言」,コンビニでも人気のある「雑誌」,いつも不思議な発見がある「雑書」,そして「雑学」など。字書(漢字源)によると,「雑」には,「いろいろなものがひと所に集まって入りまじる。入り乱れる。集めていっしょにする。」という意味があります。また違う字書(新字源)によると,「いろいろのいろどりの糸を集めて衣を作る,ひいては「まじる」意をあらわす」とあります。
「雑」は総体として不思議な何か(チカラやイロ?)を発揮しますが,それを構成する個々も各々不思議な何かを,小さいけれども他とは違った何かを本来は持っていると思います。それらを個々が磨けば必ずその総体も磨きがかかって,より一層何かを発揮することになると思います。
いろいろなひとが寄り集まって様々なグループが構成されます。その中で交流(コミュニケーション)すること,お互いをこすり合わせることで自然と磨かれていくモノもあると思います。これからも大いにいろいろな人と交流したいと考えています。
最近のマイブームフレーズに,金子みすずの「わたしと小鳥とすずと」の一節,
すずと、小鳥と、それからわたし,
みんなちがって、みんないい。
自分とは違うみなさんと,雑の一人として私も‘ひたすら’,何かを見つけて磨かねば思う,今日このごろ……。
朽木糞牆といわれる前に,不惑男の密かな自戒を込めて……
yamanaka@sta.tenri-u.ac.jpでした。
図書館学研究室 吉田憲一(よしだ けんいち)
もう10年近くも前になるが,1992年秋に13回構成のテレビ番組「はじめてのパソコン」がNHKでスタートした。全国的なパソコン人気が,放送界でもこんなにまとまった入門シリーズを実現させたのだろう。講師を担当された教育工学が専門の赤堀侃司氏は,最初の回に「読み・書き・パソコン」と語られた。そろばんの現代版,道具としてのパソコンがもつ役割が印象的な番組であった。
また出版界では,最新情報を提供してくれる新聞に「週刊読書人」がある。この雑誌が,新しい世紀の第1号で「パソコンと新書」(「新書にはパソコンがよく似合う!」)を特集した。実際,90年代に入ってパソコンを使った情報の整理や組織化に関する図書が,新書等で次々と刊行された。今までになかったことである。その中では,時間軸を整理の基本とする『超整理法』(野口悠紀雄著 1993 中公新書)や,昨年秋にNHKの「クローズアップ現代」にも登場して立花隆が一方的な非難を浴びせた(文藝春秋2000年12月号)『捨てる!技術』(辰巳渚著 2000 宝島社新書)がパソコン時代に乗じてベストセラーになったりした。いずれも「整理技術」を個人の体験に置き換えた勝手な解釈で,読者の危機感に訴えた皮相的な興味をそそる内容,とてもこのテーマにきちんと取り組んだ本とは思えないのだが,ミリオンセラーを達成している。パソコンやインターネットが時代のキーワードとなり、膨大化する情報の洪水を交通整理することに社会の眼がむけられてきたことによるのだろう。私の研究分野は図書館情報学だが,このような時代にあって、様々な情報を適切に整理・組織化して,きちんと主題検索できるシステムに興味をもっている。
次に私の趣味の将棋界では,といってもここ10年くらいは人との対局をしたことはなく,もっぱらパソコンとの対戦なのだが。この世界には「竜王」という最高のタイトルがある。お茶の間のコマーシャルにも登場して,皆さんも名前だけはご存知かと思うが,羽生善治五冠王が挑戦者となって,藤井猛竜王に挑戦したタイトル戦の第1戦が,昨年10月に上海で行われた。この上海では,子供達に将棋が人気になっていて,小学校の教科に採用されている学校がいくつもあるそうだ。大阪府でもそのような話があるようですが。またゲームの種類は異なるが,韓国では囲碁が少年少女に大変な人気で,囲碁のチャンピオンはヒーロー扱いされているそうだ。一方,ヨーロッパで人気のチェスは,囲碁や将棋に比べると,一手の自由度が極めて小さいこともあって,IBMのスーパーコンに,世界チャンピオンが負けてしまった話題が,数年前,新聞紙面を賑わせた。しかし本当にコンピュータは世界チャンピオンに勝つほどに世界最強の力をもっているのだろうか。現在のノイマン型コンピュータには,必ずしもそのような能力はないようで,この世界チャンピオンに勝ったコンピュータが,彼より少し弱い相手に勝つかというと,そうはいかないようです。しかし新世紀に入って経験獲得型の新たなコンピュータが出てくれば,さらなる飛躍が期待される。人間のチャンピオンなどとても相手にならなくなるのであろう。楽しみなことです。
一方,将棋や囲碁の世界では,残念ながら実力はまだまだだ。5年位前までの将棋の実力は,アマチュアの4・5級程度だった(それでも結構な実力ですが)。ところが,今や毎年行われるコンピュータ将棋選手権の出場者(ソフト作成者)も急増した成果として,昨年優勝したソフト(現役東大生らが制作した「東大将棋」が昨年優勝した)の実力は,アマチュア2・3段位の腕前をもつまでにアップしてきた。詰将棋に至ってはプロ顔負けの実力である。こんなこともあって,プロの将棋界にも数々の話題を提供している。先の竜王戦の前夜祭では,竜王や五冠王が,コンピュータが将棋のチャンピオンを越える日が何時やってくるのか話題にされていたとのこと。
将棋のようなゲームは,物事を論理的・系統的に考えていく(つまり情報を整理・組織化する)力を磨いてくれるのではないかと思っている。ゲームの対戦では、ひとつの目的(相手の玉を詰めること)を実行するにおいて,そのプロセスでは、様々な考え方は自由にできるが,必ず結果からの厳しい「返礼」(敗戦)を受けることになる。つまりその考え方や発言の責任を,結果から厳しく問われることとなる。近年,一方的で無責任な発言が一人歩きして、結果の責任が問われないことが多い現代社会への挑戦とも言える醍醐味が大変に面白いと思っている。
情報の組織化や図書館情報学に興味を持つ方,将来,図書館員になってみたい方,あるいは,(パソコン)将棋に興味のある方,研究室をお訪ね下さい。研究室は,研究棟3階の354室ですが,共同研究室(370)にいる方が多いかと思います。
いま、こんなことをしています
教職課程 赤塚康雄(あかつか やすお)
論文作成と採点で苦闘しています。時間がありません。申し訳ありませんが、最近の新聞記事を通して、いまこんな仕事をしています、という意味で自己紹介にかえさせて戴きます。
 痛々しい肉声収録
痛々しい肉声収録
国民学校の証言集を出版
(埼玉新聞2000年11月14日)
太平洋戦争中や戦後、統廃合などで消えた大阪市の国民学校(小学校)の実態について関係者数百人に取材、まとめた証言集がこのほど出版された。
 この本は赤塚康雄天理大教授(日本教育史)がまとめた「続 消えたわが母校 なにわの学校物語」(つげ書房新社)。
この本は赤塚康雄天理大教授(日本教育史)がまとめた「続 消えたわが母校 なにわの学校物語」(つげ書房新社)。
五年前に出版した証言集の続編で、今回は写真や証言で四十八校を紹介。満州開拓団に加わった少年の体験談や、体力づくりのためと女生徒が上半身裸で運動場を行進させられた訓練の様子など、痛々しい肉声でつづっている。
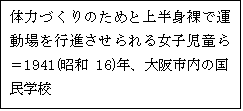 同教授によると、国民学校の記録はほとんどなく、所在地すら不明となっているケースも多い。戦時下の学校の悲惨な状態を知る上で、貴重な資料となりそうだ。
同教授によると、国民学校の記録はほとんどなく、所在地すら不明となっているケースも多い。戦時下の学校の悲惨な状態を知る上で、貴重な資料となりそうだ。
終戦直前の一九四五年春、市内に二百七十七校あった国民学校は翌春、百八十八校に激減。特に軍需工場や港湾施設が集中した港区の空襲は激烈で、多くの学校が再開できないほどの甚大な被害を受けた。
学校ごとに割り当てがあったためか、教師による「満蒙(まんもう)開拓青少年義勇軍」への強引な勧誘もあった。帰れなかった子どもが多い一方、捕虜になったり野戦軍に加わるなどして命を永らえ、五〇年代になり、ようやく帰国できたとの証言も。
赤塚教授は「証言者の多くは高齢者。取材半ばで亡くなる人もいて、あせりながらまとめた。痕跡すら消えた学校の同級生同士が連絡を取り合えるきっかけになれば」としている。
---------------------------------------------------------------
(追記)戦後教育改革の資料探索に国会図書館へ通っていた青年時代、恩師から夜は図書館は開いていないだろう、折角の東京の時間が勿体無い、夜は改革に関わった人物を訪ねなさいと指導されました。改革を推進したかつての教育刷新委員の南原繁、天野貞祐、城戸幡太郎各氏や田中耕太郎、日高第四郎氏ら文部省の元高官からうらばなしまで聞くことが出来、研究の財産になったことを思い出しています。若さゆえにやれたこと、いまからだったらできるかどうか。そのときの方法論がこの年齢になっても生きているようです。学生諸君、ゼミの教師から人生の指針を得ておくことも必要かと思います。
教職課程 伊藤和男(いとう かずお)

神田さん(写真右)も私も、戦後のベビー・ブームの頃に生まれた「団塊の世代」。どう数えるのかは知らないが、現在の人口のうち800万人ほどがこの世代にカウントされている。何をするにもずいぶん競争の激しい世代で、おたがい押し合いへしあいしながら生きてきた。大学に入ったのは1960年代の終わりころ。ちょうど経済の高度成長のピークが重なって、大学がはっきりと大衆化していく時期だった。いまではもう死語になったようだが、そのころはまだ「五月病」ということばが生きていた。それまで程度の差はあれ大人たちが敷いたレールの上を走ってきた高校生が、大学に入ったとたん、今日からおまえは自由だ、といわれ、何の準備もないまま唐突に自由という重荷を担わされるはめになったことからくるストレスに悩む症候群のことだ。そのころの学生のファッションで覚えているのは、大きなショルダー・バッグ。たぶん重い本が何冊も入っていたのだろう。いま振り返れば、何か重りがなければフワフワとどこかへ飛んでいきそうな自分を現実につなぎとめる重石のように思えてくる。私もまた人並みに大きなショルダー・バッグを、どこに行くときも手放さなかった。そのバッグの中身が頭に入ったかどうかは定かではないが、重いものを歩いて運ぶ体力だけは確かについた。それに比べていま学生をしている皆さんは、いかにも軽やか、しなやかだ。すくなくとも、「自由という重荷」などに悩む自意識過剰の事大主義とは無縁に見える。
大学は教育学部に入ったのだが、確かなことを学びたかったので歴史(教育史)を専攻することにした。「授業をしているのではなく、大学の軒先を借りて塾を開いているのだ。」と広言していた指導教官のゼミは、2時半から始まって8時すぎまで続くのが普通だった。ある日、風邪でゼミを休んだら先生から電話がかかってきた。熱は何度ある、と尋ねられたので、37.5度は超えていた体温計の目盛りを答えたところ、それぐらいで休むなら大学を辞めてしまえ、と叱られた。どれもむちゃくちゃな話のように聞こえるだろう。でも、大学の先生はどこか取り澄ましたタイプが多かった時代に、こんな先生と出会ったことは生涯の幸いだったと思っている。テーマをもって研究するようになってからつくづく思い知らされたのは、自分の視野の狭さだった。自分では精いっぱい正確かつバランスのとれた見方をしたつもりでも、まったく違った視点や発想からその偏りを指摘されたりする。また私が切り取った歴史上の現象は、それとは一見無縁に見える他の分野の出来事と深いところでつながっており、その関わりを解きほぐさないと、部分的には妥当な分析であっても、全体から見れば一面的でありうるということに気づかされたことも少なくない。ひとことでいえば教養の不足である。これは単に研究生活に限った話ではない。計量的効率性を重視する産業社会では、そもそも計量不能で、しかもいつ役に立つかもはっきりしない(もしかしたら一生役に立たないかもしれない)「教養」は、これまでのどの時代にもまして不人気である。あるフランス人のように「教養とは、あらゆる知識を忘れ去ったあとになお残っているもの。」などと禅問答のようなことを言われると、よくは分からないがとりあえずは敬して遠ざかっておこうという気にもなろう。だがしかし、いま自分の目の前にあるリアリティ、自分の世界にこだわることが、自分の外にも別の世界が広がっており、そこにはまた別のリアリティがあることに対する想像力の欠如につながるとすれば、私(たち)は、かつてプラトンが「洞窟の比喩」を用いて憐れんだ魂の奴隷の世界で、勘違いしたまま生涯を終えることになる、と自戒している。
