民謡曲を習ってから、尺八を演奏する機会が多くなった。
得意先の結婚式でお祝いに「長持唄」を吹いた。 その事が業界の噂になり「おれの息子が結婚するので一曲吹いてくれ」と頼まれる様になる。
二度三度続くうちに、冗談で「ギャラ貰いますよ」と言いながら「やっぱり、御得意さんからギャラを貰うわけにはいかんので、ギャラ分うちの本を売ってください」と言うと「よっしゃ、よっしゃ」と嬉しそうな声が帰って来た。そんなこんなで、舞台度胸も板に付き「お立ち酒」や宮城長持唄」などが私の得意曲になった。
与作の好きな「ふるさとの唄」
青森県 津軽山唄 謙良節
山形県 最上川舟歌
宮城県 長持唄 さんさ時雨
秋田県 喜代節
青森県 十三の砂山
岩手県 南部牛追唄
福島県 新相馬節
宮崎県 刈干切り唄
徳島県 祖谷の粉ひき唄
栃木県 石切節
宮崎県 日向木挽唄
奈良県 吉野筏流し唄
尺八は悲しい時の方が良く似合う。
88才で亡くなった父が死んだ通夜の席、天寿を全うした親父を送るに相応しい賑やかな雰囲気の中、仏の前で古典「朝露」と言う曲を吹いた。
吹きながら涙がこぼれた。 尺八の音が悲しみを増幅させたようだ。さっきまで笑っていた家族親戚みんなが涙してくれた。
たかが竹、されど竹。 たった五つの穴から出る音色は喜び、悲しみ、苦しみの感情を伝える独特の音色なのかも知れない。
生涯尺八とは縁が続きそうだ。
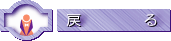
我が人生「尺八」を友に
35年前、薄暗い裸電球の下で聞いた尺八の音色に感動して、無性に尺八を習いたくなる。
「尺八の先生知らない?」と、会う人毎に訪ねて回った。
幸いな事に都山流竹林軒の称号を持つ辻井嶺山先生に出会って入門、初伝から師範の免状を取得するまでに10年の年月がかかった。
その間、演奏会で舞台に立つ事も多くなり高度な曲をこなせる様になったが、 なぜか古典曲には夢中になる事が出来なくなった。
少しづつ情熱も消え舞台に立つ事も尺八を吹くことからも遠のいてしまった。
数年後、心境の変化が起きる。 「もう一度自由に尺八を吹きたい」
思い立って民謡尺八の畦地玉堂先生に弟子入り、4年間で120曲の民謡を教わる。
民謡尺八は主役にはなれない、歌い手を盛り上げる為の脇役である。 しかし楽しい。
古典から民謡に変わることはクラシック音楽からポピュラー音楽に変わる様なものだ。
心癒してくれた尺八


