
誓いと絆(中編)
2 絆に導かれ
一夜が明けた。
集落を包み込んでいた炎は、どうにか消し止められた。
今は、昨夜の惨劇で亡くなった同朋たちの遺体を一つの場所に集め、その葬儀を行っている。
生き延びたごく一握りの人間たちは、亡くなった同胞たちの魂が、無事〈聖霊〉に受け入れられるよう切に願った。
イーシャの姿もそこにあった。彼女は熱心に祈りながら、サリサや親しかった知人たちに心で呼びかけた。
(皆、きっとあたしが仇をとってやるからね)
イーシャは昨晩の事件以後、ずっとそのことを考えていた。そうでもしないことには、自分の中での怒りがおさまりつきそうになかったからだ。このまま何もできないままでは、気分も悪い。
しかし、どういうふうに仇を討つかと考え始めると、中々結論はでてくれなかった。
生き延びた集落の人間にしても、敵に復讐しよう考えるものはいなかった。だが、それも無理ないこと。生き残りの大半は、無力な老人なのだから。
老人たちにも悔しい気持ちはあるだろう。その悔しさをバネにする行動力がないだけだ。そして、それはイーシャにも、ある意味で言えることだった。気持ちだけが先走って実質が伴わない・・・・・・。
敵の数は、少なく見積もっても三十人以上はいたという。その中でも指揮をとっていたのは、この島では珍しい赤い髪の男だという。
なんにせよ、イーシャ一人で戦いを挑むには数が多すぎる。
彼女は剣の達人でもなければ、知識に長けた賢人でもない。多少は何らかの才覚があるにせよ、非凡な人間の範疇を超えることはできないのだ。
・・・・・・力が欲しい。
イーシャは死者への祈りを捧げながら、痛切に思った。
そのときだ。
『汝、復讐を望み、力を欲するか?』
心の内より、そんな声が響いた。それは重々しい男の声だった。
(誰?)
イーシャは驚いた。実際に耳に聞こえた声ではない。
『我は汝を見守りし者。そして、汝に試練を与えし者』
心の内から脳裏へ、その声は響く。
はじめてのこの感覚にイーシャは戸惑った。だが、不思議と嫌な感じはしなかった。むしろその声は、はじめて聞くはずのものなのに、懐かしみすら覚えるぐらいだ。
(あんた、一体誰なのさ?)
イーシャは心の中で再び問いかけた。すると、彼女の脳裏に一つの姿がうっすらと浮かび上がる。
現れたのは、黄金の角をもった黒い大男だった。
『我は汝が〈聖宿〉アポルトブルト』
(・・・・・・アポルトブルト? 何だい、それは。名前なの)
『いかにも。そして我は、汝が〈聖宿〉』
(〈聖宿〉って、どういう意味さ)
『〈聖宿〉とは汝が生まれし時よりずっと、汝が成長を見定めしもの。そして、必要あらば道を示す者』
アポルトブルトは尊大に語るが、イーシャには今一つピンとくるものがなかった。少なくとも判ったことといえば、ただ者ではなさそうだということぐらいか。
(あんた、人の心の中に直接語りかけてくるなんて、神様かなんかなの?)
イーシャは嫌悪を露にして訊ねた。彼女は神と呼ばれる存在に、あまり良い印象は抱いていない。
もっともそれをいえば、この世界の人間の大半はそうなのかもしれない。
この世界・・・・・・ヴァルナレードにおいては、神は人間の創造主ではない。神は人間にはない強大な力を備えた、別次元の住人と呼べばよいだろうか。神には空高くにおわす天空の神々と、地の深くに住まう冥界の神々とが存在する。そして、この二派の神々の間では、その昔、この地上世界たるヴァルナレードを巡って、凄絶なる戦いが繰り広げられたのだ。
山は砕け、海は裂け、炎の柱が幾本にも渡って、この世界を貫いたという。
人間たちは、地上世界の先住種族であったにもかかわらず、神々の抗争には何ら手出しをすることもできなかった。ただ無力さを噛み締めながら、自分たちの世界を蹂躙していく神を黙って見ているしかなかっらのだ。
しかし、その戦いの流れも、ある瞬間から変わっていった。人間の嘆きに同調した一人の心優しき女神が、とある人間の青年に〈神殺し〉の力を授けたからである。〈神殺し〉となった青年は、横暴なる神々に対して次々と戦いを挑み、最終的にはこの世界に居据わった神々を、それぞれの世界に引き戻させることに成功した。
それ以後は神々も、この世界への直接介入は避けるようになったという。
これが神と人間との、おおよその関係。ヴァルナレードに住まう人間にとって神々とは、大いなる力を持った、忌むべき存在という認識が強いのだ。
だが、今イーシャに語りかけるアポルトブルトは。
『我は〈聖宿〉。神々とは異なるもの』
重々しき口調で、そう答えた。
(神様ではないの? じゃあ、一体何なの)
『我は〈聖宿〉。汝が生まれし時よりずっと・・・・・・』
(ああ、もういい。もういい。あんたは〈聖宿〉、それでいいよ。そんなことより、あんたはあたしに何の用なのさ?)
イーシャは投げやりに問う。
『汝は復讐を願った。ゆえに我は、汝に助力をせん』
(・・・・・・それって、あんたがあたしに力を貸してくれるって事かい)
『いかにも。汝が復讐は、汝に課せられし宿命であり、試練でもある。ゆえに汝がその道を進むとあらば、我は汝に助力する』
アポルトブルトの言葉にイーシャは迷った。
力は確かに欲しい。しかし、えたいの知れぬ者の力に頼るのもどうかと思える。
そんなイーシャの心を察してか、アポルトブルトは更に語りかけてきた。
『汝が復讐は、あくまで汝が成すもの。それが試練でもある。我が手助けするは、あくまでも力の一端を与える事のみ。それをいかにして使うかは、汝の心が決めること』
(あんたからの助力を断ったらどうなるの?)
『別にどうにもならぬ。ただ、汝は復讐をあきらめるかも知れぬが』
(どうしてそんなことが言える!)
イーシャは心の中で激昂するが、アポルトブルトは穏やかにやり返した。
『我は汝の成長を見定めしもの。ゆえに汝の今の性格は把握している。今の汝では我が道を示さぬ限り、動くことはかなわぬであろう』
(好き勝手言ってくれるね)
イーシャは憤慨するが、半ば指摘されたことが間違っていないだけに悔しい。
確かに今の自分には迷いが多い。力が欲しいと願うあたりから、そもそもが間違っているのかもしれない。いや、力が欲しいという願望は構わないが、それを得るための努力を自分はしようとしたのか?
考える時間が少なかったといえばそれまでだが、それだけでは言い訳のような気がする。イーシャは良くも悪くも、自分にも他人にも厳しい部分があった。
しばらく考えた後、イーシャは己の心の弱さを認めた。
(アポルトブルト)
イーシャは〈聖宿〉に呼びかけた。
『何だ?』
(あんたの助力を受けてやるよ。それで復讐を遂げられる見込みがあるならね)
己の弱さを認めても弱気になる必要はなかった。むしろ素直に認められてこそ、気分を入れ換えて強気にいくべきだ。
どんな手段をとっても、復讐を遂げる。今の彼女の思いはそこに集約された。
『ならば我、汝に助力をせん。そして、その助力の証として〈刻印〉を授ける。〈刻印〉、《鋼の狩人》を・・・・・・』
その言葉と同時にアポルトブルトの黄金の角が輝く。
まぶしい。そんな感覚がイーシャの脳裏を支配するが、それも一瞬のこと。次にはアポルトブルトの声が響く。
『これで汝に〈刻印〉は刻まれた』
(よ、よくわからないけど、これであたしは強い力を得たのかい?)
イーシャは半信半疑だった。
『普段はいつもの汝と変わりない。だが、汝が強く願えば〈刻印〉は発動する。あと、これを心せよ。〈刻印〉は汝にとって、本当の試練と感じた時点で使え。下手に乱用することは、汝の命を削るだけに過ぎぬ』
(いざという時ってことだね。でも、この〈刻印〉を使うとどうなるんだい。天変地異でも呼べるってのかい?)
『使った時にこそ、その真価がわかる』
その言葉を最後に、アポルトブルトの姿は薄らいでゆく。イーシャは慌てた。
(ちょ、ちょっと待った。まだ質問は終わっちゃいない)
『・・・・・・北へ向かえ。そこで汝と絆を共にするものが待つ』
心から響く声は止んだ。イーシャはそこで我に返る。
周囲では、いつのまにか葬儀が終わりつつある。
頭の中がぼんやりとした。自分は夢でも見ていたのか? どうも実感がわかない。
だが、心は妙に晴れていた。葬儀前と比べても、迷いはどこか消えている。
「北へ向かえ・・・・・・か。そこにあたしと絆を共にするものがいる・・・・・・」

イーシャは、一人つぶやく。
心は決まっていた。確かめてみるつもりだった。自分がみたものが、夢か現実かを知るためにも。
「それじゃあ、あたしは行ってくる」
イーシャはそれだけ告げると、馬に飛び乗った。
集落の老人たちが不安そうに見守るなか、彼女は馬の腹に蹴りを入れる。旅立ちの時はきたのだ。
馬は走りだした。彼女が乗るには少々大きめの葦毛の雌馬だ。
空は灰色の雲に覆われており、お世辞にもよい天気とはいえなかった。雨が降っていないことが幸いといえるが、この調子ではいつそれが崩れてもおかしくはない。
昼には集落を飛び出し、しばらく馬を走らせると、やがて夕暮れが近づいてくる。
北へ向かってひた走っているが、誰の姿も見えない。この広大なる草原において、いま存在している生き物は自分たちぐらいではないだろうか。そんな錯覚すら覚えるぐらいだ。
とにかく、今は北を目指すしかない。また、イーシャが仇と狙う〈赤い風の獣〉の集落にしても、北の方にある。
仮に絆を共にするものが現れなかったとしても、一人で向かうつもりでいる。それが、自殺行であったとしても、己の気持ちに正直であろうとすれば、そうするしかないように思えた。
そんな事を考えながらも、更に時は経つ。
そして、太陽がその姿を大地に消そうかという頃、イーシャは一人の人間の姿を見つけた。
その人間は、草原のど真ん中にポツリと立っていた。まだ、うら若い少女に見える。長い白金の髪が、風にさらわれて美しく煌く。整った顔立ちは、イーシャとは比較にならないぐらい魅力的だった。
少女は、じっとイーシャに目を向けている。イーシャは少女の近くまで寄ると、馬を止めた。
「あなたがイーシャさん?」
いきなり少女が訊ねた。鈴のように愛らしい声。
イーシャは戸惑いながらも「ああ」とだけ頷いた。
「良かった〜。違う人だったらどうしようかと思ってしまったよ。あっと、申し遅れました。私はティス。よろしくね、イーシャさん」
そう言ってティスと名乗った少女は、にこやかに手を差し出してくる。イーシャも馬から下りて、一応その手を握り返す。
「・・・・・・あたしの名前を知ってるって事は、あんたが絆を共にするものってこと?」
「うん! そうだよ」
場違いなぐらいに明るく、ティスは頷いた。
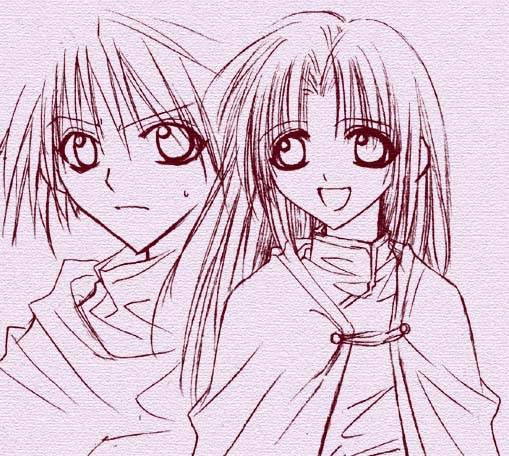
イーシャとしては多少調子が狂う。当初想像していた人物とは、完全に印象が異なるからだ。絆を共にするものというぐらいだから、もっと重々しいものを背負っている人物だと思っていた。だが、目の前の彼女からは、あまりそういう雰囲気は漂ってこない。どちらかといえば、脳天気そうに見えるのは気のせいか・・・・・・。
少なくとも、この島の住民ではなさそうだった。肌の色も白く、白金の髪をもった人間など、この島には存在しない。一応、たっぷりとしたこぎれいな長衣を纏い、腰には剣を吊るし、手には奇妙な輝きを放つ石が埋めこまれた杖をもっているが、その姿はお世辞にも似合っているとは言いがたい。
ティスは、まじまじと自分を見つめるイーシャの視線が気になったのか、首を傾げて訊ねた。
「どうかしたの?」
「あっ、いや。別に。・・・・・・それより、あんたは一人なの」
「そうだけど、何か問題でもあるの」
「特にないけど・・・・・・どうやってここまで来たのさ? 馬の姿も見えないけど、ひょっとして一人で歩いてきたとか?」
「うう〜〜ん。どうやって来たのだろう。私」
いきなり真剣に唸り出すティス。イーシャは力が抜けそうになった。
「おいおい。自分の行動も覚えてないのかい。あんたは」
「だって気付いたら、この場所に立っていたんだもん」
「つまりは何かい? 自分でも知らない内に、この場所に立っていたとでも言うわけ?」
「そうだね。まんま、そうなるかな。あははは」
(笑い事ではないだろうに)
イーシャは、げっそりとする。あるいは単にからかわれているだけか・・・・・・。
とはいえ、ティスがこの場にいるという理由も、〈聖宿〉の不思議な力でも働いているからだろうか。イーシャはそれを訊ねようとしたが、ティスに先手を越された。
「ねえねえ、イーシャさん。もうすぐ夜も来ることだし、今日はここで野営をして、お互いの交流を深めない?」
「あ? ・・・・・・そうだな」
イーシャは、つい頷いてしまった。
「わ〜い。そうと決まれば早速準備だよね。実を言うと、私、お腹ペコペコだったんだぁ」
はしゃぐティスを見て思った。
完全にあの子のペースにハメられていると・・・・・・。
しかし、時間があるのもまた事実だ。イーシャは黙って、野営の準備をすることにした。
月が雲に隠れて、薄暗い。
周りを照らすのは、小さな焚き火の明かりだけだ。
草原の夜は肌寒い。イーシャにとっては慣れているものだが、ティスという娘にしてはどうだろう。イーシャは、チラリとティスを覗き見た。
いらぬ気遣いだったかもしれない。彼女は先程焼けたばかりの肉を、美味しそうに頬張っている。その姿はとても脳天気そうに見え、緊張感のかけらも感じられない。
どうしてこの娘が、自分と絆を共にするものなのか、イーシャには疑問でならなかった。
部族の同朋を失い、悲痛な思いを胸に復讐に赴く自分。それに対して相棒は、明るく脳天気で、悲痛な思いとは無縁そうな少女。
やはり疑問すぎる。イーシャは、じっとティスを見つめたまま考え込んだ。
「どうかしたの。イーシャさん?」
イーシャの視線に気がついたティスが、キョトンとした瞳で訊ねてくる。
「・・・・・・別に何もないさ」
「だったらいいけど。一瞬、私が食べているものでも欲しいのかと思ってしまった。でも駄目だよ。これは私の物だもん」
「あのねえ。あたしはそこまで食い意地は張ってないぞ」
イーシャは溜め息をついた。このままでは、またティスのペースにのまれてしまうそうだ。
「ねえ、ティス」
思い切ってイーシャは声をかけた。
「ん? にゃに」
口をモゴモゴさせながら、ティスは彼女を見る。
「あんたも〈聖宿〉アポルトブルトって奴の助力を受けていんの?」
「ううん。私は違うよ。私は〈聖宿〉クミナレアリース様の助力を受けているから」
「クミナレアリース? 〈聖宿〉ってのは、他にも存在してるのかい」
「あれ、イーシャさん知らなかったの。〈聖宿〉にもいろいろあってね、今言ったクミナレアリース様以外にも、ラヴァルトレイス様やリリフティノア様とか色々といるんだよ」
少し自慢げにティスは言った。
「そうか。それは初耳だ。でも、そもそも〈聖宿〉っていうのは何なんだい?」
「ううむ。実は私も詳しく知らないんだぁ。へへへ」
またしても、イーシャは力が抜けそうになった。
「あんた、詳しいんじゃない訳?」
「そんなこと言ってないよ。第一〈聖宿〉って、大陸の学者の間でも解明しきれてない部分が多いんだから」
「じゃあ、あんたが知っている限りの事でいいから教えてくれる?」
「うん。いいけど、何から話そうか」
「あんたに任せるよ」
イーシャは投げやりに言った。
「じゃあ、まずは〈聖宿〉の存在意義について話すね。そもそも〈聖宿〉っていうのは、人間の成長を見定める存在らしいの」
「そういやアポルトブルトもそんな事を言っていたな」
「でね、人間ひとりひとりには、それぞれ何らかの〈聖宿〉がついていて、それらの導きの元に人生を送ってゆくの」
そこでイーシャは、ふと疑問に思った。
「それじゃあ、何かい? あたしたちの人生って〈聖宿〉の好き勝手に操られているって事?」
もしそうだとしたら、サリサや集落の仲間が亡くなったのも、〈聖宿〉の仕業とも言いかえられる。
「そこまではひどくないよ。たぶん」
「でも、導きの元に人生を送るんだろ?」
「それはあくまでも例えだよ。〈聖宿〉は普段の生活にまで介入はしてこないものなの。何らかの深い事情がある時だけ、その姿を現すらしいけど」
「・・・・・・深い事情ねぇ」
「残念だけど、私もこれ以上の説明はできないの」
申し訳なさそうにつぶやくティスに、イーシャはヒラヒラっと手を振った。
「別にいいよ。あまり期待はしてないしさ」
「・・・・・・それって何かヒドイ。もう少しくらいは期待してくれても」
「会ったばかりなんだし、何を期待していいのかもわかんないさ」
「だったら、もっと色々と話して交流を深めようよ」
「話よりも食い気に走っていたのはどこの誰だい?」
「ううぅ。お腹が空いていたのだから、仕方ないでしょ」
涙目で唸るティスを見て、イーシャは頭を掻いた。どうも自分から話していかないと、ロクな会話になりそうにない。それに自分から聞きたいことも色々ある。
「そういや、ティスはあたしの事情をどこまで知っているの?」
まずそれが知りたかった。これから同じ行動をとるにしても、目的が違っていては話にならない。
「とりあえず、イーシャさんの周りで起こった不幸は知っているつもりだよ。部族の人たちの仇をとるべく、北に向かっているんでしょ」
「ああその通りだ。でも、その復讐の旅の道連れが、どうしてあんたな訳。あんたもあたしと同じ仇でも追っているの?」
「私はイーシャさんの手助けをしてあげてってクミナレリース様に言われたの。あなたが私の助けを待っているからって」
「はあ? あたしは誰の助けも待ってなんかいないよ。復讐だって、そもそも一人でやり遂げるつもりだったのだから」
「そう言われてしまうと、私も困るのだけど。私はクミナレアリース様にあなたを助けるよう言われただけだもん」
「でも、そう言われてホイホイと助けにくるあんたって、相当のお人好しではない?」
イーシャのこの言葉に、ティスは少しムッとなる。
「困っている人を助けることは悪いことなの?」
「・・・・・・そうは言わないけど、限度ってものがあるだろ。大体、あんたこの島の人間ではないよね? 今までどんな生活を送っていたかは知らないけど、それらを放っぽりだしてまで助けにくる義理なんてないんじゃない」
少なくともティスは見た目、旅慣れた印象には見えない。武器などは身に帯びているものの、それらを扱えるほどしっかりとした体型にも見えなかった。更に言えば、サリサよりも頼りなげに見える。
「私は自分の意思でここに来たのだから、イーシャさんが気にすることでもないわ」
「そうは言ってもねぇ」
イーシャが呟いた矢先。
「・・・・・・少し静かにしてくれる、イーシャさん」
ティスが急に緊張した声をあげた。
「どうかしたの?」
訊ねるイーシャも、只事ではない何かを感じ取っていた。思わず剣をたぐりよせる。
「何か来るわ。私たちに害意をなそうとするものが」
「敵か?」
その答えは、言ったそばから示される。この野営場所に向かって、奇妙な姿のものが突っ込んできたからだ。
炎に照らされたその姿は、人の姿をした蛇。赤黒い鱗が不気味に照り輝き、その手には無骨な戦槌などの武器が携えられている。
「しまった、蛇人かよ!」
イーシャは言って、己のうかつさを呪った。考えても見れば、いま自分達がいる辺りは蛇人の生息地域だ。ティスとの出会いでそのことを失念していた。
だが、後悔したところでもう遅い。蛇人は彼女らの目の前にまで近づきつつある。その数は三匹。
幸いをいえば、“静かなる狩人”の異名をもつ蛇人の襲撃に、いち早く気がつけたことぐらいか。蛇人は足音をたてない。よって、本来ならば不意打ちを受ける危険性すら多かったのだから。
「ティス。無理はするなよ。やばくなったら、あたしの後ろに隠れてい」
剣を抜きながらイーシャは叫ぶ。
「私なら大丈夫。それよりもイーシャさんは自分の身を護ることに集中して」
「わかった」
とりあえず今はティスを信用することにする。それに自分も、これ以上のやりとりを交わしている余裕もなかった。
蛇人の武器がイーシャに対して振り下ろされるが、それはかろうじて剣で払いのけた。そして勢いあまった蛇人の脇腹に、蹴りを叩きこむ。これが普通の人間なら、相手は咳き込むなり、バランスを失って倒れることもあろう。
しかし、蛇人は頑丈だった。倒れることも咳き込むこともない。固い鱗に覆われた身体は、かえってイーシャの脚を痛めさせただけ。
イーシャが脚を痛めた状況を蛇人は見逃さなかった。再び戦槌を振り回し、今度はその攻撃が彼女をとらえる。
「くっ」
胴に重い痛みが走った。硬革鎧ぐらいは身につけているとはいえ、衝撃はかなりのものだ。朦朧として意識が飛びそうになる。
「イーシャさん、しっかりして!」
ティスの叱咤の声が上がる。ティスは二匹の蛇人を相手取りながらも善戦していた。彼女が白銀に輝く剣を振り下ろすたび、蛇人たちは確実に傷を増やしている。
どうやら相手の身を案じるよりも、自分の身を一番に心配するのがいいのは事実のようだ。イーシャはそう実感した。
だが、そう考える頃には蛇人の次の攻撃がイーシャをとらえようとする。イーシャはそれを避けるべく、どうにか身体を動かそうとした。しかし、身体の反応は一歩遅れる。
イーシャは観念して、攻撃の衝撃に耐えるべく歯を食いしばった。
しかし。
襲い来るはずの衝撃は、寸での所で止まっていた。見れば蛇人の腕はまっすぐに伸びきったまま硬直している。明らかに様子が変だった。そこへ、ティスの声が飛ぶ。
「そいつの腕はしばらく動かないわ。今のうちにとどめをさして」
何が起こったのかは理解できなかったが、好機であるのは事実だった。イーシャは剣を両手に構えると、うろたえる蛇人の喉元を一気に切り裂いた。
どす黒い返り血がイーシャを汚すが、そんなものは気にしていられない。イーシャは相手が完全に動かなくなるまで、剣を振るいつづけた。そして、しばらくもすると蛇人は完全に息絶える。
イーシャは肩で息をしながら、ティスの方を向き直った。彼女も蛇人を一匹は屠り、もう一匹を仕留めるのも時間の問題のように思えた。しかし、それよりも別に気がつくものがあった。
こちらに向かって、更なる蛇人の集団が近づくのが見えた。
「・・・・・・まずい」
イーシャはそう思うと、自分たちの荷物を持てるだけ担ぎ、馬に飛び乗った。そして手綱を操り、馬をティスと蛇人の間に割り込ませる。
「ティス、後ろに乗れ!!」
「うん」
ティスは蛇人がひるんだ一瞬の隙を見計らって、馬に乗った。
「いくよっ!!」
相棒が後ろに乗ったことを確認して、イーシャはかけ声と共に手綱を引く。馬は一気にこの場を走りぬけた。
とりあえずこのまま、蛇人の生息地は抜けきるつもりだった。月明かりだけを頼りに、馬は草原を疾駆する。
「はぁぁ。びっくりしたねぇ〜」
ある程度、落ちついてきたところでティスがのんきな感想をもらす。
「迂闊だったよ。蛇人の生息地域で野営しちまうなんてさ」
「助かったのだし、いいじゃない」
「あんた、のんきだねぇ」
イーシャは苦笑した。
「でも、少しは見なおしたよ。あんたって見かけによらず強いみたいだしね。蛇人の襲撃にもいち早く気がついたりして、危険を感じることにしても案外しっかりしているじゃない」
「あはは。それは魔法のおかげだよ。敵意あるものが近づくと、警告がとぶ結界を張っていたから」
「魔法。・・・・・・あんた、魔法使いだったの?」
「そうだよ。私、こう見えても聖都リメロフロイアの“真理の門”で学びを受けた純魔術師だからね。だから、結界を張ったり、イーシャさんが戦っていた蛇人の腕を拘束したのも、私の魔法の力なんだよ」
「そうか。それで納得いったよ。・・・・・・それにしても、“真理の門”の純魔術師とはねぇ」
この世界においては、魔法は誰もが学べる技術だ。その中でも、魔法の真髄を極めんとする学徒の集団は“真理の門”と呼ばれる学院に属し、研鑚を高めていくとイーシャは耳にしたことがある。純魔術師は、魔法に生涯を捧げたものの名誉ある称号ともいえる。
「意外そうな顔だね〜」
「まあね。純魔術師なんて、もっと年寄り連中の集まりだって想像していたから」
「純魔術師にも色々とあるんだよ。でも、私が純魔術師である証拠はこの“真理の杖”だね」
そう言えばティスは杖を持っていた。それには奇妙な輝きの石が埋めこまれていたのを、イーシャは覚えている。
「この“真理の杖”は、魔術の奥義を志す者のみに与えられる立派な杖なんだよ」
「そういや噂でなら聞いたことある。純魔術師は武器を帯びる事を禁止されるかわりに、その杖を授けられるんでしょ」
「うん。その通り」
「・・・・・・でも、待てよ。あんた、さっき思いきり剣振り回してなかった?」
イーシャは蛇人との戦いを思い出して、指摘した。
すると、ティスはチロッと舌を出して笑う。
「まあ、あれは特別ってこと。そもそも私が持つ剣は、〈聖宿〉クミナレアリース様に授かったものだもん。だから、使わないと損かなあって。それに魔力を帯びた道具を使うことは、“真理の門”の組合だって奨励していることだしね」
最後はいかにも、とってつけたような言い訳に聞こえた。
「じゃあ、あの剣は魔力を帯びた武器なんだ」
「おそらくね。でないと私も、あそこまで戦えないもの」
「どおりでおかしいと思った。あたしより非力そうなあんたが、やすやすと蛇人と渡り合っているんだもんね」
「まあ、足手まといにならないだけマシだと思ってよ」
「・・・・・・それもそうだな」
イーシャは言って、少し笑った。それを見て、ティスも柔らかい笑みを浮かべる。
「ようやく笑ってくれたね。イーシャさん」
「え?」
「だって、会った時は緊張していたし、会話もどこか固かったしね」
「・・・・・・そういや、そうだったな」
先程までは心を許していたつもりもなかったが、いつのまにか自然に話して笑っている自分がいる。
「ねえ。少しは私を認める気になったかな?」
ティスが後ろから、息がふれるほどに覗きこんでくる。
認めるかと聞かれると、まだ躊躇する部分はあったが、ティスのおかげで助かった部分もあった。イーシャはしばらく考えた後に、いま時点での答えを出した。
「とりあえずは、もうしばらくは一緒に行動してもいいと思う。その上で先のことは考える」
「・・・・・・ううん。まだ、警戒されている?」
「あたしはあんたと比べて、脳天気じゃないんでね」
イーシャはわざとらしく嫌味に言った。すると、予想通りティスはムッとふくれた。
「会ったばかりなのに、その言い方ってとても失礼ではない?」
「失礼なことを言うほど、気を許してるって解釈してほしいね」
「あ」
ティスは一瞬呆けた顔をしてから、大声で笑い出した。
「もう。イーシャさんって、意地悪なのだから」
パンパンと背中を叩くティスを見て、イーシャも苦笑する。少なくともこの素直さは、ある意味で好ましくは思えた。
「あんまり馬の上で暴れないでよ。振り落とされても知らないよ」
「あはは。ごめん、イーシャさん」
「それとあたしの名前を呼ぶときは、呼び捨てでいい。そのほうが気がねしない相棒っぽくていいだろ?」
相棒という言葉を聞いた時、ティスの顔は輝いた。そして、元気よく。
「了解! イーシャ」
頷いたのだった。
草原の夜に、二人の声が響く。それはとても明るい声。
一人よりも二人。それだけで、不思議と心強さは増すものだ。
二人を乗せた馬は、北を目指して走り続けた。
あとがき
「誓いと絆(中編)」をお届けします。今回はいよいよイーシャの旅が始まり、ティスとの出会いが書かれています。
あとはこの世界ならではの概念がいくつか説明されていくという(聖宿とか純魔術師やら)感じですね〜。まだまだ設定的なものはあるのですが、それは追々物語の進行に合わせて公開していくこととなるでしょう。
次の後編はいよいよ決戦です。イーシャの復讐は、どのような結末を迎えるのでしょうね。そして、その先にあるものとは・・・・・・。
とりあえずは、期待してもらえると嬉しいです。
あと設定などでよくわからないとか、もっと詳しく説明が欲しいなどという場合は、随時質問も受け付けています(笑)
SHORT STORYに戻る ホームに戻る