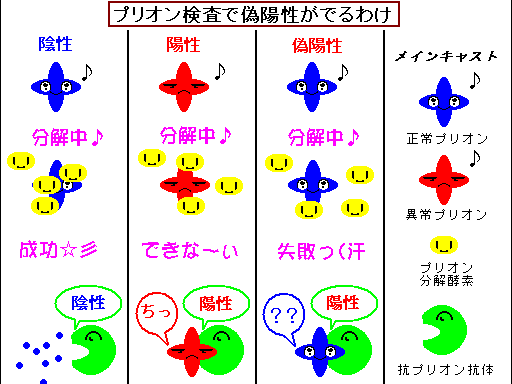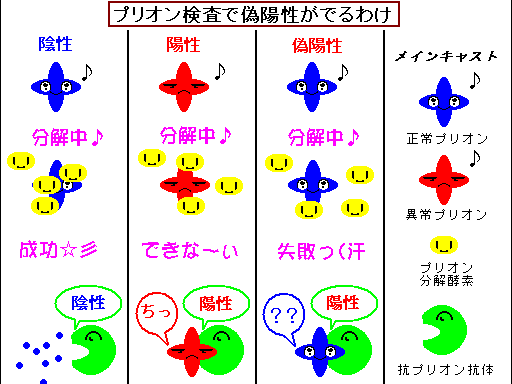狂牛病が発生して以来、肉処理時に狂牛病検査が行われるようになりました。
とちく場では、すべての牛を対象としたBSEスクリーニング検査を実施して、
この検査で陽性となった場合、国の検査機関に検体を送付し確認検査が行われま
す。
〈BSEスクリーニング検査〉
牛を解体した後、脳の一部(延髄)を採取し、ELISA(エライザ)法で異
常プリオンの有無を検査します。ELISA法は、抗原抗体反応を用いた検査法
のことで、色素のついた抗体を抗原の異常プリオンに反応させて発色させます。
牛の延髄から検査部分を取り乳液状にします。プリオンタンパク質分解酵素の
プロテアーゼKを用いて正常プリオンタンパクを分解します。抗プリオン抗体を
加えて、プリオンがあるかどうかを検出します。プレートに検査材料を入れ、発
色する抗体を加えます。色の濃さを機械で測定します。
これで異常プリオンが発見できます。
解体された健康な牛の延髄を使って、酵素免疫測定法 (ELISA)による検査の演
習を行った際、健康な牛から、狂牛病であるという陽性結果が検出されることが
あります。結局陽性ではなかったため、偽陽性という事になりました。その間、
解体中の牛肉の出荷停止などの混乱が起こりました。一次検査での偽陽性はその
後も起こりました。
偽陽性の発生のしくみ。
検査は酵素免疫測定法 (ELISA)を用いています。正常プリオンタンパクと異常
プリオンタンパクの判別は、プリオンタンパク質分解酵素のプロテアーゼKを用
いて正常プリオンタンパクを分解し、抗プリオン抗体を加えて、プリオンがある
かどうかを検出します。この時、プロテアーゼKによる正常プリオンタンパクの
分解が不十分であれば、抗プリオン抗体はプリオンと反応して陽性となってしま
います。
なぜ、偽陽性が発生するのかというと、完全に反応が行われていないためです。
検査は酵素反応であるため反応pHや温度などが最適でないことが考えられます。
とはいえ、反応温度は、50〜60℃、pHも厳密に合わせなくてもそんなに大
差はありません。おまけに、これらの検査薬品はキットになっていて、量や操作
方法はテキストに書かれていて、誰でも読めばできます。
にも関わらず、偽陽性が出るのは、検査するプリオンタンパクの量が多いから
と考えられます。試料の量が多すぎると、酵素がプリオンを分解しきれない、あ
るいは時間がかかるために、テキスト通りにならなくなります。
つまり、偽陽性が出る事は回避できないわけではなく、慎重に分量などを間違
えないでテキスト通りに進めていけば問題はないわけで、正確に慎重に行えば偽
陽性の検出は減らす事が可能です。
狂牛病であるのに関わらず陰性が出てしまい、その肉が流通してしまうよりは
ましですが。
さらに厳密にチェックするためにELISA(エライザ)法で偽陽性か陽性か
が出てしまったものについては、ウエスタンブロット法もしくは免疫組織化学検
査により、異常プリオンの有無を確認します。これで陽性が出れば狂牛病が確定
します。
現在日本では、速攻で陰性のものを除き、陽性・偽陽性のものを慎重に検査さ
れています。