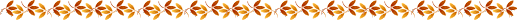Solo Pieces for
Contrabass
コントラバスのための曲
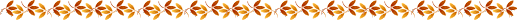 コントラバスは、オーケストラの中ではいつも他の人を支える仕事をしていて、
コントラバスは、オーケストラの中ではいつも他の人を支える仕事をしていて、
自分が主旋律を弾く事はあまりありません。
それがバスの本分ですし、一番の持ち味ですから。
でも、たまにはソロも弾きたくなるもの。
このコントラバスの低音を生かしたソロ曲はいくつか作られています。
(たいていは本職のバス弾きが書いたもの)
とは言えやっぱり曲数が多いとは決して言えないので、
他の楽器のための曲をアレンジして弾くことも多々あります。
そういう「コントラバスで演奏されている曲」を、
ここではいくつか紹介してみようと思います。
 >コントラバスのために書かれた曲<
協奏曲
G.ボッテジ−ニ(1821〜1889):協奏曲第1番/第2番
ジョヴァンニ・ボッテジーニは、
>コントラバスのために書かれた曲<
協奏曲
G.ボッテジ−ニ(1821〜1889):協奏曲第1番/第2番
ジョヴァンニ・ボッテジーニは、
150年ほど前にソリストとして大活躍した、イタリア出身のコントラバス奏者。
「歴史上3大コントラバス奏者」のひとりに数えられ、
グランド・オペラ華やかなりし頃、演奏、作曲から指揮まで幅広く手掛けていました。
(ヴェルディの「アイーダ」の初演を指揮したのは、実はこの人。)
彼の作品は数多く残っていますが、非常に技巧的な、いわゆる「難曲」の多い作曲家です。
この2つの協奏曲も例外ではなく、全コントラバス曲の中でも
かなり高いレベルに属していて、ソリストは苦労を強いられます・・・。
 S.クーセヴィツキー(1874〜1951):協奏曲、Op.3
セルゲイ・ク−セヴィツキーはロシア出身のコントラバス奏者、
S.クーセヴィツキー(1874〜1951):協奏曲、Op.3
セルゲイ・ク−セヴィツキーはロシア出身のコントラバス奏者、
彼も後年はアメリカに渡って指揮活動を展開。
たぶん、ボストン交響楽団の指揮者としての方が有名でしょう。
彼は小品を数点(下項参照)と、このコンチェルトを残しています。
暗く激しさのある第1楽章、リリカルに歌い込む長調の第2楽章、
第1楽章の再現から始まる第3楽章の3つからなりますが
各楽章に切れ目はなく、全曲通して演奏されます。
 C.D.v.ディッタースドルフ(1739〜1799):協奏曲
カルル・ディッタース・フォン・ディッタースドルフは、
C.D.v.ディッタースドルフ(1739〜1799):協奏曲
カルル・ディッタース・フォン・ディッタースドルフは、
ウィーン古典派時代のオーストリア人作曲家。
本人はヴァイオリン奏者でしたが、このコントラバス協奏曲の他にも、
ヴィオラやオーボエのための協奏曲、室内楽曲など
かなりの数の作品を残しています。
しかし、現在ではほとんど忘れられてしまっています。
この曲は、コントラバスを専門に勉強する人は
必ずと言っていいほど弾く曲です。
第1楽章の中に、ボウイング、フレージングを始め、
非常に幅広い技術を要求されます。
曲想は非常に明るく、「あっけらかん」と言う言葉が
なんとも似合ってしまう雰囲気です。
この曲の第1楽章を聞くと、その1曲だけで
奏者の技術や音楽性が分かってしまうため、
ほぼ全世界のオーケストラが、
バス奏者の入団オーディション課題として使用しているとか。
 小品・組曲
小品・組曲
(数が多いので私の好みで選曲)
G.ボッテジ−ニ:エレジ−(哀歌)
上記のボッテジーニによる短い小品。難曲が多いとは書きましたが、
この曲は歌曲のような柔らかい歌が印象的。
「哀歌」と言っても短調の激しい哀しみではなく、
どちらかと言うと過去への回想を思わせるような、長調の穏やかで優しい曲。
「郷愁の歌」と表す人もあります。
(ボッテジーニは非常に広範囲で活躍し、故国を離れる事が多かった)
作曲者本人もこの曲を非常に愛し、
自身のリサイタルでもこの曲はプログラムから決して外さなかったとか。
 S.クーセヴィツキー:小さなワルツ
クーセヴィツキーが書いた4つの小品の中の一つ。
S.クーセヴィツキー:小さなワルツ
クーセヴィツキーが書いた4つの小品の中の一つ。
ワルツと言ってもウィンナ・ワルツのように大規模な舞踏会ではなく、
ちょっとおしゃれした人たちがくるくると踊っているようなかわいらしい曲です。
 L.グリエール(1875〜1956):タランテラ
レインゴリト・グリエールは、ベルギー系ロシア人作曲家。
L.グリエール(1875〜1956):タランテラ
レインゴリト・グリエールは、ベルギー系ロシア人作曲家。
ロシア国民楽派を継承し、またアゼルバイジャンなど
東方の民俗音楽を作品に取り入れるなど、
ソヴィエト音楽の発展に多大な貢献をした人で、バレエ「赤いけし」は有名。
また、プロコフィエフやハチャトゥリアンなど、
旧ソ連を代表する作曲家を育てた名教師でもあります。
グリエールは1905年、ベルリン留学中に
クーセヴィツキーと親しくなり、彼のために4つの小品を残しています。
いずれもコントラバスの性能を存分に発揮できるように作られ、
殊にこの「タランテラ」は「現在この世で最も難しいコントラバス独奏曲」と
言われるほどの難曲。
テンポが速く、左手が指板の上を走り回る(!)ように見える曲です。
 H.フリーバ(1899〜1986):無伴奏コントラバス組曲
「無伴奏組曲」というとかの有名なバッハによる
H.フリーバ(1899〜1986):無伴奏コントラバス組曲
「無伴奏組曲」というとかの有名なバッハによる
ヴァイオリン、チェロのための曲が真っ先に浮かびますが、
これは正真正銘コントラバスのための無伴奏曲。
ハンス・フリーバは、スイス・ロマンド管弦楽団の
首席コントラバス奏者をつとめていた人。
正式名「古い形式による組曲」の通り、バロック時代の慣例に倣って
プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、ジーグの
6楽章からなっています。
形式だけでなく、音型やリズムもバロック時代の音楽そのもので、
曲を聴いた限りでは、20世紀に作曲されたとは信じられないくらいです。
また、フリーバはこの曲で様々な演奏技巧を追求しているので、
演奏難度は非常に高いです。
 >他の楽器の曲からアレンジされたもの<
小品
>他の楽器の曲からアレンジされたもの<
小品
(これはほんとに多数あるのでほんの一部)
N.パガニーニ(1782〜1840):モーゼ幻想曲
ニコロ・パガニーニは言わずと知れたヴァイオリンの名手。
彼の曲は技巧の多用で知られています。
その彼の作品をコントラバスで・・・!?とお思いかも知れませんが、
実はこれ、けっこうメジャーなコントラバス曲になってしまっています。
曲そのものは、ロッシーニのオペラ「エジプトのモーゼ」のメロディを
技巧を凝らしてヴァリエーションに仕上げてあるもの。
 C.サン=サーンス(1835〜1921):白鳥
これは言うまでもなく、超有名なチェロとピアノの曲。
C.サン=サーンス(1835〜1921):白鳥
これは言うまでもなく、超有名なチェロとピアノの曲。
ソロをコントラバスに取り替えるだけで、
また違った味わいが出ていいものですよ。
ちなみにこの「白鳥」、もとは「動物の謝肉祭」と言う組曲の中の一つですが、
この組曲にはコントラバス独奏とピアノのためのオリジナル曲もあります。
タイトルは、「象」。
重た〜い象が、メンデルスゾーンやベルリオーズの
「妖精の踊り」(すごく軽やかな曲)を踊る、と言うもの。
 S.ラフマニノフ(1873〜1943):ヴォカリーズ
ヴォカリーズとは、「歌詞のない歌曲」の意味。
S.ラフマニノフ(1873〜1943):ヴォカリーズ
ヴォカリーズとは、「歌詞のない歌曲」の意味。
文字どおり、もとは声楽曲。短調で、情感たっぷりに歌い上げます。
ところで、この曲には面白いいきさつがあります。
ラフマニノフは、もともとこの曲を「コントラバス独奏」用に書いたんだそうです。
奏者として考えられていたのは、同じロシア人のクーセヴィツキー。
ところが、いよいよ曲を発表する段になってこの二人が口論してしまい、
ラフマニノフは、結局この曲をヴァイオリン用として発表、
後にソプラノ用も出版されました。
でも、この曲が本格的に有名になったのは、
当のクーセヴィツキーがオーケストラ編曲し、
彼が指揮していたボストン交響楽団が演奏するようになってからだったとか・・・。
 (番外編:こんなのを弾いてる人も・・・います)
A.ドヴォルジャーク:チェロ協奏曲
N.A.リムスキー=コルサコフ:熊ん蜂の飛行
P.de サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン
(番外編:こんなのを弾いてる人も・・・います)
A.ドヴォルジャーク:チェロ協奏曲
N.A.リムスキー=コルサコフ:熊ん蜂の飛行
P.de サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン
 「Contrabass」メインページへ
「Contrabass」メインページへ