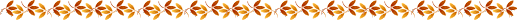C o n t r a b
a s s
i n
O r c h e s t r a
私たちの真骨頂
またはあるバス弾きの呟き
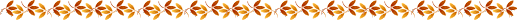 −オーケストラの中でのコントラバスって、メロディもないけど、どうして大事?−
例えば、家を作ろうと思ったとするよね。
そしたら、まず土台と柱が要る。
どんなに屋根が綺麗にできてても、可愛い出窓があっても、
それしかなかったら崩れちゃうでしょ。そういうこと。
ー私が高校生だった頃、あるコントラバス奏者が語ってくれた事ー
−オーケストラの中でのコントラバスって、メロディもないけど、どうして大事?−
例えば、家を作ろうと思ったとするよね。
そしたら、まず土台と柱が要る。
どんなに屋根が綺麗にできてても、可愛い出窓があっても、
それしかなかったら崩れちゃうでしょ。そういうこと。
ー私が高校生だった頃、あるコントラバス奏者が語ってくれた事ー
 コントラバス。
コントラバス。
見たままかもしれませんが、おおよそ独奏用に作られた楽器とは思えません。
その通り、彼等の巨大さは、
ひたすら「アンサンブルに参加するため」に発展したもの。
西洋音楽は、「低い音」と言うものを非常に重要視します。
100人近い人数を抱えるオーケストラから弦楽四重奏まで、
俗に言う「合奏」をしようとすると、
必ず「低音域」を扱う役割が必要になります。
それを土台にして、高音域のメロディが作られているからです。
それが、西洋音楽が作られる根本原則なのでしょう。
ところで、日本音楽には、
例えばコントラバスとかチューバだとか、
ああいう極端に低い音が出て来る事はありません。
(善し悪しの問題ではなく、そういう文化であるだけのことです)
上にも書いた通り、オーケストラは
大規模なものになると100人近い人数になります。
その団員それぞれが異なる楽器でいろいろな音を
いっぺんに出すわけですから(もちろん楽器ごとの人数差はあるにせよ)、
誰かが土台になっていないと高音ばかりでは安定しないわけです。
それをやるのが、コントラバス。
チェロも時には似たような役割をしていますが、
彼ら以上に「他の人を支える、他の人が歌いやすいようにする」事に
徹してしまったのが、コントラバス。
自分がメロディを綺麗に歌う事よりも、
他の楽器がそれぞれの持ち味を最大限に生かして
交代で主役を張っている間中、それを支えている事、
それを逆に自分の持ち味にしてしまったのが、コントラバスと言う楽器。
メロディを弾かないと、主役になれない・・・
誰か、そんな事言った?
オーケストラの演奏を何度か聴いた事のある人ならお分かりと思いますが、
一度、「低音のないオーケストラ」と言うのを想像してみて下さい。
実際に聴いた事のある方はないでしょうけど。
(こう書いている私も、実はありません)
・・・どうでしょう。なんか、軽すぎて変じゃありません?
いくら主旋律が綺麗でも、高い音ばかりだと、すごく浮いてしまうと思うんです。
そうならないように下からずっと持っているのが、コントラバスの仕事。
つまり、どんな楽器でもほとんどの場合は
「自分一人が歌っている」のではなくて、
実は「コントラバスと一緒に歌っている」、のです。
オーケストラの、あの深みのある響きは、
コントラバスが作っていると言っても過言ではないのです!
・・・と、私は思います。
「他人を支える」ことにも、
またそれにしかない楽しみや喜びがある。
だから、コントラバスって面白い。
私の知人に、音楽を「風景画」に例える人がいます。
何もない紙の上に、いろいろな音色という絵の具を使って絵を描くわけです。
コントラバスが描くのは、「当たり前すぎて目に付かないもの」。
他の人よりも2倍(contra)低い音(bass)で、
音の風景の「大地」や「空気」を描いて行く。
草原だったり、花だったり、海だったりは、他の人が描いてくれる。
でも、「そこにある事が前提」なものは、バスが作る。
取り立てて目には付かないけれど、確かに存在するもの。
それが、オーケストラのコントラバス。
 ・・・まあ長々と書きましたねえ・・・
私が常日頃から思っている事を、この際なので書いてみました。
こんな独り言に付き合って下さった皆さん、ありがとう。
・・・まあ長々と書きましたねえ・・・
私が常日頃から思っている事を、この際なので書いてみました。
こんな独り言に付き合って下さった皆さん、ありがとう。
 「Contrabass」メインページへ
「Contrabass」メインページへ