| ア ス ト ロ ラ マ の エ ピ ソ ー ド |
| 【今アストロラマは見られないのか】 |
| これから先、直径30mのスクリーンで映像を見ることは、まず出来ないでしょう。理由は、 |
| 大勢の観客が常に入るとは思えないし、常設館としては、商売にならないと考えるからです |
|
| 【アストロラマの収容人数は】 |
 |
| 大阪万博で直径40〜50mのスクリーンを採用していれば、もっと多くの観客 |
| にアストロラマを見てもらえたのに残念です。(計算上の定員を30mで1000 |
| 人とするならば、40mで約1800人、50mで約2800人になります。)オープン |
| 前の実験で、みどり会関係者の協力を得て約2000人入れたことがありまし |
| た。寿司詰めでよければ、更に入るはずです。 |
| もっとも、当時そこまで映像を拡大するには、技術的にも解決しなければならない問題 |
| (特に明明るさや揺れ対策)がありました。それよりも、コンパニオンの皆さんの苦労は、 |
|
もっともっと増えていたと思います。
|
|
| 【ドームの外周は100m】 |
| 各映写室の状態を見て回って、コントロール室に戻ってくると、1回で約100m歩き(走り) |
| ました。トラブルがあった時は、コントロール室から走って行きますから、右回りを選ぶか |
| 左回りを選ぶかをとっさに判断しないと、走る距離はかなり違うのです。 |
|
それが、もし50mスクリーンだったら、1周が約150mですから、もっと大変になります。
|
|
| 【残念だったこと】 |
 |
| 我々は毎日、毎日いやと言うほどアストロラマを見ましたが、 |
| 世界中でわずか600万人(万博総入場者の1割)の |
| 人にしか見せられなかったのも、残念なことでした。 |
|
| 【素晴らしかったこと】 |
| アストロラマで誇りに思って良いことは、期間中に1日中映写出来ないという日が、皆無だっ |
| たことです。開始時刻が遅れたことや、5台のうちの1台が映写できなかったトラブルは |
| あったが、ままあそのくらいは大目に見てもらいたいですね。そのような快挙が実現した |
| のも、裏方の目に見えない努力があったからです。 |
| 今思えば、かなり綱渡り的な事をしていた時期もあったのです。 |
|
| 【トラブル1】 |
| 光源のキセノンランプの寿命が実に不安定で、始めは5Kwの水平点灯タイプを使用 |
| していたのですが、100時間もしないうちにエアーが入ってしまうことが度々で、 |
|
結局3,6Kwの水平点灯タイプに変更してしまいました。
|
| 開発中のランプを採用し、製造技術がまだ安定していなかったのが原因でしたが、 |
| 会場全体が実験室みたいなところがありましたので、ある程度の冒険は |
| 許して頂けたのではないでしょうか。上映中に、急に1画面だけ暗くなって、 |
|
うっすらと映像が見えていたのを経験された方もいらっしゃると思います。
|
| そんな時、コントロール室では、新しいキセノンランプを用意し、トラブルのあった映写室 |
| で上映が終わるのを静かに待っていて、次の回の上映が始まるまでにランプの交換をして |
| いたのです。そして次の回には、何もなかったような顔をしてコントロール室に引き上げた |
| ものです |
|
| 【トラブル2】 |
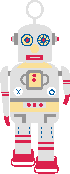 |
| 映写機そのものも時々動かなくなり、夜中に徹夜でヘッドマシン |
| を交換したことが何回かありました。 |
| 前日は1画面だけ映像が映らなかったのに、翌日来てみたら |
| ちゃんと映っていたなんてこと、覚えていませんか。 |
| そんな時、誰かが徹夜で修理していたのです |
|
|
| 【トラブル3】 |
| フィルムそのものも、たまには切れました。今だったら切れにくいPET(ポリエチレン |
| テレフタレート)ベースを使えるのですが、当時はTAC(トリアセテートセルロース) |
| ベースしかなかったので、まあしかたないかな。 |
|
| 【70mmフィルム】 |
| あまり知られていないのですが、大阪万博当時は、日本で70mmフィルムの処理が出来 |
| なかったのです。需要がないから現像所も設備しなかったのです。 |
| そこでアストロラマは35mm8Pフィルムで撮影し、アメリカで70mm8Pに焼付けしたのです |
|
(この辺りは、相原さんが苦労したところです)
|
| 日本で70mmフィルムの現像とプリントが出来るようになったのは、 |
| なんと15年も後の筑波科学万博の時なのです。 |
|
| 【音響機器】 |
| 音響機器の方はトラブルがなかったのか、私はあまり知らないのですが… |
 |
| 期間中に音が出なかったことは皆無でした。これも、影でメンテナンスを |
| していたのかな。後から思うのですが、画と音がずれたなんて話は |
| 一度も出なかったですね。 |
| これは、それなりに自慢して良いことだと思います。 |
|
| 【画と音の同期】 |
| 一般の映画は、フィルムに音が焼き付けられているので、画と音がずれることはありませんが、 |
| アストロラマでは、画と音は、それぞれ別のモーターを使っており、各々が電源周波数に同期し |
| ているだけだったと思います。 |
| テープは1インチ幅の16トラックで、1トラックを同期信号に使っていたと思います。スタートも同 |
| 時スタートだったので、今思えばよく画と合っていたものだと思います。 |
| 今だったら、テープ側に同期信号を入れて、その信号で映写機のモーターを制御することも出来 |
| るのに…。 |
|
| 【アストロラマは半球か】 |
| ところで、一般に180°の画角を持つレンズを魚眼レンズと言いますが、魚眼レンズを真上に向 |
| けて撮影したら、我々が普通に見ている景色がすべて撮影されるでしょうか?直感的には出来 |
| そうですが、実際にやってみるとびっくりします。 |
| 道路の見えない街、足のない人間…。そうなんです、レンズから下の景色が写っていないので |
| す。レンズから上だけで180°なのだから、当然です。もし道路まで写すのであれば180°より |
| 大きい画角のレンズが必要になります。 |
| そんな理由でアストロラマは220°の画角にしたのです。アストロラマを半球スクリーンと思って |
| いる人も居ますが、実際は220°の欠球だったのです。 |
|
| 【目の錯覚】 |
| もう1つ、私がびっくりしたことがあります。それは、魚眼レンズを通して景色を見るとほとんどが |
| 空になってしまうことです。建物とか人物というものは、水平からせいぜい5°か10°しかなく、 |
| 残りは空なのです。これは、目の錯覚と言うより、我々が水平以下の部分(足元とか道路)の情 |
| 報をいっぱい取り入れていて、どちらかと言うとうつむき加減で景色を見ているためだと思います。 |
| もしスクリーンの水平線から45°近くに建物を映写しようと思えば、 |
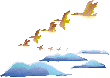 |
| カメラを建物に近づけるか、カメラを建物の方へ傾けるしかないのです。 |
|
| 【アストロラマの工夫】 |
| そんな訳で、せっかく作ったアストロラマで、空ばかりをお客さんに |
| 見せるわけには行かないので、演出の立場からも苦労があったものと思います。 |
| 5面が別々の映像であったり、5台の蒸気機関車が迫って来たりして、見事に解決していました。 |
| もちろん、つながった画面でも、たとえば埴輪が周囲に並んでいて時間変化が影の動きで |
| 分かるシーンや、原生林に全体が包まれたシーン、ヨットの帆が空をおおっているシーン等々 |
| ドーム映像でなければ表現出来ない素晴らしいシーンでした。 |
|
| 【必要な邪魔者】 |
| 撮影時のもう1つの悩みは、太陽でした。カメラの足元を除く全ての景色が撮影されると言うこと |
| は、画面の中に太陽が入ってしまうということです。太陽が入ると眩しいだけでなく、ハレーション |
| が出たり露出が合わなかったり……。そこで考え出されたのが、太陽を何かの影に入れてしまう |
| 方法です。例えば、木の影や建物の影。言い換えればカメラを何かの影の中に置く方法です。 |
| この方法が使えないシーンもありました。車で移動するシーンです。これは、太陽が写っていた |
| り、大きなハレーション(六角形の絞りの形がいくつもつながって、ちょうど連ダコのように見え |
| た)があったりしましたが、それよりも全体の臨場感に気を取られてしまって、あまり気付かなか |
| ったのではないでしょうか。 |
 |