|
科学哲学ニューズレター |
![]() No.17, May 1997
No.17, May 1997
Book Review: Soshichi Uchii, "Akira Tonomura's Seeing Gauge Fields, Koudansha, March 1997"
New Junior Students
Our Activities in 1996
書評
外村 彰 『ゲージ場を見る』講談社ブルーバックス、1997年3月刊。
著者外村氏は、電子線を使った機器の開発と、それによってミクロの世界の実態を明らかにする数々の重要な実験結果を明らかにしてきたこととで知られる実験物理学者である。例えば、本書の表紙に使われている写真は、電子線を使った干渉顕微鏡によって量子力学における「アハラノフ・ボーム効果」の決定的な検証を行なったもの(1986年)であり、著者の代表的な業績の一つである。
という、ここまでの短い紹介ですでにいくつかの難解なコトバが出てきており、「素人にはむずかしい本だ」という第一印象を受ける読者が多いかもしれない。しかし、本書はこの第一印象よりははるかに読みやすいし、むずかしいにしてもそれだけ読みがいのある見事なできばえの本である。外村氏の技術開発や実験の苦労話を縦糸に、現代のミクロ物理学の重要な話題を横糸にして織りなされ、読み進むうちに、量子力学の基本的な考え方へ、電子線の干渉の原理やホログラフィー(波紋のような模様が写ったフィルムにレーザー光を当てると物の立体像が見えるようにする技術)の原理へ、ファラデーやマクスウェル以来の電磁気学の概念から現代のゲージ理論へ、またひところマスコミをにぎわした「超伝導」現象の理論的説明などへと読者をいざなってくれる。

この本は、こういった点で有益であるだけでなく、科学哲学の基本問題の一つである「理論と観察」というテーマについて刺激的な題材を提供してくれる点で、とりわけ評者の好奇心を駆り立てた。物理学実験によって「何が」見えるか、電子顕微鏡やホログラフィによって何が「見える」のか。理論的対象の「存在」はどのようにして確認されるか。著者外村氏は科学哲学者ではないのでこういった問題に関する哲学的分析を展開しているわけではない。しかし、そのための具体的題材は本書のうちにふんだんに提供されており、「現場の物理学」に即した哲学的考察のまたとない機会が得られる。以下、評者の考察を少々展開してみたい。
光学顕微鏡で何が見えるか。光が電磁波の一種であることはたいていの人が知っている。そして、光は電磁波のなかでは比較的波長が長い。したがって、可視光線を使った顕微鏡にはこの波長の長さによって解像力の限界が生まれる。例えば、黄緑色の光は波長が約0.5μm(マイクロメートル、ミクロンとも呼ばれ、μm=10の-6乗m)。したがって、このサイズより小さな対象はこの光では識別できないことになる。つまり、光学顕微鏡を使った「観察可能性」の限界はこの周辺に設定される。倍率でいうなら、約2000倍である。
電子顕微鏡の発明はこの限界を改善し、「観察可能性」を拡大した。これに先だって、電子線が波の性質を持つということが実験的に確認されたのは1927年のことである。そして、電子線の波長は光に比べてきわめて小さい。可視光線の約十万分の一であるから、単純に倍率に換算すると、光学顕微鏡の2000倍の十万倍になるはずで、二億倍まで倍率を上げられそうだが、いろいろと制約があって実際には約二百万倍のあたりだそうである。ちなみに、電子線やγ線の波長は10のマイナス2乗nm以下(nm
はナノメートルと読み、1nm= 10のマイナス9乗m)、X線10のマイナス3乗nm 〜10nm、可視光線400nm 〜800nmというスケールである。
さて、「観察可能性」が拡大したと言ったが、これは正確にはどう解釈すべきなのだろうか。最近の科学哲学でこの「観察可能性」の問題を取り上げたファン・フラッセンの議論を手がかりにして少し考えてみよう。『科学的世界像』(原書1980、邦訳1986)で展開された彼の基本的な考えは、科学の目的は実在の隠れた構造を見いだすことではなく、現象に合致するようなモデルを構成し、観察可能な現象をそのモデルの部分構造として埋め込むことができるような理論を作ることだというものである。この考え方は「構成的経験論」と呼ばれる。何が観察可能かは、かつての論理実証主義の正統的な見解のように理論から独立に決まっているのではなく、われわれ人間にとっての観察可能性は、それ自身経験的問題として科学的探求の対象となる。しかし、ファン・フラッセンにとって、観察可能な命題は真偽が言えるので、科学理論を受容する際の認知的な側面に関しては最も重要な基準を提供する。すなわち、ある科学理論を受け入れるときにわれわれが認知するのは、その理論が示すモデルの観察可能な部分が真であるということである。理論のそれ以外の部分には別種の長所や多くの実用的メリットはあるかもしれないが、それが文字どおり真であることまで認めるわけではない。
この抽象的な考えを、外村氏の具体的な成果に照らしてできるだけわかりやすく展開してみよう。簡単に言えば、外村氏の成果とは、物理学で理論的に予測された効果(例えば、後述のアハラノフ・ボーム効果)を写真で見える形にして確認できるようにし、それが観察可能であることを経験的に示したということである。外村氏の成果が得られる以前には、量子力学におけるアハラノフ・ボーム効果の実在性については賛否両論があった。アハラノフ・ボーム効果がどのような現象であるかは、本書で詳しい説明があるので参照していただきたいが、簡単に言うと、電場も磁場(これらが物理的な効果をもたらすことは疑問視されない)もなく、ただ「ベクトル・ポテンシャル」(ゲージ場)と呼ばれる抽象的な場しかないところを通る電子が物理的な影響を受ける、という現象である。「物理的な影響を受ける」とは、何らかの形で観察可能な現象として検出できるということである。もちろん、その検出を行なうためには、量子力学の理論を使って入念な実験装置を考案し、それを技術的に実現しなければらない。つまり、ミクロの領域で、普通の観察手段では検出できなかった過程の結果を、普通の手段で確認できる(つまり、観察可能性については疑問の余地のない)形にまでもってくる、というのが検証の課題なのである。太字の部分がまさに外村氏の業績の本質的な部分で、そのために何年にもわたる工夫と技術開発が行なわれたのである。
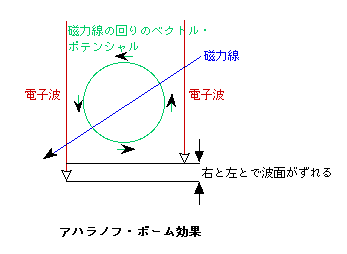
ファン・フラッセンが強調する「観察可能性」の基盤はまさにこの太字の部分にある。しかし、彼の構成的経験論の立場では、「アハラノフ・ボーム効果」の検証から、「ベクトル・ポテンシャルないしはゲージ場の存在」を結論してはならない。科学哲学の分析になれていない人は、素人であろうが物理学の専門家であろうが、このギャップをすぐに飛び越えてしまいがちである。アハラノフ・ボーム効果のようなミクロのレベルでの現象が観察にかかるというとき、図式的に書けば次のような多くのステップが背後に控えていることに注意しなければならない。
ミクロの現象 ⇒ 電子線の干渉像 ⇒ 光学的な像 → 肉眼で観察可能
しかし、⇒の部分には幾重にもわたる一般化や理論的前提がはいる。しかも、「アハラ ノフ・ボーム効果」は「ベクトル・ポテンシャル」あるいは「ゲージ場」を仮定する理 論からの一つの帰結にすぎない。したがって、前記の図式を仮定した上で「アハラノフ ・ボーム効果」の観察可能性が確立されたと認めても、これは「ゲージ場」そのものの 観察可能性を認めることには必ずしもならないし、その「存在が確立された」ことにも ならない。ある理論的過程や対象の「存在」を言うためには、その存在を確認するため にはどういう基準が満たされなければならないかという観察可能な条件を示さなければ ならない。したがって、ファン・フラッセンの構成的経験論の立場では、「ゲージ場の 存在」と「アハラノフ・ボーム効果の検証」との間にはまだギャップがある。
では、外村氏はこのギャップをどのようにして乗り越えるのだろうか。実は、この点が 本書では一番説明の不備な点ではないだろうか。本書の山場とも言うべき第六章で、ベ クトル・ポテンシャルからゲージ場への歴史的変遷が説明された後、次のような一文が この点を示唆するのみである。
この "ゲージ場の理論" にとって、AB[アハラノフ・ボーム]効果は、大変重要な意味を持つことになる。なぜなら、AB効果は「ゲージ場の実在性を直接示す現象」だからである。(p.142)
「実在性を直接示す」という表現に評者は直ちに引っかかった。好意的に解釈すれば、 これは「ゲージ場が実在するとすれば、最も明瞭な形で観察可能になるはずの現象」と いう意味であり、まさにそのクリアーカットな観察可能性が「存在の最も有力な証拠に なる」というくらいの意味であろう。しかし、「示されるべき存在」とそれを「示す証 拠」とのギャップはきちんと区別した上で議論が行なわれたほうが、説得力が増したで あろうし、読者にもよりわかりやすかったと思われる。いずれにせよ、「直接」という 言葉は「観察可能性との強いつながり」と理解してはじめて、前述の引用文には説得性 が生まれるのであろう。
科学哲学に対して、物理学者をはじめとする科学の専門家や彼らの見解の尻馬に乗った 一部の科学哲学者から「現場の科学を忘れるな」という苦言がしばしば呈せられる(例 えば、並木美喜雄「量子力学の哲学的議論のために」『科学哲学』28、1995)。こういった苦言にはもちろん傾聴すべき点も少なくないが、もし、こういった苦言が意図しているのが、「物理学者はその道の専門家なのだから、彼らの見解に合うように科学哲学をやれ」というメッセージであるのなら、科学哲学者はそのようなメッセージは断乎として叩かなければならない。すぐれた物理学者や実験家が、自分たちの出した成果や結果の哲学的な解釈(例えば、量子力学の「コペンハーゲン解釈」)についても正しいとはかぎらない。これは、著者外村氏を批判しているのではないことをお断りしておく。ただ、著者が一般の読者向けにわかりやすく説明した言明が、(不注意な読者によって)無批判に字義通り(あるいは、むしろ意味をよく考えずに)理解されると、前述のギャップを無視した安易な解釈に受けとられやすいことを注意したまでのことである。
電子線を使った検証写真が真正な「アハラノフ・ボーム効果」の現象を捉えていることを保証するために著者たちがいかに周到に試験片を作り、いかに周到な実験計画を立てたかは、著書のいろいろな部分から伝わってくる。それと同様の注意が、こういった検証結果が正確に「何の」検証であり、「何を」確立したかの解釈にも必要である。このような問題を考える評者にとっても、この本はきわめて刺激的で有益な素材を提供してくれた。(内井惣七)
○新専攻生
(大学院生は本年度入学はなし)
三回生
金田明子 論理学関係に興味。
瀬戸口明久 理学部を卒業して学士入学。生命科学の歴史に関心。
○1996年度研究室活動記録
4月19日 新入生歓迎会
4月 伊藤(和)「マルピーギの医学論」、『日本医史学雑誌』第42巻第1号
伊藤「運動物体の衝撃力をめぐって―ガリレオ・トリチェッリ・ボレッリ―」、『京 都大学文学部紀要』、第35号
5月 内井『進化論と倫理』世界思想社
5月23日 S.Uchii, "Darwin on the Evolution of Morality", International Fellows Conference,Center for Philosophy of Science (Univ. of Pittsburgh), Castiglioncello, Italy
6月8日 内井「数学と経験」、シンポジウム、日本経営数学会、関西学院大学
6月21日 『科学哲学ニューズレター』14号
6月22-23日 伊藤「フラカストロの伝染理論」、第97回日本医史学会総会、札幌医師会館
7月15-19日 内井「進化論と倫理」東京大学大学院(駒場)集中講義
8月1-2日 内井「進化論と倫理」放送大学面接授業
9月1・18日 伊藤「トスカーナに見る建築の流れ」(講演会)、日本イタリア京都会館
9月2-6日 集中講義(横山輝雄「社会的認識論」)
9月6日 内井「進化論から見た倫理」京都会議
9月27日 『科学哲学ニューズレター』15号
11月 内井「書評・伊藤笏康『科学哲学』」、『科学哲学』29
11月16日 伊藤「ガリレオとデカルト」、第29会日本科学哲学会大会シンポジウム「近代 における科学と哲学」、香川大学
11月30日 内井「進化と倫理」、人間性の進化的理解に関する研究会、KKRニュー目黒
12月9-13日 内井「進化論と倫理」香川大学教育学部集中講義
2月4日 卒論試問
2月20日 『科学哲学ニューズレター』16号
3月20日 予餞会 + 謝恩会
3月28日 内井「エゴイズムと倫理との共存」、学際パネル「進化について」進化経済学 会、京大会館
編集後記 誰に頼まれたわけでもないが、今回は大変感銘を受けた本の書評を自発的に書いてのせることにした。本研究室も創設以来五年目を迎えた。これまで一部の方々には科学哲学ニューズレターを郵送してきたが、今回よりホームページの掲載のみに切り替ることにした。ホームページは本年四月の中旬に公開を始めたが、その後内井の最近の出版物の英文要約など適宜更新を行っているのでご贔屓に願いたい。(May 15, 1997. S. Uchii)
Last modified Nov. 29, 2008, 1999.
